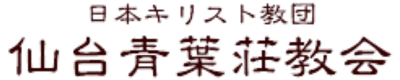「静まりから生まれるもの」
マルコ1章35―39節
牧師 野々川 康弘
今日の箇所は、シモンペトロの姑を癒した後の出来事です。33節を見ますと、「町中の人が、戸口に集まった」そう記されています。
このことから分かるのは、主イエスの名はすでに広まっていたということです。でも何故、主イエスの名が広まっていたのでしょうか。
それは、主イエスの起こす奇跡が、あまりにもすごかったからです。汚れた霊に取りつかれた人たちを癒したり、多くの病人を癒したりする奇跡は、人間離れしています。だから人々は、主イエスは一体何者であるか。そのことに興味を持っていたのです。
後の話に出てくることですが、マルコ8章28節を見てみますと、主イエスのことを「洗礼者ヨハネだ」という者や、「エリヤだ」という者や、「預言者の一人だ」という者がいたことが記されています。
何故このような、色々な憶測が飛びかっていたのでしょうか。それは人間離れしている奇跡を成せる人こそ、あの栄華を極めたダビデ王国の再建をしてくれる救い主ではないか。そういう期待があったからです。
この当時のユダヤの人たちは、ローマ帝国を打ち破って、自分たちの王国を再建するという救い。それを成してくれる人が現れることを、切に待ち望んでいたのです。つきつめて言えば、自分たちの生活が守られて、自分たちの暮らしが豊かになることを切望していたのです。
でも主イエスは、彼らの期待とは違う歩みをしていたのです。主イエスが汚れた霊に取りつかれた男を癒した御業も、多くの病人を癒した御業も、全ては近い将来、御自分がどのような救済を、十字架において成し遂げるかを指し示すためにした、御業だったのです。
確かに、主は憐み深く、今この時、困っている人たちに、御手を差し伸べます。彼らの必要を満たす救い。それをお与えになります。でもそれは、第一義的なものではありません。第二義的なものなのです。
何故なら、今癒されたとしても、いずれ人は死ぬのです。人に本当に必要なことは、神と人との関係に永遠に生きることの出来る命です。
そのことを主イエスはよく分かっていたのです。ですから、そのための宣教を、ガリラヤ地方で開始されたのです。でも人々は、表面的なところしか見ない。自分の現在の実生活における必要に対して、主イエスがどう応えてくれるのかということしか考えていないのです。
主イエスが何を願われているのかということに思いが行かないのです。それが意味しているのは、主イエス御自身を見ていないということです。もっといえば、主イエスの人格を慕っていないのです。主イエスの能力、すなわち、自分たちの王国の再建を成し遂げることが出来る能力。それを慕っていたのです。
それが明らかになった出来事は、主イエスが十字架に架かった時です。かつて、主イエスをほめたたえた人たちは、一転して、主イエスを罵りました。自分たちの王国の再建の夢が破られた時、人々は主イエスを罵るようになったのです。
私自身、人は本当にどこまでいっても、表面的なところしか見ないのだということに気付かされた経験があるので、それを紹介させて頂きます。企業で人事を担当している人は、仕事の助けになるので、産業カウンセラーという資格を取得する方が多くおられます。その資格取得のための講義で、人事の人が気をつけならないことの一つとして、ハロー効果というのを習います。ハロー効果とは、いつも挨拶が出来るということだけで、この人は対人関係を上手くやれると判断をしてしまうことです。そのような錯覚に陥ってしまうことの危険性を習うのです。人は一つのことが優れていると、それを基準に、他のあらゆることも優れていると過大評価してしまうのです。そのような人事の失敗事例を、いくつもその学びの中で紹介されました。本当は対人関係が苦手なのに、挨拶が出来るということだけで営業に回されて、実際は適性が無いために、仕事が続けられなくなってしまった事例なんかも学びました。
誤解しないで頂きたいのですが、挨拶が出来るということはとても大切なことです。その人の印象は、格段に良くなります。でも、挨拶が出来るということだけで、人間関係を上手くやっていくことが出来る。そう判断出来るかどうかは、別の話です。
人は、相手を表面的なところしか見ない傾向があります。その人の人格を注意深く見ていないことが多々あるのです。人は本来の相手を見るのではなく、自分が受けた印象を通してでしか、相手を見ようとしない傾向が強いのです。
主イエスは、確かに人でしたが、神でもあるのです。主イエスは、群集や弟子が、御自分の人格を慕っていないこと。御自分の真意を分かろうとしていないこと。そのことを良くご存じでした。
人々や弟子たちが、御自分の奇跡的な御業や、ダビデの時のような王国を再建する力、それを慕っていたことをよく御存じだったのです。
主イエスは本当の意味で求められているのではなくて、御自分の力のみが利用されようとしているのを感じていて、とても孤独だったと思います。人々の主イエスの力に対する期待が渦巻く中で、彼らの勝手な期待に振り回されることなく、父なる神から任された使命を全うしようとするのは、どんなにエネルギーが必要だったことでしょう。
しばしば、主イエスは疲れを覚えたのです。だから主イエスは、土曜日に、会堂で悪霊を追い出す癒しの業を行い、日曜日にペテロの姑を癒し、多くの人々を癒した業を成した後の月曜日に、35節にあるように、人里離れた所へ出ていって、そこで祈られたのです。
ダビデ王国再建の期待が自分に押し寄せてくる中で、あの主イエスでさえも疲れを覚えて、人里離れた所へ出て行って、祈っておられた事実を、私たちは心に留める必要があると思います。
主イエスでさえ、そのようにされたのです。そうであるならば、私たちもしばしば、人々の所から離れて、ひとり静まって祈る休息の時が必要なのです。
人々の思い描く期待の渦巻く所から離れて、独り神の前に静まる中で、人々からのプレッシャーから解放されてこそ、自分が主にあって、本当になすべきことに専念する力が育まれるのです。
人々の思い描く期待の渦巻く所から離れて、独り神の前に静まる中で、人々からのプレッシャーから解放されてこそ、キリスト者として、この世に調子を合わすことなく、この世で生きることが出来るのです。
私たちは、人々の中にずっと浸っていると、ついつい人の期待に迎合してしまう弱さがあるのです。ひとり神の前に静まることのない生活は、自分の活動が、人々の期待に応えうるかどうかということでしか、自分を評価することが出来ない自分になっていってしまうのです。
そうすると、いつの間にか人の顔色を伺って、自分が人々から良い評価を得ることに、執着するようになるのです。そして、最期には、人の評価を得るためだけに、自分が生きているみじめな自分を認めると、自尊心が傷つくので、自分がしていることを正当化するようになるのです。
そうなると、残念ながら、キリスト者といえども、この世に迎合して生きる人になってしまうのです。それは、塩気が失われた塩です。
主イエスの歩みは、人の期待に応えようとするものではありません。その事実として、主イエスは、律法学者やユダヤ人たちの期待に応えるような歩みをしませんでした。それどころか有害な者と見なされて、彼らの手によって、十字架に架けられ殺されたのです。でも、主イエスが、十字架に架けられなければ、本当の意味で、人々が憩うことの出来る救いに、導くことは出来なかったのです。まさに、マルコ12章10節に「家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となった。」と、記されている通りです。
このことを象徴するような話があります。
ある場所に、一本の巨大な、節だらけの、見事な樫の老木がありました。すると大工は弟子に、「この木はどうしてこんなに高く、大きく育って、たくさんの節をつけた見事な老木になったか分かるか」そう尋ねたのです。そうしましたら、弟子は師匠をじっとみて「分かりません。何故でしょうか」と言ったのです。そうしたら、大工は「それは、これが役に立たない木だったからだ。もし、この木が役立つものだったら、とっくの昔に切り倒されて、机とか椅子になっていた。しかし、何の役にも立たなかったからこそ、おまえがその木陰に座って憩うことのできる、これ程の高さの見事な木になれたのだよ。」そう答えたのです。
この話のように、主イエスはユダヤ人たちから、必要と思われなかったが故に、父なる神の贖いの御計画は完成したのです。主イエスが、ユダヤ人たちから嫌われたからこそ、十字架の死を通して、全世界の人たちを、救いに導き入れて、真の安息をもたらすことが出来るようになったのです。
とはいえ、人々の期待に流されずに、福音の本質がぶれないように生きるのは主イエスであっても至難の業だったのです。だから、主イエスはひとりで、父なる神の前で、静まる時を持たれたのです。
そのことから学ばされるのは、私たちもまた、ひとり神の前で静まることによって、自分はどれほど人の役に立つだろうかとう思いにとらわれず、のびのびと、キリスト者として成長することが出来るようになるということです。
人の期待に流されることがなくなれば、主イエスの十字架の愛をもって、つまりは、自分を分け与える愛を持って、隣人と交わることが出来るようになるのです。私たちがそうなれば、この世で、キリストの香りを放つ者となるのです。
聖書に話を戻しますが、36節~37節では、主イエスが静まって祈っていたら、シモンや他の弟子たちが、主イエスを探しに、追いかけて来たことが記されています。
おそらく、彼らは、悪霊を追い出す御業や、病人を癒す主イエスの奇跡によって、カファルナウムでの人々の関心が自分達に高まっているのを感じて、気分が高揚していたのでしょう。寂しい、静かな場所に主イエスが退いて祈る必要があった意味を、到底、理解出来なかったのです。
それどころか弟子たちは、カファルナウムの人々の期待に応えて欲しい。人々の心を掴むチャンスを逃して欲しくない。そう考えていたのです。
その証拠に、「みんなが捜しています。」という理由で、主イエスの後を、シモンをはじめとする弟子たちは、主イエスを追って来たのです。
でも、主イエスはひとり静まって祈っていたからこそ、弟子たちの言葉に振りまわされることなく、父なる神の御旨を正確に受け止めることが出来たのです。主イエスが、父なる神から示されたことは、弟子たちと真逆です。「これ以上、カファルナウムだけに留まっていてはいけない。」そのことを示されたのです。だから主イエスは、38節に記されている通り、「近くの他の町や村へ行こう。そこでも、わたしは宣教する。そのためにわたしは出てきたのである。」そう弟子たちに言うことが出来たのです。
今朝、私たちもこの主イエスの在り方に学びたいと思います。皆さんは、慌ただしい生活の中で、ひとり神の前で静まる豊かな時を持っているでしょうか。私たちは人の期待に応えるために何か行うことばかりを考え、神の御前にひとり静まることをないがしろにはしていないでしょうか。今朝、主は言われています。「騒がしいところからひとり離れて、静かな所へ行って、静まって、祈ることを大切にしなさい」
この神からの語りかけに耳を傾けるなら、私たちは人々の期待に流されずに、巨木のような信仰が私たちの内に形成されるのです。その結果、真の憩いをもたらす救いを、人々に指し示すことが出来るようになるのです。
主イエスは、私たちがなかなか、騒がしいところからひとり離れて、静かな所へ行って、静まって、祈ることを大切に出来ない程、神を軽視している私たちの罪の身代わりとなって、十字架にお架かりになられたのです。
その救いに感謝して、今週一週間、密室の祈りを大切にして、皆さんと共に歩んでいきたいと思います。
最後に一言お祈りさせて頂きます。