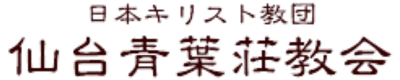使徒言行録10章1節-33節
「人間らしい歩み」
牧師 野々川康弘
今日の箇所を見ますと、ヤッファと、カイサリアという2つの町が出てきます。ペトロは神に示された、ローマ軍の百人隊長コルネリウスに招かれて、1日で、ヤッファからカイサリアへ行きました。1日で、カイサリアからヤッファへ行けたということは、ヤッファとカイサリアは、近い距離にあったということです。
でも、この二つの町の間には、とても大きな隔たりがありました。
そのことを知るためには、二つの町の歴史、それ知る必要があります。
まず、ヤッファですが、ヤッファは、旧約時代から続く、とても古い町です。ダビデソロモン時代は、地中海に面した、唯一の港町でした。ソロモン神殿の建設に使われたレバノン杉は、ヤッファの港から運び込まれました。
それだけではありません。紀元前780年頃のヨナが、アッシリアの都、ニネベへ行けという神の命令に背き、反対の方向に逃げる時に、船出した場所も、ヤッファの港でした。
ヤッファは、ユダヤの民にとって、とても親しみがある港町だったのです。
その一方で、カイサリアは新しい町です。カイサリアを、大きな港町にしたのは、イエス・キリスト時代の、ヘロデ・アンティパスの父、ヘロデ王です。彼が、ローマ皇帝カイサルの名にちなみ、カイサリアと命名したのです。
その名前の通り、カイサリアには、劇場や競技場、水道、皇帝アウグストゥスを祭る神殿がありました。そんなカイサリアは、紀元6年以降、ローマ帝国の直轄領になりました。そのようにしたのは、総督や軍団を駐屯させて、ユダヤ支配の、要の町とするためです。
だから、ローマ軍の百人隊長、コルネリウスがいたのです。
つまり、ヤッファは、ユダヤの民に、古くから親しまれていた、町であった一方で、カイサリアは、異邦人が、ユダヤの民を支配するための町だったのです。この2つの町の間には、越えがたいユダヤ人と、異邦人の隔たりがあったのです。
だから、一日で行くことが出来る近くの町に、ペトロが伝道にいったという、そんな単純な話ではないのです。
ペトロがヤッファから、カイサリアに行くのには、大きな一歩があったのです。その大きな一歩とは、異邦人への伝道の開始という、大きな一歩です。だから、ユダヤ人キリスト者たちは、世界伝道の始まりは、使徒言行録2章のペンテコステの出来事ではなくて、此処が、世界伝道の始まりだ。そう主張するのです。
それはそうと、ユダヤ人たちは、自分たちが神に選ばれた民であることを誇って、他の民族のことを「異邦人」と呼び、蔑んでいました。その証拠が28節です。そこでペトロは、「あなたがたもご存じのとおり、ユダヤ人が外国人と交際したり、外国人を訪問したりすることは、律法で禁じられています」そう言っています。
ユダヤ人と異邦人の間には、そういう隔たりがあったのです。そして、その隔たりは、主イエスの救いを信じる者たちの群れであっても、そう簡単に乗り越えられるものではなかったのです。
ユダヤ人たちは、外国人と交際したり、外国人を訪問したりすることを、ずっと禁じられた信仰教育を受けていました。
そんな彼らは、ダビデソロモン時代に栄華を極めた、あのイスラエル国を再建して下さること。そのことを救い主に期待していたのです。そういう救い主のイメージから、なかなか抜け出すことが出来なかったのです。そんな彼らが、伝道の対象にしていたのは、基本的には、ユダヤ人の血を引く人たちでした。
でも、主イエスの救いは、そんな彼らの思いを超えていたのです。父なる神が復活させた主イエスは、使徒言行録1章8節で、「あなたがたの上に聖霊が降ると、あなたがたは力を受ける。そして、エルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また、地の果てに至るまで、わたしの証人となる」そう言っておられました。
主イエスの福音は、ユダヤ人という一つの民族から、主イエスの十字架・復活・昇天の救いを信じる全ての人たちにまで、広げられたのです。その救いを信じる人たちこそが、神の民なのです。
でも12弟子の意識、エルサレム教会の意識は、まだその新しい事態に、追い付いていなかった。使徒たちの代表といえる、聖霊をサマリア教会の人たちに授けたペトロでさえ、そうだったのです。
ペトロ以外の12弟子も、ペトロのサマリア伝道の報告とか、フィリポの、エチオピア人の宦官が救われた報告を受けていたはずなのに、主イエスの救いの御業を信じる人たちこそが、新しい神の民であると、分かっていなかったのです。
10章後半から11章まで見ますと、異邦人が教会に加わることに対し、彼らが躊躇していたことが記されています。
そのことから分かるのは、ヤッファとカイサリアの間の隔たりを、乗り越えるのは、別の言葉で言えば、ユダヤ人と異邦人の間の隔たりを、乗り越えるのは、とても大変なことだったということです。
人間は、長年受け継がれてきた常識、それを覆すのは、とても大変なことなのです。
これは他人ごとではありません。私たちもそうなのです。私たちは、日本の文化に親しんでいます。そんな日本の教会の中では、キリスト教を信じているのに、悪いことをしたら罰が与えられるとか、神に召された人に、お供えものを捧げるとか、赦しの実践は、嫌な事をされたら水に流すことであるとか、そんなふうに考える人たちがいます。
でもキリスト教は、どんなに悪いことをしても、悪いことをしたと、認めれば、罰ではなく、赦しが与えられます。聖書の神は、罪の赦しを与える神なのです。また、神に召された人に寄り添う意思があるならば、お供えものではなく、信仰継承をするのです。また、罪を水に流す神ならば、主イエスが十字架にお架かりになる必要は無かったのです。
私たちが日々聖書を知らされて、自分勝手に思い描いている神像が崩されて、自分の照準が、本当に聖書になっていくことは、案外とても大変なことなのです。
人間は何処までも、自分が歩んできた在り方、それを中心にして生きています。それ程、自我が強いのです。そういう罪深い存在が、人間です。
でも、今日の箇所を見ますと、ユダヤ人と異邦人の間の隔たりが、乗り越えられたことが記されている。
何が、ユダヤ人と異邦人の間の隔たりを、乗り越えさせたのでしょうか。
結論から言うと、ユダヤ人と異邦人の間の隔たりを、乗り越えさせたのは、人間の信仰と、人間の体験です。
2節に、コルネリウスのことが、このように紹介されています。「信仰心あつく、一家そろって神を畏れ、民に多くの施しをし、絶えず神に祈っていた。」
更に22節では、コルネリウスの召し使いたちが、彼のことを、こう証言しています。「百人隊長のコルネリウスは、正しい人で神を畏れ、すべてのユダヤ人に評判の良い人。」
これらのことから分かるのは、コルネリウスの「信仰」は、「神を畏れ」る信仰だったということです。彼は、神を「畏れて」いたからこそ、自分の思い込んでいる、イスラエルの神になっていなかった。
彼と、彼の家族は、異邦人でありながら、ユダヤ人たちの神を畏怖し、祈っていたのです。4節に「施しは、神の前に届き」そう記されています。此処でいう施しは、イスラエルの民に対する施しです。
ローマの軍の百人隊長でありながら、彼は、ユダヤ人と、ユダヤ人の信仰を尊敬して、彼らのために、色々な助けの手を、差し伸べていたのです。エチオピア人の宦官と同じように、主なる神を、心から求めていた、異邦人だったのです。神はそんな彼の信仰と、祈りに応えて、ペトロとの出会いを与え、主イエスの救いにあずからせたのです。
またペトロも、サマリア人が信仰を得て、教会に加えられたことを体験していました。その体験が、異邦人との間の隔たりを、乗り越える備えになったのです。
コルネリウスの信仰と、ペトロの神体験、それが異邦人に、主イエスの救いが宣べ伝えられていくために、豊かに用いられたのです。
神のなさることに、意味の無い事など何一つないのです。神を侮ってはいけないのです。
私たちはすぐに、「こんなこと意味がない!」そう思うのです。何故そう思うのか。それは、自分の力を過信して、神を侮っているからです。
神は全て知っておられる。その上で、全てを用いて、私たちを導いておられるのです。
そのことを、私たちは、深く心に刻み込む必要があります。
とはいえ、ペトロが、ヤッファからカイサリアへ、つまり、ユダヤ人と、異邦人の隔たりを越えて、出かけて行くことが出来たのは、コルネリウスの信仰や、ペトロの神体験に基づいた、彼の判断ではないのです。
先程、私が申し上げたことと、矛盾しますが、ペトロと、コルネリウスが、幻を見たこと。それが、ユダヤ人と、異邦人の隔たりを越えて、ペトロがカイサリアへ、出かけて行くことになった直接原因なのです。
2人が神からの示しを受けたこと。それが、ユダヤ人と、異邦人の隔たりを越えて、ペトロがカイサリアへ出かけて行った、直接原因なのです。
コルネリウスが神に祈っていた時、天使に「ヤッファへ人を送り、ペトロと呼ばれるシモンという人を招きなさい」そう命じられました。そのことが5節に記されています。
でも彼は、ペトロのことを知らなかったのです。天使が、「ペトロがいる場所は、皮なめし職人シモンの家である。その家は海岸にある。」そのような細かいことを、教えたのです。
天使がペトロを、彼の家に招くように言ったのです。彼はそれに従って、ヤッファに人を遣わして、ペトロを招いたのです。
ペトロにしても、コルネリウスの使いが到着しようとしていたころ、祈っている中で、神から幻が与えられたのです。
天が開き、大きな布のような入れ物が、四隅を吊るされて、彼の目の前に降りて来た。その中に、いろいろな獣、地を這う蛇のような動物、そして鳥が入っていたのです。それらの動物は、律法によって、汚れたものとされていた食材です。
「食べてはいけない。」そう命じられていたものばかりです。
でも天から声があって、「ペトロ、身を起こし、屠って食べなさい」そう神が、彼に語りかけたのです。彼は、「主よ、とんでもないことです。清くない物、汚れた物は何一つ食べたことがありません。」そう答えました。すると、「神が清めた物を、清くないなどと、あなたは言ってはならない」そう言っていたのです。ペトロはその幻を、三度、続けて見たのです。3という数字は完全数です。
「いったいこの幻は、どういう意味なのか、神は自分に何を語ろうとしておられるのか。。。」そう彼が考え込んでいた時、コルネリウスの使いの者たちが到着したのです。
その時、今度は「霊」によって示しが与えられたのです。「三人の者があなたを探しに来ている。立って下に行き、ためらわないで一緒に出発しなさい。わたしがあの者たちをよこしたのだ。」そう言ってきたのです。これはとても具体的な示しです。幻と、霊の示しが、ここまで具体的にあたえられたなら、その意味は明らかです。
ペトロは、「異邦人であるローマの百人隊長コルネリウスが、神の示しを受け、自分を招き、主イエスの救いを聞こうとしている。だからこそ行け。そう神が言っておられる。大きな布(ぬの)のような入れ物の中の、汚れた動物たちとは、異邦人たちのことだ。神は、自分が彼らを清めたから、私がそれを清くないと言ってはならない。そう言っておられる。」そのことが分かったからこそ、ヤッファからカイサリアへ向かったのです。
異邦人伝道が実現したのは、神がペトロと、コルネリウスに与えた幻によるのです。つまり、聖霊が2人に働きかけたからこそ、ユダヤ人と異邦人の隔たりが、乗り越えられたのです。
神が2人に働きかけて、2人ともその働きかけを受け入れたことが大事なのです。先行恩寵があって、その恩寵を、畏れと感謝を持って受け入れてこそ、主イエスの福音が働いて、人と人との隔たりを乗り越えて、伝わっていくようになるのです。伝道は、そういうかたちで実現していくのです。
10章は、表面的に見れば、ペトロのコルネリウスへの伝道であり、ペトロのカイサリア伝道です。でも実際は、ペトロの伝道ではありません。
神の示しに、畏れと感謝をもって、2人が神に従っただけのことなのです。その結果、主イエスの救いが、ペトロからコルネリウスへ、ユダヤ人から異邦人に、手渡されたのです。
伝道は、私たち人間が、何かをすることによって成し遂げられる業ではない。むしろ、人間的な思いが先行するなら、主イエスの救いは後退していくのです。
聖書が私たちに求めることは、神が語りかけてくること、神がなさる御業、それを畏れと感謝を持って受け入れて、それに従うことです。
御言葉を伝える人も、伝えられる人も、神が語りかけること、神がなさる御業、それを畏れと感謝を持って受け入れて、従った時にこそ、人と人との間に在る、色々な隔たりが乗り越えられて、主イエスの十字架・復活・昇天という救いの御業が、伝わっていくようになるのです。
心の痛い話ですが、今日の箇所が教えている最も大事なことは、伝えられる人より、伝える人の方が、神の御業に対するより大きな服従の決断を求められるということです。
ペトロがまさにそうでした。彼は、触れると汚れてしまうと思っていた異邦人に、触れることを求められたのです。彼は幻の中で、汚れたものを食べることを三度断りました。先程も申し上げましたが、3という数字は完全数です。
何故そこまで頑なに拒んだのでしょうか。それは、自分で自分の清さを保とうとしていたからです。
つまりペトロは、自分が望んでいる理想の自分に、自分が思い描く自分に、自分が満足できる自分に、留まっていたかったのです。だから頑なに拒んだのです。
ペトロは、自分の在り方に固着していたのです。自分の主を、自分として、神を自分の従としていたのです。主従逆転していたのです。神を畏れていなかった。その結果、彼は、神に変えられることを拒み、今の自分のままでいようとしたのです。自分の自尊心と誇りを、自分で守ろうとしていたのです。でも、その度ごとに、神はペトロに「神が清めた物を、清くないなどと、あなたは言ってはならない」そう言われたのです。
自分がこうありたいと思う自分であり続けようとすること。自尊心や誇りを自分で守ろうとすること。そういう姿勢は、主イエスを無視する罪のために、主イエスが十字架に架かられたことを否定すること、拒否することになるのです。そしてそれは、主イエスの救いは自分に必要無い。自分の力で自分らしく生きていく。そう言っていることになるのです。
神を拒否したペトロは、キリスト者らしく、最後はちゃんと自分に死にました。自分の自尊心や誇りをかなぐり捨てて、主イエスを自分の主として受け入れて、自分の主である主イエスに服従して、神の言葉がちゃんと立つように歩んだのです。
ペトロが主イエスを自分の主として、主イエスに服従した歩みをしたからこそ、ユダヤ人と異邦人の隔たりを、乗り越えることが出来て、主イエスの救いが、全世界に広がっていったのです。
伝道とは、神の言葉を伝える者が、本当に神に服従することを通して、実現していくのです。
伝道は、人を神に従う者に造り変えることではありません。それが出来るなら、私たちに神は必要ありません。人間が自分たちの力で、神に認められる義を獲得出来ていくならば、主イエスの救いは必要ないのです。人間が自分たちの力で、神に認められる義を獲得出来ないからこそ、主イエスの救いの御業がなされたのです。
ですから伝道は、誰かに神の救いを宣べ伝えるということではなくて、自分のアイデンティティーが、ちゃんと主イエスの十字架になっていることです。自分のアイデンティティーが、ちゃんと主イエスの十字架になるならば、自分の主が神となり、いつもその神に、服従する者となる。そのように自分が神に造り変えられていってこそ、ちゃんと聖書が伝えようとしている御言葉、ちゃんと聖書が説いている主イエスの救い、それが隣人に伝わっていくようになるのです。
もし私たちが、神を自分の主とする関係修復のために、主イエスの救いの御業がなされたことを見失うならば、私たちの伝道は、人間の業になりさがります。
そうなれば伝道は、誰かを慰めてやろうとか、諭してやろうとするものになってしまう。あるいは、「罪深い自分には伝道なんか出来ません」そういって、主イエスの救いを宣べ伝えることに、しりごみをするようになるのです。
それらはどちらも、伝道に対する間違った姿勢だと、言わざるを得ない。伝道は私たちの自己主張ではありません。伝道は、神に服従している私たちの姿です。そして、神に服従している私たちの姿は、主イエスの十字架が、自分のアイデンティーティーとなっているところにこそ、生まれてくるのです。
主イエスの十字架が、自分のアイデンティーティーになっていてこそ、主イエスに対する服従が生まれて、人と人との間を隔てている、溝や壁や対立が、乗り越えられて、主イエスの救いが広がっていくようになるのです。
では、主イエスに対する服従、別の言葉で言うと、神に服従するとは、一体どういうことなのでしょうか。その参考になるのが、コルネリウスの姿勢です。
25節を見ますと、ペトロを迎えたコルネリウスが、その足もとにひれ伏して拝んだことが記されています。
コルネリウスは、神に派遣されたペトロを、まるで神であるかのように、拝んだのです。それは、権威を持った神が遣わしたのが、ペトロだったからです。だから、ペトロの権威を認めたのです。神の権威を認めていない人は、神によって、自分の上にたてられている人の権威を認めることが出来ないのです。
神の権威を認めていない人は、会社でも、教会でも、自分の上の権威を認めません。逆に言えば、会社でも、教会でも、自分の上の権威を認めて歩める人は、神の権威を認めて歩むことが出来るのです。
それはそうと、コルネリウスが、ペトロの足もとにひれ伏して拝んだ時、ペトロは彼を起こして、「お立ちください。わたしもただの人間です。」そう言いました。
この言葉は、口語訳聖書では「わたしも同じ人間です」そう記されていました。口語訳の方が、原文の意味を正確に表しています。
「わたしも同じ人間です。」この言葉は、今の私たちの感覚ではなく、当時のユダヤ社会の感覚から聴けば、とてもびっくりする言葉です。
異邦人であるコルネリウスと、ユダヤ人であるペトロが、同じ人間であることを認めるのは、当時のユダヤ人の言葉とは思えないびっくりする言葉です。
「わたしも同じ人間です。」この言葉をペトロが言ったということは、彼がそれまで抱いていた、異邦人に対する伝統的な考え方を捨てることができたということです。ユダヤ人と異邦人との間の溝を乗り越えることができた。そのことは、「人間は皆平等」という、ヒューマニズムなことではありません。
そうではなくて、ペトロが、主イエスに背を向ける者ではなく、主イエスと向き合う者になれたということです。それが意味しているのは、自分の原罪を思い知らされて、心底悔い改めたからこそ、人と人との間を隔てる壁を乗り越えて、主イエスの十字架が立つ交わりを、確立することができるようになったということです。主イエスの十字架が立つ交わりとは、相手の人権を尊ばなければならないという、道徳を大切にする交わりではありません。そうではなくて、主イエスの十字架の権威を尊ぶ交わりです。
ペトロは、コルネリウスとの間に、そういう交わりを確立することが出来たのです。じゃあコルネリウス側は、どのようにして、神の権威を尊ぶ交わりの実現に至ったのでしょうか。それを示しているのが33節の彼の言葉です。彼はペトロに、「よくおいでくださいました。今わたしたちは皆、主があなたにお命じになったことを残らず聞こうとして、神の前にいるのです」そう言っています。
つまり、ペトロの言葉なんかではなくて、神の言葉を聴くために、ペトロの前に立っていたのです。それが、ペトロを迎えたコルネリウスの姿勢です。
そこにこそ、人と人との間の色々な隔たり、色々な溝、それ乗り越える交わりが、生まれるのです。
人が人につまずかないためには、もっと言えば、私たちが、人間としてのいろいろな違い、対立、隔たり、溝を乗り越えて、真の交わりを持つことができるようになるためには、神を礼拝することです。つまり、神にちゃんと仕えることです。
神に仕える姿勢で、神に遣わされた人の前に立つ人が、本当の神の御言葉を聞くことが出来る人です。
なので皆さんにお願いしたいことがあります。それは皆さんが、罪深い私という人格に左右されることなく、「今自分は、神がたてている私を通して、神の御言葉を聴かせるために、神にこの礼拝に招かれた。」そういう思いをもって、礼拝に出て頂きたいと思います。
神に仕えるという本当の礼拝を守る時にこそ、神の御言葉が、恵みに満ちた語りかけとなって、皆さんの心に響いてくるようになるのです。
この世に神の権威によって立てられていないものは何一つありません。
神の権威を恐れ敬うこと。それが、私たちの祝福となるのです。
そのことを覚えて、今週一週間、皆さんと共に歩んでいければと願っています。
最後に一言お祈りさせて頂きます。