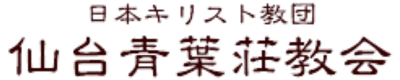使徒言行録9章32節-42節
「主に立ち返れ」
牧師 野々川康弘
今日の話しは8章14節~25節の続きです。つまり、ペトロとヨハネが、エルサレムからサマリアに出向いて、サマリアのキリスト者たちに手を置いて祈った時に、彼らに聖霊が与えられた続きが今日の箇所です。
今日の32節を見ますとこう記されています。「ペトロは方々を巡り歩き、リダに住んでいる聖なる者たちのところへも下って行った」
ペトロはサマリアに行ったことをきっかけに、既に各地にあった教会を巡り歩きました。
実は、彼がサマリアに行った時も、サマリア教会に行っていたのです。今日の箇所を見ましても、リダの教会に行ったことが分かります。その証拠が、「リダに住んでいる聖なる者たちのところへも下って行った」という32節の言葉です。
32節がいっている「聖なる者たち」とは、罪から分かたれた者たちのことです。つまり、主イエスの救いを信じて、教会に属しているキリスト者たちのことです。
また、今日の36節以下を見ますと、ペトロがヤッファに行ったことが記されています。それも、ヤッファの弟子が、つまり、ヤッファの教会が、彼を招いたからです。
私が何を言いたいかといえば、エルサレム教会から、サマリアに派遣されたことをきっかけに始まったペトロの旅行は、既に存在していたキリスト者たちの群れである教会を訪ねて、力づけて、励ますことだったのです。
そういう教会の訪問のことを、教会用語で「門安」と言います。言葉の意味は「安否を問う」ということです。でも、元気かどうかを確かめるだけではありません。問安は、教会の信仰を確認して、教会の信仰を整えることを目的としています。教会の信徒たちの信仰生活に励ましを与えるために訪問がなされるのです。
ペトロが各教会を問按していた当時、生まれたばかりの教会には、まだ御言葉を教える教師がいなかったのです。信徒の群れが出来てはいても、それを指導して、導く人が、それぞれの教会にいませんでした。
そういう教会を導いて、諸教会の信仰の一致のために、最初は使徒たちが、後には使徒たちの信仰を継承していた長老たちが、今でいう牧師たちが、教会を巡回して、信仰の指導をしていたのです。
ペトロが各地の教会を訪れたのには、そういう意味があったのです。そして、そんなペトロの門安は、ペトロの個人の伝道の業ではなく、教会の業だったのです。
私がいっている教会とは、一つの個教会のことではなくて、エルサレムから始まって、ユダヤとサマリアの各地に広がった諸教会全体のことです。諸教会全体を指導する人として、ペトロはあちこちを巡回していたのです。
実は、日本基督教団の教職は、個教会に教会籍がありません。その理由は、教職は日本基督教団という全体教会を、指導するために召されている人たちだからです。そして、個教会の教派にあった指導をしていくために、日本基督教団の中の個教会から招聘されるシステムになっているのです。
それはそうと、使徒言行録は個教会の成長というよりも、全体教会の成長を描いています。だから、話はエルサレム教会のペトロのことからフィリポのこと、そして、そこからサウロの話になり、再度、エルサレム教会のペトロのことに戻っているのです。そういう構図に、ルカが意図的にしているのです。
ルカは、一人一人の伝道者の働きを描いて、その伝道者一人一人の働きが、全体教会の成長に繋がっていることを指し示しているのです。
今日のペトロの働きも、その一環として読んでいく必要があります。
今日の箇所を見ますと、リダとヤッファで、ペトロが奇跡を行なったことが記されています。リダでは、8年間中風で床についていたアイネアを癒しました。ヤッファでは、死んだタビタという女性キリスト者を生き返らせました。
今日の箇所を見る時、「今の教会にも、そういった力を持った人がいてくれれば」そう思うかもしれません。でもそういう思いに捉われて、使徒言行録を読むのであれば、使徒言行録の話しの腰を折ることになります。使徒言行録が、今日の箇所で言わんとしていることは、驚くべきペトロの力ではありません。
今日の箇所を通して、使徒言行録が言いたいことは、教会で原罪という病からの解放の御業、復活の命が与えられるという御業、それが行なわれたということです。もっと正確に言えば、ペトロの門安でそういったことが起こったのです。教会が問安を受けて、正しくしっかりとした信仰指導を受けて整えられていった時に、原罪という病から解放されて復活の命が与えられるという素晴らしい神の御業が起こるのです。
でもそれは、ペトロの個人の力でも、教会の人たちの力でもありません。原罪という病から人々を解き放ち、復活の命を与えるのは、教会の頭である主イエスです。
主イエスの救いの御業が行なわれていくようになること。それが、教会の正しい成長です。優しい共同体が構築されるとか、自己肯定感を持てる共同体が構築されることが教会成長では無ありません。
正しい会教成長をしていくためには、主イエスの御業が、私たち人間の色々な思いにより、妨げられることがなくなる必要があるのです。
そうなっていくために、ペトロは各地に出来た教会を問安したのです。つまりペトロは、私たちの色々な思いにより、主イエスの教えの筋から外れていくことがないようにするために、各地に出来た教会を問安したのです。
ペトロは教会を問安して、人が原罪という病に侵されていて、死に対する恐怖に怯えている中にあって、主イエスの原罪からの解放と、復活の命を指し示したのです。
実は、タビタの復活の出来事は、マルコによる福音書5章の、主イエスによる会堂長ヤイロの娘の復活と重なるのです。そこで主イエスは、「タリタ、クム」そう言って少女を生き返らせました。それは「少女よ、わたしはあなたに言う。起きなさい」そういう意味のアラム語です。ペトロもタビタにアラム語で、「タビタ、クム」そう言ったのです。つまりペトロは、主イエスご自身がなさった復活の御業と同じことを行ったのです。40節の「皆を外に出し」たというのも、主イエスがなさったことと同じです。
今日のアイネアの病を癒した業も、マルコによる福音書2章の、中風の人を癒した主イエスの御業と重なります。主イエスは中風で寝たきりの人に対して、「わたしはあなたに言う。起き上がり、床を担いで家に帰りなさい」そう言って彼を癒しました。ペトロがアイネアに語った言葉は、それと同じです。
つまり、ペトロが行なった癒しの業、死者を復活させた業は、主イエスの御業と重なるのです。でも、ペトロが主イエスの真似をしたわけではありません。使徒言行録の著者ルカが、今日の箇所を通して言わんとしていることは、ペトロを通して行なわれた救いの御業は、主イエス御自身の救いの御業であるということです。そして、主イエスの救いの御業とは、原罪からの解放と、復活の命を与えることです。そんな御業は、主イエスにしか出来ません。そんな主イエスしか出来ない御業が、諸教会で起ったのです。
ペトロは、主イエスが諸教会で、救いのみ業を行う器として用いられたにすぎません。ペトロ自身が奇跡を行なう力を持っていたわけではないのです。ペトロが、何か自分が思い描いたことを実現したのではないのです。彼は、自分はからっぽになって、主イエスの救いの御業を、そのまましたのです。つまり彼は、主イエスの救いの御業が指し示されるために、聖霊の働きの道具として、器として、用いられただけです。
私たちは9章で、サウロの回心を学びました。サウロの回心は、サウロが自分の思いや、自分の熱心さを持って生きていたところから、神の御業に用いられる器に変えられた出来事です。
同じことがペトロにも起こっていたのです。彼も、主イエスに用いられる器として歩んでいたのです。ペトロ自身は、力が無くて欠けの多い器です。でもそのような者が、主イエスの救いの御業を、教会で行なう者として用いられたのです。
ペトロは、主イエスの救いの御業が、教会に現れるための器とされたのです。ということは、私たちがペトロのように、ちゃんと主イエスの救いの御業が現れる器となれば、今の私たちの教会も、原罪という病からの癒しや、死んで滅び去るように定められた者に、復活の命が与えられるようになる奇跡が起るということです。
仙台青葉荘教会が、自分たちの教会という意識ではなくて、ちゃんと主イエスの全体教会の内の一教会であるという意識をちゃんと持っているとすれば、主イエスの救いの御業が、教会に連なっている私たちの間に現れるのです。御国が私たちの間に到来するのです。そこにこそ、本当の神の平和(神との関係の修復、隣人との関係の修復)が実現するのです。
繰り返しになりますが、使徒言行録が書き記しているのは、個人の特別な力によって、素晴らしい奇跡が行なわれたということではないのです。そうではなくて、主イエスに仕えていた弟子たちが、ちゃんと主イエスに用いられる器になっていたからこそ、教会に、原罪からの解放と、復活の命が与えられるという主イエスの救いが現れたのです。ということは、器は必ずしもペトロでなくてもよいのです。私たちの中の誰であってもよいのです。
器として用いられる人が、特別に立派な力がある人である必要は全くないのです。逆にそれは、かえって邪魔になります。
何故、ユダヤ人たちが神の民として選ばれたのでしょうか。その理由が申命記7章7節に記されています。そこを見ますと「主が心引かれてあなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民よりも数が多かったからではない。あなたたちは他のどの民よりも貧弱であった。」そう記されています。かつてユダヤ人たちが神に選ばれた理由は、他のどの民よりも貧弱だったからです。神は弱い人を好みます。その理由は、強い人は自分を誇ろうとするが故に、神が介入する余地が無いのです。その結果、神の栄光が豊かに現れないのです。
神の民の資質は、自分の弱さや破れを認めて、主イエスに、自分の全てを明け渡す器になれるかどうかです。それがとても重要です。
仙台青葉荘教会に連なる私たちが、主イエスに、自分の全てを明け渡す器になることが出来ていれば、ペトロのように、主イエスの救いの御業が、教会に現れるための働きを成すことが出来るようになるのです。今日の箇所に出て来る救いの御業と同じことが、この仙台青葉荘教会の中でも起こるようになるのです。
今日の箇所に記されているのは、病気で寝たきりの人が癒されて起き上がったり、死んでしまった人が生き返ったりすることです。そういう奇跡の業が、教会には実際にあります。でもそれが、今日の箇所の第一義的なものではありません。
使徒言行録でも、福音書でも、言葉通りの癒しや、言葉通りの死者の復活が、主イエスの救いではありません。
癒しの業や、死者の復活の業は、主イエスが、私たちの救い主であることを示すためになされた御業です。
もし、病が癒されることや、死んだ人が復活することが、主イエスの救いであるならば、救いに与る人は限りなく少ないことになります。
更に言えば、病が癒された人も、死から復活した人も、最終的には皆死んで、主イエスの御業は、最終的には死の力に打ち勝てなかった。そういう結論になってしまいます。
主イエスの救いの御業とは、病を癒したり、死者を生き返らせたりして、今この時を生きやすくするためのものではありません。
そうではなくて、病を癒したり、死者を生き返らせたりする主イエスの御業は、私たち人間の原罪という病を癒し、私たち人間を支配する死の力を打ち破ることを指し示しているのです。
そしてそれは、主イエスの十字架の死と復活によって実現しました。神の独り子である主イエスが、私たちと同じ人間として、この世にお生まれになって、私たちの原罪を背負い、十字架に架かって死なれたのです。
父なる神は、その主イエスの十字架の死を受け入れることによってのみ、私たちの原罪を赦して下さいます。そして、父なる神が、神の子主イエスを、死者の中から復活させたのは、神の子となった人は、死で終わることがない永遠の命が与えられることを指し示しています。
原罪が、神との関係の死、隣人との関係の死を齎して、私たちの肉体の死をも齎すのです。
人間が、原罪という癌に蝕まれて以降、人間は死を恐怖して生きています。そして、死を恐怖して生きている私たちは、憎い相手への報復に、自分が恐怖している死を用いるのです。
あまり良い例えではありませんが、親から体罰を受けて育った人は、子供に体罰を与えるようになりがちです。
それはカウンセリング的に言えば、「自分の育ってきた環境から、自分の子供を分からせる方法をそれしか知らないから自然にそうなる。だからちゃんと、自分が子供に分かってもらいたいことを、ちゃんと言語化出来るように訓練する必要がある」とか、「自分が過去に体罰を受けたことで、自己肯定感を無くしている。だから自分の気持ちを分かって欲しいという思いが強すぎて、自分とは別人格の子供と、ちゃんと向き合えなくなっている。だから自己肯定感を持てるように支援する必要がある。」そのように言うことが出来ます。
でもそれだけではないのです、親から体罰を受けて育った人が、子供に体罰を与えるようになるのは、自分が体罰の怖さを身に沁みて良く分かっているだけに、それがいかに、相手をやっつけるのに有効であるかを、知ってしまっているからです。
それと同じように、原罪という病に侵されて以降、人間は死の恐ろしさを感じ取っているが故に、自分の大切な人の命を奪った憎い相手には、憎い相手をやっつけるために、死刑を執行することが良いと思ったり、自分で自分を守るという意味も勿論ありますが、自分の憎い相手をやっつけるために、関係の死を用いたりするのです。罪深い私たちは、人を恐怖に陥れる死の力を、思う存分活用するのです。
人間が原罪という病に蝕まれて以来、死の恐怖に支配されている私たちは、憎い人には、自分が最も恐怖している死を与えることで、自分を守ったり、自分の怖さを教えようとしたりするのです。相手に死を与えるという復讐によって、自分の感情浄化を図り、平穏な日々を取り戻そうとするのです。
原罪という病は、永遠の命の源である神との関係を消失させて、死を萬栄させるのです。創世記の構図を見てもそれは明らかです。創世記3章は、人間に原罪が入ってきたことを教えています。そして、4章では、アベルとカインの話しを通して、原罪が人間関係の断絶を生み出したことを教えています。そして5章のアダムの系図の話しでは、人間関係の断絶が、死を萬栄させたことを教えています。
つまり、原罪が人間関係の断絶を生み出して、人間関係の断絶が死の萬栄を生み出したことを、創世記3章~5章は教えているのです。
原罪という病が、神との関係の断絶、隣人との関係の断絶に私たちを導いて、挙句の果てに、私たちの存在を永遠の滅びに向かわせるのです。
その病の特効薬は、自分の主(あるじ)を自分とせずに、自分の主(あるじ)を神にすることです。自分の主(あるじ)を神とするとは、私たちの原罪のために、主イエスが十字架に架かって死なれ、3日後に父なる神の御手によって、主イエスが復活なさったことを信じることです。
そのことを信じるなら、私たちの原罪という病は癒されて、自分を永遠に支ええて下さる神の恵みの下に置かれて、死で終わらせる世界観とは真逆の、永遠の世界観を持って生きることが出来るようになるのです。
そうなった時にこそ、死に対する恐怖から解放されるようになるのです。それは、神と人と共に永遠に生きるという、永遠の世界観により頼みながら、新しく生かされていくようになるからです。
神を信じて永遠の世界観に生きている人は、憎い人に、死刑や関係の断絶で報復することはしません。本当の報復は、憎い相手が、主イエスの原罪という罪の赦しと、主イエスの復活の命を信じて、永遠の世界観に生きるようになって、死刑や関係の断絶を憎むようになることです。
実は、32節~43節のペトロの働きによって起ったことは、そういうことなのです。
使徒言行録の著者ルカは、32節~35節の、ペトロのアイネアの病の癒しの御業を通して、原罪という病の癒しを見つめています。また、36節~43節の、ペトロがタビタを生き返らせた御業を通して、原罪という病が癒された人は、永遠の命が神から与えられて、永遠の世界観に生かされていくようになることを見つめているのです。
主イエスの十字架と、復活の御業を信じることは、十字架にかかって死なれ、復活なさった主イエスが、時が良くても悪くても、自分の日々の生活を支えて、導いていておられることを信じることです。いつも主イエスを、自分の支配者と認めて、歩むようになることです。
主イエスを自分の支配者と認めることは、自分が主イエスの救いの恵みの下にあると信じて、自分を自分の支配者とする病や、死の力の支配に逆らって生きることです。
感情のままに生きるのではなくて、主イエスに救われているという事実に生きることが大切なのです。でも私たちは、それがなかなか出来ません。だからこそ、主イエスが、十字架・復活・昇天の救いの御業を成し遂げてくださったのです。
だから私たちは、いつも出来ないから仕方がないと開き直るのではなくて、主イエスの救いに立ち返ることが大切なのです。私たちが順調な時だけではなくて、失意の中にある時も、理不尽なめにあっている時も、自分を自分の主(あるじ)としてしまっている病の中にあっても、自分の死を目前にしている時も、主イエスの救いの恵みが、私たちを捕えて、支配して、導いていることを信じることが出来るなら、それはまさに奇跡です。
それは、人間の力や、人間の思いでどうにか出来るものではありません。だからこそ、主イエスの十字架・復活・昇天の救いの御業に心を開いて、神が私たちに働いて下さらなければならないのです。神が私たちに働くなら、私たちには不可能に思えるような奇跡が、起こるようになるのです。
そして、その奇跡が私たちに起こったなら、私たちは心から、原罪の罪の赦しと、復活の命を、言葉や行動で、宣べ伝えることが出来るようになるのです。
だからこそ、今週一週間、皆さんと共に、いつも主イエスの十字架・復活・昇天の救いの恵みをいつも見上げて、そこに立ち返っていくことが出来ればと、心から願っています。
最後に一言お祈りさせて頂きます。