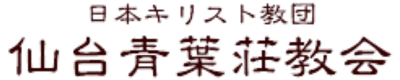マタイによる福音書20章1節ー16節
「後にいる者が先になる」
久保田順子神学生
皆さんこんにちは。初めましての方が多いかと思います。東京聖書学校3年の久保田順子と申します。本日はこのような貴重な機会を頂き、心から感謝いたします。
私は福島県伊達市の出身で、高校一年生の時に福島市にある福島新町教会で受洗の恵みに預かりました。進学、就職で福島の地を離れた時期もありましたが、結婚を機に福島に戻り、今も福島に暮らしております。夫と小学生の娘が二人おります。神様はそのような私に献身の道を開いてくださり、今は福島市の自宅から聖書学校の授業にインターネットを通じて参加しています。日曜には福島新町教会で学びと訓練をさせて頂いています。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
さて、本日はマタイによる福音書20章1節から16節が与えられております。イスキリストが話された譬え話の一つです。この譬え話は前の箇所からの続きになっています。19章16節からの話を受けてこの譬え話は語られていて、19章の最後(30)と20章16節には同じ意味の言葉が語られています。19章16節から、誰が天の国に入れるのかということが語られています。そして27節で、ペトロは「この通り、私達は何もかも捨ててあなたに従って参りました。では、私達は何をいただけるのでしょうか」とイエスに尋ねます。それに対してイエスはペトロの言葉に答えた後で「先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になる」と話されてこの譬え話が始まります。
イエスキリストは天の国がどのようなところかを語ろうとしています。この、天の国、というのは日本でイメージされる天国とは違います。聖書の伝える天の国は神の国とも表されますが、これは、神が支配する国のことです。神の権威に皆が従う国、神が主権者であられる国が天の国であり、神の国です。簡単に言えば、神中心の世界、皆が神中心に生きる世界です。教会は神の国の先駆けであるとも言われます。イエスキリストは当時のユダヤ人にとって身近な出来事を使って、天の国の譬えを話されました。
ブドウ園の主人と日雇い労働者の話が語られていますが、ブドウは当時の生活に欠かせない作物です。水資源が乏しい地域なのでワインは水代わりに用いられました。薬としても使われています。ブドウの収穫は雨季が始まる直前でした。雨が降る前に採ってしまわないといけないので、このように日雇い労働者を雇って収穫することもよくあることでした。
1.当時ユダヤ人の労働時間は夜明けから日没までだったそうです。大体朝6時から夜6時まで働いていました。ここに書かれている1デナリオンという金額は、その当時、家族が1日暮らすのに必要なお金に値します。このブドウ園の主人は、労働者を一日1デナリオンで雇うことにして、自分で労働者を雇うために夜明けに広場に出掛けていきます。広場は労働者が日雇いの仕事を探す場でもありました。仕事を求める人々は皆広場に集まっていました。この主人は夜明けにそこに出掛けて行って、労働者を雇います。さらに、9時、12時、3時にも広場に出かけて行って、仕事を探している人を雇います。広場には仕事を探している人たちが絶えなかったことがわかります。今もそうですが、能力のあるように見える人はどんどん雇われます。ですから残っていたのはそうではない人達でしょう。
この箇所を読みながら、大学時代に就職活動をした時のことを思い出しました。私が高望みをしていたこともあるのですが、希望する就職先はどこも門前払いでした。そこでは、まずどの大学を出たかで線を引かれました。理不尽さを感じましたが、雇う側とすればそれは当たり前でした。会社のために役に立つ人間かどうか、大学名がその人間をある程度保証すると考えられるからです。
多くの人は、雇ってもらえる人間になることを目指します。そこに競争が生まれます。競争に負けてしまう人はこの世界では容赦なく切り捨てられます。それがこの世界の現実です。このブドウ園の主人はしかし、そんなことにはお構いなく、雇える人を皆雇いました。そして、なんと、夕方5時ごろにも広場に出かけて行くのです。労働時間は夜6時までですから、1時間も働けないかもしれないのに、この主人は仕事がなく途方に暮れていたであろう人々を雇うのです。雇われた人々もそんなに働けないことはわかっていたでしょう。どのくらい賃金がもらえるかもわからない。それでもブドウ園に行って働くことを選びました。そして、驚くことが起こります。ブドウ園の主人は、夜明けから働いた人々と夕方5時から働いた人々に同じ1デナリオンを支払うのです。しかも最後に来た人々から先に支払ったのです。常識では考えられません。夕方5時から働いた人達は嬉しくて仕方がなかったでしょうが、夜明けから働いていた人々はどうでしょう。彼らは支払いを待つ間、自分たちはもっと貰えるだろうと期待しました。それが同じ1デナリオンだったのです。
彼らは言います。「最後に来たこの連中は、1時間しか働きませんでした。丸一日、暑い中を辛抱して働いた私たちと、この連中とを同じ扱いにするとは。」当然のセリフだと思います。今のこの暑さのせいで、余計に彼らの気持ちに同情したくなります。イエスキリストはこれが天の国だというのです。どういうことなのでしょう。
2.真面目に長時間働いても報われない世界だということでしょうか。しかし、立ち止まって考える時、この主人は最初から一日1デナリオンの約束をしており、13節にあるように、不当なことはしていません。ここで問われているのはなぜ彼らが不満に思うのか、ということではないでしょうか。生きるために働くのは当然のことです。ブドウ園の主人は、そのことがわかっています。ですから、全ての労働者に労働者家族が生活できるだけの報酬を支払っています。
ここで、不満を言った人々に目を向けると、彼らがなんのために働いているのか、なんのために利益を得ようとしているのかが見えてくるように思います。必要な生活の糧が与えられても、彼らはもっと報酬が欲しいと思いました。それは自分の欲を満たすため、ではないかと思うのです。雇ってくれた主人のために喜んで働いたわけではない。夕方5時から雇われた人々は雇ってもらえたことが嬉しかった。だからいくらもらえるかによらず、喜んで働いたのではないかと思うのです。ブドウ園の主人は神を指しています。私達は主人である神のために喜んで働くことができるでしょうか。
この箇所を丁寧に読むときに、そこには神の愛と憐れみ、そして人間の自己中心的な姿が表れていることがわかります。まず、主人は自分で雇う人間を探しにいきます。しかも朝早くから何度もです。使用人には任せない。神自らが私たちの中に入ってきてくださる、ということです。イエスキリストは神でありながら人間となって、私達のもとに来てくださいました。私達を救うために、神自らが私達のところに降りてきてくださいました。そして、ここではどんな人にも同じように神の恵みが与えられることが伝えられています。その恵みは人間の努力や成果によって決まるのではなく、神の意志によって決まります。人間の常識からすると、それは不公平のようにも感じますが、神は愛と憐れみによって全ての人に等しく恵みを与えられるのです。
夕方5時から雇われた人々は、他に雇ってくれる人がいない人達です。様々な事情から働きたくても働けなかった人々を、この主人は働かせ、報酬を与えられました。この主人は言います。「わたしはこの最後の者にも同じように支払ってやりたいのだ。」ここでは労働者がどれだけの成果をあげたかは問題になっていません。私達が持っている小さな力を、神の恵みに答えて喜んで差し出すことを、神は喜んでくださいます。私達がどれだけ成果を出したかによらず、どれだけたくさん働いたかによらず、神の憐れみによってその愛が注がれている。神は結果を出せない者も切り捨てません。良い結果を出すために努力することは悪いことではありませんが、自分はよくやっている、評価されるに値する人間だと思っていると、この夜明けから働いた3人々のように、神から与えられている恵みと、その背後にある深い愛に気がつくことができません。神の憐れみによって生かされていることに気がつけないのです。
イエスキリストは自分はよくやっていると思っているペトロにこの話を聞かせています。私はずっとこの箇所の意味がわかりませんでした。どうにも不公平に思えて、素直に受け止める事ができずにいましたが、少し前ふと、この最後に雇われた者は私なのだということに気付かされました。私はそれまで自分の傲慢さに気づいていませんでした。それが示されたのは、ちょうど夫と衝突を繰り返してしまうことに悩んでいた時で、神はそのことを通して、夫の前に私が傲慢であることを教えて下さいました。
全ての人が神の憐れみによって生かされている。私こそが夕方5時から雇われた者であり、自分が本当に無力であることがわかった時、自分に注がれている神の愛の大きさがよく分かりました。私の出した成果や結果ではなく、私の存在そのものを神は愛しておられることに気がつきました。そして、相手の弱さも受け入れなければいけないことがよく分かりました。神は夫とのことを通して、私だけでなく、皆同じように弱さを抱えていることも教えてくださいました。
「あとの者が先になる」とは、自分の無力さに気づき、神の憐れみによらなければ生きられないことを知る者が「先になる」、つまり、神の恵みをより豊かに受けるということです。それが天の国だとイエスキリストは教えています。神が支配する世界とは神の愛が満ちる世界です。神の国、天の国とはそのような神の愛のもとに人々が生きる世界なのだとイエスキリストは私達に教えているのです。自分の力に頼って、自分の思い通りに生きようとしていると、夜明けから働いた人たちのように、神の愛がわからなくなってしまいます。彼らは弱さを認めません。弱い者を受け入れる神の愛を認めません。それは律法学者の姿です。彼らはイエスキリストを認めませんでした。イエスキリストは律法学者たちから非難された時、旧約聖書のホセア書6章6節の言葉を引用しておられます。「私が喜ぶのは愛であっていけにえではなく、神を知ることであって焼き尽くす献げものではない。」そして、その言葉を受けてイエスキリストは言われます。「私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためである。」マタイ9:13
私は今日の箇所を黙想しながら、私の誰よりも汚れた手を、離すことなく握り続けてくださる神の手があることを教えられました。私たちの手がどんなに汚れてい4ても、神は決して離す事なく握っていてくださいます。その汚れを私達は自分では落とすことができない。それにも関わらず、神はその手を握っていてくださる、それが神の愛なのです。神こそが正義であられますが、罪人である私達に愛を示してくださるのです。それは無償の愛です。その愛が私達を生かします。私達は神が差し出していてくださる愛を素直に受け取るものでありたいと願います。そして、神の愛に応えて、喜んで、自分が持っているものを神と人のために差し出すものとなりたいと思わされます。神のために働くことを神は喜んでくださいます。
私達は一人一人に神からの賜物が与えられています。それは人と比較して何かがずば抜けて優れているということではありません。「結果」が出せるということでもありません。神がその賜物を喜んでおられるということです。些細なことに思えても、神の目から見たらそうではないのです。私達がその賜物を神のために用いることを神は望んでおられます。それは100点満点を取ることではありません。人に迷惑をかけてしまうこともあるかもしれません。それでも大丈夫。お互いに弱さを受け入れ合うことを神は求めておられます。神の愛のもとに、出来ることと出来な
いことをみんなで分かち合うことができたら、どれだけ豊かな世界になるでしょうか。今の世の中は律法学者のように、皆が自分の思う正義を振り翳して生きているように見えます。自分で自分の利益を守ることに必死になり、弱い者や間違えるものを許さない。認めない。助けない。結果として皆が生きづらさを感じているように見えます。私達は皆弱さを抱えています。許し合い、助け合うことなしには生きられないのです。イエスキリストの十字架と復活によって、私達は神に赦されています。赦された者として、愛されている者として、私達も赦し愛する者でありたいと思います。
私達に注がれている神の愛を信じて受け入れて生きることができますように。神の愛に応えて、神を愛し、自分と人を愛して生きることができますように。教会が、神の愛の満ちる天の国となるように、そして、一人一人がその天の国で生きる喜びを伝える者として生きることができますように。お祈りいたします。