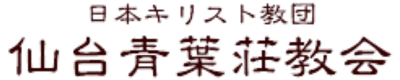マルコ14章1-9節
「できるかぎりのことを」
牧師 野々川藍
今は受難節ですから、今日はマルコによる福音書14章の御言葉に耳を傾けたいと思います。マルコによる福音書では、14章からが、受難の出来事となっています。14章から主イエスが捕えられ、十字架につけられて殺される御受難へと向かっていくのです。
まず1節を見ますと、「さて、過越祭と除酵祭の二日前になった」とあります。実はこれは主イエスの十字架の死の二日前ということになります。マルコの記述を見るなら、過越祭と除酵祭の最中に、主イエスは十字架にかけられたことが分かります。1節~2節には祭司長、律法学者たちが、イエスを捕えて殺そうと計略を練っていたけれども「民衆が騒ぎだすといけないから、祭りの間はやめておこう」と言っています。しかしこの時、祭司長や律法学者たちがそう言っていたのにも関わらず、結局は主イエスの十字架の死は祭りの最中となるというのは興味深いことです。それは言わば、祭司長たちの思惑を超えて、色々な事情が重なり、急展開したことを示しています。イスカリオテのユダが主イエスを引き渡すことを申し出たのもその一つでしょう。色々な成り行きの中で主イエスの十字架は、彼らの計画よりも早くなったのです。それは人間の色んな思いや事情を超えたところで働いておられる父なる神の御心があったということなのです。父なる神が主イエスの十字架の死がこの祭りの間になされることを御計画され、それが実現したのです。では父なる神は、何故そのようにしたのでしょうか。
それをひも解く鍵は、過越祭と除酵祭のそれぞれが持つ意味にあります。過越祭は、エジプトで奴隷とされていたイスラエルの民を主なる神が救い出して下さったことを記念する祭りです。
エジプト王ファラオはイスラエルの民をなかなか解放しようとしませんでした。そのため主なる神は、エジプト人の長男や、最初に生まれた雄の家畜を全て打ち殺すという恐るべき災いを下されたのです。しかしその時、イスラエルの民は主なる神の言葉に従って、子羊の血を戸口に塗ったのです。その血の印のある家だけは、主なる神の怒りが通り過ぎて、何の災いも起こらなかったのです。イスラエルの民は小羊の犠牲の血によって、災いから守られ、エジプトからの解放を与えられたのです。そのことを心に刻むために、イスラエルの民は「過越の小羊」と呼ばれる羊の血を戸口に塗って、その肉を食べるようになりました。それが「過越祭」です。イスラエルの民は「過越祭」の時に、食事の席で「この儀式にはどういう意味があるのですか」と子供たちが聴くそうです。それに対して親は「これが主の過越の犠牲である。主がエジプト人を撃たれたとき、エジプトにいたイスラエルの人々の家を過ぎ越し、我々の家を救われたのである」と答えるのです。そのようにして、主なる神の救いの恵みが、継承されていくのです。実は「過越祭」というのは、1日で終わるものなのです。
「過越祭」と「除酵祭」をまとめて、「過越祭」と言ったりもしますが、実際には「過越祭」が終わったすぐ後から7日間、除酵祭がなされます。何故、イスラエルの民は、除酵祭をするようになったのでしょうか。それはイスラエルの民が、主なる神の導きによって、出エジプトをした時に酵母を入れて発酵させる暇がないので、酵母を入れないパンつまり種無しのパンを持って、エジプトを脱出したことを心に刻むためです。
つまり過越祭も除酵祭も、イスラエルの民がエジプトでの奴隷状態から解放されるという、主なる神の救いの出来事を心に刻み込むための祭りなのです。そのような祭りの中で主イエスが十字架につけられて殺されるのです。これは本当に皮肉なことです。
でも、彼らは、今日の箇所で、主イエスを捕えて殺すのは、祭りの間はやめておこう、と言っています。「祭りの間は」という意味は、マタイなどの並行記事を見ると、祭りの期間はということではなく、祭りに集まる民衆の前では、という意味合いで描かれています。祭りには多くの民衆が各地からエルサレムに集まります。そんな民衆の前で、主イエスを死に至らしめるのはやめて、目立たない仕方で秘かに抹殺しようと考えていたということです。しかし結局は彼らの思惑とは違い、祭りのただ中で、多くの民衆の目の前で、主イエスは十字架につけられます。それは父なる神の御心によることです。父なる神の御心は、主イエスの十字架の死が、この祭りを通して、イスラエルの民がいつも心に刻んでいる、過越の小羊としての死であることを示したのです。
エジプトからの解放の時、過越の小羊が犠牲となって殺され、その血が鴨居に、戸口に塗られることによって、イスラエルの民は災いから守られます。そうしてエジプトからの脱出が出来たのです。つまりイスラエルの民は小羊が犠牲となって殺されて、その血が流されたことによって救われるのです。それと同じこと、いやそれよりももっと決定的なことが、主イエスの十字架の死において起こるのです。神の独り子イエスが、人となってこの世に来られ、私たちの罪を全てその身に背負い、十字架に架かって死んで下さったのです。そういった主イエスの犠牲の死によって、私たちは罪を赦され、神の民とし、新しく生きることが出来る今この時があるのです。主イエスが、過越祭の時に十字架に架けられて殺されたことは、主イエスこそが、私たちのための過越の小羊であることを示しているのです。主イエスを亡きものにしようと策略を練っていた祭司長、律法学者たちは、主イエスを十字架につけて、自分たちの思いを遂げたと思って、さぞ喜んだことだと思います。しかし実際は、父なる神がその背後で、彼らの悪しき思いをも用いて、過越の祭りの中でなされるように導き、まことの過越の小羊である、主イエスの死による救いを実現して下さったのです。
さて今日の3節以下で語られることは、マルコの記述によれば、主イエスが捕えられる前の日、つまりいわゆる受難週の水曜日の出来事です。エルサレムに来られて以来、主イエスは、日中は神殿の境内で教え、夜は近くのベタニアの村のある家に泊まっておられました。3節を見ると、ベタニアの村のある家とは「重い皮膚病の人シモン」の家であったことが分かります。一方、ヨハネによる福音書では、これが、マルタとマリア、そしてラザロの兄弟たちの家だったと記されています。
さて、主イエスが、シモンの家で食事の席に着いておられた時、一人の女性がやって来ました。そしてその女性は、主イエスの頭に、ナルドの香油を注ぎかけたのです。ナルドの香油は、インドや東アジア原産の香油で、大変高価なものです。5節には、「これを売れば三百デナリオン以上になったはずだ」とあります。一デナリオンが当時の普通の労働者の一日の賃金ですので、三百デナリオンは三百日分の賃金、つまりほぼ一年分の収入ということになります。小さな壷に入った香油が、それほど価値を持っているのです。しかもこの女性はここで、その壷からポタポタと数滴を主イエスの頭に注いだのではありません。「石膏の壷を壊して」とあります。つまり彼女は壷の中身を全部注いでしまったのです。残しておいて他のことにも使おうとは全く思わなかったのです。
彼女はなぜこんなことをしたのでしょうか。聖書には彼女の思いや言葉は全く記されていません。だからこそ私たちは色々なことが想像できます。でも彼女の思いはさておき、ナルドの香油は、当時、死体の葬りの時に、死臭を防ぐための香料として用いられていました。ですから彼女自身の思いは定かではありませんが、結果として、主イエスの埋葬の準備をしたと言えるのです。8節の主イエスの言葉を見ると、そういうことが伺えるのです。しかし彼女自身はきっとそんなこと意図してはいなかったでしょう。普通に考えると、まだ普通に生きておられる主イエスに、埋葬の準備として香油を注ぐというのは奇妙なことだからです。
はっきりしていることは、彼女は、主イエスを心から愛しており、主イエスのために何かをしたい、と純粋に思っていたということです。今自分が、主イエスのために出来ることは何だろうかと考えた末に、そうだ!と彼女は自分が一番大切にしているものを主イエスにお献げしたのです。ナルドの香油の壷は、彼女が母親から、母親はそのまた母親から、先祖代々大切に受け継がれてきた宝物だったのだと思います。家族の思いが詰まっている非常に価値のあるものだったのでしょう。お金の価値だけでいっても、300デナリオンです。ちなみに、マルコ6章の五千人の給食の箇所で五千人分のパンを買うのに200デナリオンかかると弟子達が言っていました。ナルドの香油はそれをはるかに超えているのです。それ程までの宝物を全て、彼女は主イエスに献げたのです。頭に油を注ぐという行為は、旧約の伝統から言ってその人を王、メシアとすることを意味します。彼女の行為は主イエスが油注がれるメシアであることを表わしたのです。高価な自分の宝物を全て捧げる程に、彼女は主イエスを愛し、自分の全てを献げる献身の思いを表明したこと。それが人の思いをはるかに超えて、神に、豊かに用いられたのです。
しかし、そこにいた人たちの何人かは、彼女の行為を見て憤慨しました。マタイ福音書の並行記事では、憤慨したのは弟子たちとなっています。ヨハネ福音書はさらにそれをイスカリオテのユダだと言っています。しかしマルコ福音書は「そこにいた人々の何人か」と言っています。なぜ漠然とした言い方にしたのでしょう。それはそうすることによって、マルコは、福音書を読む私たちが、自分自身をその場に置いて考えることを求めているのです。想像してみてください。私たちがこの女性の、主イエスへの真っすぐな愛と献身とを目の前で見たら、どんな反応するでしょうか。何と言うでしょうか。「なぜ、こんなに香油を無駄遣いしたのか。この香油は三百デナリオン以上に売って、貧しい人々に施すことができたのに」と私たちも言ってしまうかもしれません。なぜならそれはある面で非常に正しい主張、正論だからです。マルコ10章で主イエスは金持ちの男に持っているものを売り払い、貧しい人々に施しなさいと教えていました。
それなのに三百デナリオン、三百日分の賃金ものお金があれば、それを有効に使って色々なことが出来るはずです。それだけの貧しい人々を支えるという善いことをすることができます。それを主イエスの頭に全て注ぎかけてしまったら、三百デナリオンは一瞬にしてパーになります。そんな使い方は無駄遣い、というのは、私たちももしその場にいたらそんな風に考えてしまうであろう正論なのです。人々はそういう正論によって、彼女を厳しくとがめたのです。
しかし主イエスは、それに対して、「するままにさせておきなさい。なぜ、この人を困らせるのか。わたしに良いことをしてくれたのだ」と言われました。「そんなことを言ってこの人を困らせるのはやめなさい」と言われたのです。実際、そこにいた人々がしていたことは、女性のしたことにケチをつけて、困らせただけでしかないのです。貧しい人への施しという大義名分を掲げていますけれども、それは彼女を困らせるための口実に過ぎません。そのことを主イエスは、7節でこう指摘しておられます。「貧しい人々はいつもあなたがたと一緒にいるから、したいときに良いことをしてやれる。しかし、わたしはいつも一緒にいるわけではない」。貧しい人々を助けることは、あなたがその気になりさえすれば、いつでも出来る、そのために全財産を投げ出すことだって出来るから、そうすればよい、と主イエスは言っておられるのです。
しかし実際は彼らにはそんな気は全然ないのです。彼らは、貧しい人のことを本気で考えているのではなくて、ただ単に彼女のしたことを批判したいだけなのです。それは彼らが、彼女の行いに、自分たちにはない、主イエスに対する純粋な愛と献身を目の当たりにしたからです。「自分にはとても真似できない。」そう思わざるを得ない、素晴らしい愛の行為を見た時に、罪人である人間は、劣等感や妬みにかられて、何とかしてその行為にケチをつけたくなることがあります。こんな問題がある。あんな欠けがある。そう悪口を言いたくなるのです。そして、みんなに後ろ指を指されないような難癖をつけ、誰も反論できないような正論を言って、人を引きずり降ろすのです。そんなことを私たちもしばしばしてしまうのではないでしょうか。いかにも人が正しいと思うようなことを語りながら、あるいは誰かを配慮しているかのように語りながら、実は目の前の人を引き下げること、自分に有利になるように持って行こうとしてしまうなんてことが、私たちの日常生活にもあると思います。それはつい無意識のうちに、かもしれません。でもよくよく自分自身を吟味してみると確かにそういうことがあると思うのです。
さて主イエスにナルドの香油を注いだ女性の純粋な心からの献身も、違った角度から見たら、このような批判にさらされるのです。全てを見通しておられる主イエスはどうされたでしょうか。主はその批判に対して、「そんな批判は間違っている。この人の奉仕は正しい」と言われたのではありませんでした。そうではなくて「なぜこの人を困らせるのか」と言われたのです。ここに注目したいと思います。主イエスは「この人の奉仕こそ完璧だ。この人を批判することは許されない。奉仕する者は皆この人を見倣いなさい」と言われたのではないのです。「この人のしていることも、見方によっては色々な問題があるかもしれない、大いに欠けもあるかもしれない。でも、それをいちいち指摘して、ケチをつけてこの人を困らせなさんな。この人が心を込めて精一杯している奉仕を心に留めて、それを私と共に喜びなさい。」それが主イエスの御思いだと思います。
6節で主イエスは「わたしに良いことをしてくれたのだ」と言われました。彼女が「主イエスのために自分が何か出来ることはないだろうか、出来る限りのことをしてお仕えしたい。」そう思ってしたことを、主イエスは「わたしに良いことをしてくれた」と喜ばれたのです。そんな主イエスは「貧しい人々はいつもあなたがたと一緒にいるが、わたしはいつも一緒にいるわけではない」とも言われました。これは、主イエスがまもなく十字架につけられて死に至る、そして彼らのもとから引き離される時がまもなく来ることを意識して、語られている言葉です。そう語ることによって、主イエスは彼女の愛と献身を、ご自分の十字架の死と結びつけて、そのご自分のための奉仕として受け止められたのです。そのことが8節の「前もってわたしの体に香油を注ぎ、埋葬の準備をしてくれた」という御言葉に表されています。つまり「主イエスの埋葬の準備」は、主イエスが、彼女の心からの奉仕をそのように受け止めて下さった。ということなのです。主イエスとは、そのような御方なのです。主イエスは、私たちの主イエスに対する純粋な愛、献身、純奉仕を、十字架にかかったご自分への感謝として、受け止めて下さるのです。そこに主イエスの大きな恵みがあります。主イエスの十字架の死は、神の独り子が、私たち罪人を愛し、私たちの救いのために人となり、私たちが神に立ち帰ることが出来る道を供えるために、私たちに仕えて下さった驚くべき出来事です。主ご自身が、私たちの救いのために、私たちへの愛と、献身と、奉仕に生き抜いて下さったのです。私たちも、その主の愛や献身、奉仕に応えていこうではありませんか。主イエスを愛し、主にこの身を献げ、仕えていくのです。それが私たちの信仰生活なのです。
人から何と言われようと、どう思われようと、たとえ小さなことでも主イエスに対して純粋な愛を持ってなされたことなら、それがいかにつたない、欠けの多い不十分なものであったとしても、私たちに救いを与えて下さった御自分の救いのみ業への応答として、喜んで受けとめて下さるのです。
主イエスという御方は、できるかぎりのことをして、ご自分に仕えしようとしている人を、困らせたり、批判したり、ケチつけたりするなんてことを、望んではおられない御方です。ひょっとしたら、人の批判というのは結構、的を得ているかもしれません。しかし、主イエスは、「一生懸命私に仕えようとしているこの人を困らせるな。」そう言われるのです。また、私たちが、自分のしていることを誇ったり、人と自分を比べて優越感を抱いたり劣等感に陥ったりすることもお望みではないのです。例えば、この女性が、「私を批判したあの人たちは何よ!貧しい人たちのためとか言いながら、自分は何にもしていないじゃない!私は三百デナリオンにもなる香油をイエス様の頭に注いだのよ!」などと言い始めたらどうでしょう。また「フン、あの人のしたことは、二百デナリオンぐらいね。私は三百デナリオンよ!」などと言ったら、台無しです。それでは彼女も「無駄遣い」と正論をふりかざして、批判している人と同じになってしまいます。十字架の死に至るまで、私たちに仕える道を歩み通された主イエスは、私たちがその恵みに感謝して、それぞれに心から主イエスを愛し、献身し、神に人に仕えることを喜ばれるのです。
最後の9節で主イエスは「はっきり言っておく。世界中どこでも、福音が宣べ伝えられる所では、この人のしたことも記念として語り伝えられるだろう」と言われました。この御言葉は、この女性のした事が、いかに素晴らしいかを語るのではなくて、彼女がその時自分に出来る精一杯のことをして主イエスに良いことをしようとした思いを、主は、ご自分の十字架の死による救いと結びつけて、彼女自身が思いもよらなかった大きな恵みを与えて下さったことを表わしているのです。
どんなに不十分であっても、赦され、かえって私たちもナルドの香油の女性のように、主イエスの救いの御業である福音に結び付いた者であることを高らかに宣言されるのです。
そのことを覚えて共に今週も歩んで参りたいと思います。