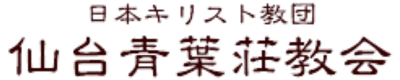詩編23編
「主の家に帰る」
牧師 野々川 藍
今朝、共に聞きます、この詩篇23篇というのは、昔から葬儀の時によく朗読されて来ました。
なぜそのような伝統となったのかははっきりしませんが、古代のキリスト者たちにとって天の御国というと牧歌的風景をイメージしたと言われています。まさに今日読まれた詩編23編にある「青草の原」なのです。
そして恐らく、葬儀を行う時に、誰もが思い起こすのは、主は私たちを導いて下さる方であるという信仰です。死を迎えた者はまさに、ただただ神に導いて頂くのみだからです。私たちは皆、いつかは地上の生涯を終える時を迎えます。だからこそ、私たちは主がどのように私たちを導いてくださるのかを共に教えられたいと思います。 終わりの時を考えることはある面でつらい事かもしれませんが、しかしそのことによって、私たちは今この時、この瞬間瞬間をどう生きるべきかを教えられるのです。
さて、聖書の中には、神が私たちの羊飼いであるという描写が何度も出てきます。その比喩は誰にでも、私たちと神との関係をもっともイメージしやすい形で伝えられます。良く言われる話ですが、羊というのはいつも自分の目の前のことしか関心がありません。目の前に美味しい草があるかどうかだけが羊の関心事です。自分の人生を何年も先まで見通している羊というのはいないのです。そういう羊に、私たち人間が譬えられているというのは、そこに私たちの性質が言い表されているからだと思います。私たちは目の前に起こっていることに、常に右往左往されながら生きていることが多いのではないでしょうか。
また羊というのは、自分で自分の身を守る術を持っていません。外敵がそろりそろりと近づいていきますと、羊は距離がある時はゆっくり移動して離れていく余裕がありますが、気がつくのがもう数メートル前になりますと、固まって身動きできなくなってしまうのです。ただ、じっと動けなくて、ただこちらを見ることしかできなくなるのです。外敵に対して何も身を守る術を持たないのです。けれども、羊は、自分たちは羊飼いたちが整えた囲いの中にいれば、絶対に大丈夫だということを知っています。だからもし、外敵が近寄って来たとしても、ある地点からは、それ以上、自分たちに近寄れないことを知っているのです。羊というのは、そのようにいつも完全に羊飼いに守られているのです。
この詩編の詩人、ダビデは、自らを羊に譬えています。古くからこの詩編は、ダビデが少年時代に羊飼いをしていた経験を晩年に思い返しながら、そのような歌をうたったと考えられてきました。羊と、羊飼いの関係がこの詩篇の中によく表わされているからです。
自らを羊であると譬えるというのは、今日ではそれほど抵抗のないことかもしれません。羊は白いふわふわした毛皮をまとって、素朴でかわいらしい生き物ですから、そのようなものに自分を重ね合わせるということがあっても悪くない気がします。しかし、聖書の時代は、羊といえば、貧しい者が世話をしなければならない生き物という貧しさを象徴的に表す生き物でした。ですから、そのような卑しいものに自分を重ねるということは、おそらく、今日の私たちの感覚とはちょっと異なるイメージがあると思うのです。
例えば、私たちが、もし誰かに、「あなたは羊のような人ですね。(自分で自分を守れず、目先の事しか考えていないのですから。)」などと言われるならば、完全な悪口だと頭に来ると思うのです。自分はそんなに愚かで弱い存在ではないと思っている人には、この詩篇はそれほど魅力的な歌として響かないのかもしれません。
自分が元気で、人生設計がしっかりあって、結構頑張ってるし、いい具合に来ているなと、自分に自信を持てる時は良いのです。が、逆に、自分の弱さを思い知らされ、自分が誰かからの助けが必要であることを痛感し、確かな方に自分を導いてほしいと願う人にとっては、この詩篇は、その心に非常によく響くものがあります。
私を導いて下さる方が確かな方であるがゆえに、死という圧倒的に人の無力さを突きつけられる時でさえも、私の神は、羊飼いのような方であるから、私には乏しいことがないのだということをよく教えてくれるからです。
この詩篇には、か弱い羊がこの歌の中で、どれほど力強い羊飼いに守られ、養われ、導かれているかが見事に歌われています。言葉で説明などいらないほど、ここで語られている情景は明確です。羊は羊飼いをただ信頼してつき従っていきます。ここには緑の牧場があり、いこいの水のほとりであって、この羊飼いは、疲れ、不安を抱え、悲しんでいる者に元気を与え、文字通りよみがえらせてくださるのです。ですから、「死の陰の谷を歩くことがあっても」、いや、死のただなかにあったとしても、この羊飼いである神、主は私たちをよみがえらせてくださるのです。神の国にわたしたちを置いてくださるのです。ですから、私たちは何があったとしても、すぐ近くまで敵が迫ってきたとしても、恐れることなく、羊飼いと共にいて平安を見出すことができるのです。神はそのように、ここで羊に譬えられている私たち人間が、平安を持って生きることができるようにと、導いてくださるお方なのです。
この詩篇は、私たち人間を、ちょっと鈍いところがあって、弱い存在である羊に譬えられていると言いました。それに抵抗を覚える方、ピンと来ない方もあるかもしれません。けれども、私たち人間が弱いものであることを認めざるを得ない時、羊飼いである神を本当に力強い導き、信頼して我が身を任せることの出来る方、そのような超越的な存在が私たち人間には必要なのだと本当の意味で気付かされるのだと思います。
むしろ、神が羊飼いに譬えられているというのは、この世界のすべてを支配しておられる偉大な方がどこまでもへりくだった方として描かれていることも、今日私たちは心に留めたいと思うのです。そこには、神が私たちのすぐ近くにきてくださって、私たちを直接に導いて下さるという、非常に具体的なイメージで、神という御方が表現されているのです。貧しい羊飼いとして、御自分を表されることを神は認めておられるどころか、聖書の中には新約聖書に至るまで、何度もこのイメージが用いられています。そこには、それほどまでに神の栄光を捨てて、全てを捨ててこの地に下って来て、私たちの近くにいてくださるということを表しているのです。どこまでも追いかけてくださる神の愛の姿が、神の本質であることをよく表わされているのです。
この世界では、弱肉強食の世界です。今日では、ますますこれを痛感させられるような気がします。ちょっと隙を見せれば、攻め入れられる、騙されるという事態を目の当たりにします。
けれども、今日の御言葉は羊飼いである主は、私たち人間が弱い者であることをよく御存じで、私たちを守り、養い、導こうとしてくださると宣言しています。敵が追いかけてくれば、この羊飼いはむちで敵を追い払ってくださるのです。私たちがどこに進んでいいか分からない時は、杖を持って先頭きって歩んでくださる。そんな御方が私たちといつも共にいてくださる、それが私たちのこの上ない慰めだと歌います。
目の前に敵が待ち構えていても、安心して食事ができるようにしてくださり、私たちを確実に守ってくださることをあかしするかのように、また王や預言者のように選ばれた者の証として頭に香油までも注いてくださる。だから、この詩人は言うのです。「わたしの杯はあふれています」と。
この詩は最後に、このようにまとめられています。「まことにいのちの日の限り、いつくしみと、めぐみとが、私を追ってくるでしょう。私は、いつまでも、主の家に住まいましょう」と。
私が生きている間、神の愛の眼差しと祝福が、私を追いかけて来ると言う事ができる人生とは、どれほど幸いな人生でしょう。神の祝福とは、必ずしも私たちの思い通りになることではなく、神の御思い、御計画は深く高く広く長いので神によってもたらされる最善は私たちの願いとは異なることがあります。
しかし、私たちは地上で生きる時だけではなく、いつまでも、私は主の家に住むことができるのです。永遠に神の国に住まい、神と共にある喜びに満ち溢れることができるのです。
羊飼いである神、主だけが、私たちにこれを与えることが出来ます。ですから、信仰を持ってこの世で生きるということは、地上で生きている時だけでなく、死を迎えた後もなお、永遠に神の国で幸いに生きることができるのです。
信仰を持って生き、そして死ぬということは、これどもまでに幸いなことなのです。私たちもこの地上でも既にその前味を味わっていますが、主の御許に召された方々は今、主の家に住んでいるのです。神の家で、神と共に、永遠の喜びの中におかれているのです。そして教会はヤコブが「ここは天の門だ」と言ったように、教会は特に天上と地上とをつなぐ所なのです。
「 主は、羊飼い/わたしには何も欠けることがない。」
主が羊飼いであるなら、わたしたちにはもはや何も欠けるものはないのです。この主は、あなたの羊飼いでもあるのです。最後に一言お祈りいたします。