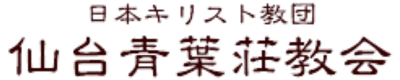創世記12:1-4
「75歳からの出発」
更生教会牧師 山口 紀子牧師
初めまして、東京都中野区にあります更生教会牧師の山口と申します。こうしてこの朝、青葉荘教会の皆さんと共に礼拝を献げることがゆるされ、心より感謝いたします。私は群馬県の出身ですが、米沢の短大を出ましたので、東北には一方的に親近感をもっています。また青葉荘教会は、敬愛する島先生、静江先生が更生教会の3代目の牧師夫妻でしたし、聖子先生は聖書学校の先輩、野々川康弘先生藍先生は後輩です。聖書学校の理事長、ホ群委員も送り出してくださっています。その皆さんと主日礼拝を共にささげることこそ初めてですが、実は教会へは2011年に1度お伺いしたことがあります。東日本大震災で甚大な被害を受けた荒浜地区へボランティアで入ったときでした。更生教会の所属する西東京教区は、教区が支援しエマオの被災者支援センターへ継続してボランティアを派遣していました。震災以降、長きに亘って青葉荘教会の皆さんが全国から集まるボランティアの食事のサポートや、宿泊場所を提供してくださいました。その愛のわざを、受け入れていただいた私たちは覚えています。
その皆さんと共に献げる礼拝です。どこから御言葉を取り次がせていただくか、野々川先生に教会の様子を伺いましたら、丁度明日は敬老の日。昨年私は教団出版局から出された「老いと信仰」という本に関わらせていただきましたので、「老いと信仰」をテーマにして欲しいと言われました。祈りつつ、導かれたのが、この朝の創世記12章です。75歳から出発したアブラハムへの主の約束の言葉に共に耳を傾けたいと思います。
ところで、更生教会では敬老の対象者は75才以上の方です。青葉荘教会はおいくつからでしょうか。一方で世の中には「高齢者」という呼び方があります。こちらは70歳以上の方々をそうお呼びすることが多いようです。これまで私はこの言葉を何の疑問も持たずに使ってきましたが、この言葉の背後には明確な価値観が潜んでいると、「老いと信仰」の中で岡本知之先生が指摘しておられます。この言葉は約130年前に制定されたビスマルク社会保険法が、老齢年金の受給資格を七十歳以上としたことに由来するのだそうですが、この年代を区切ることに何か根拠があるわけではありません。しかし区切ることで、そこに意味が生じるというのです。先生の文章にはこうあります。
『すなわち「高齢期」とは、「人を養う立場から養ってもらう立場に変わる時」という考え方です。これはつまり、生産性の有無によって人を二分しようという発想です。』なるほどと思いました。
しかし、生産性があるかないかで人を二分するとしたら、それは大きな間違いです。何が間違いかといえば、そもそも、人間の生産性や創造性を物質的な事柄に限定して考えている点が間違いなのです。それは、まさに聖書が教えてくれることです。聖書は、人間の生産性の本質は霊性・魂・体の健全さにこそあると教えます。
皆さん、人は一体なにによって構成されているのか考えたことはありますか?実感としてまず、体と心があります。心は魂と言い換えてもいいと思います。聖書はさらに、人には霊が与えられていることを教えてくれます。1テサロニケ5・23「あなたがたの霊も魂も体も何ひとつ欠けたところのないものとして守り」とあるとおりです。人は霊・魂・体でできている。
創世記によると、人は神の息、すなわち霊を吹き入れられて生きるものとなりました。だから人は、どんな時代、どんな文化、どんな人種でも、普段は神なんていないという人でも、ピンチのときには本能的に神を求めます。思わず「神さま助けて!」と祈ってしまう。それが、人が神に造られた証拠だ、という神学者もいます。祈り、礼拝するのは人間だけです。岡本先生のいう「人間の生産性の本質は、霊性・魂・体の健全さにこそある」とはそういうことです。そして、この生産性を最大限に発揮しうるのは、実は人生の成熟期を迎えた人々なのだ、というのです。
もう一度言います。この生産性を最大限に発揮しうるのは、実は人生の成熟期を迎えた人々なのです。
それは、私たちの霊性は人生が順風満帆、向かうところ敵なしといった時にこそ、もっとも低くなるからです。『人生の絶頂で、すべてが自分の思いどおりになり、肩で風を切って歩いているような時に、人間がどれほど傲慢になり、神なしに生きていけると思うか、、これは私たち誰にでも思い当たるところがありますよね?この時にこそ、私たちは本当の意味での「牧会」を必要としている。そしてそこに、人生の霊的成熟期を迎えた人々の果たす、大切な役割がある』というのです。
どういうことでしょうか。先ほど「生産性があるかないかで人を二分するとしたら、それは大きな間違い」だとお話ししました。でも、本音では、みなさんどうですか?生産性があるとは、言い換えれば、いい点をとれることであり、資格があることであり、選ばれること、バリバリ仕事ができること、沢山「持っている」こと。それがみんなからすごいと褒められる。評価される。その基準で自分自身を、人を、評価、ジャッジしていませんか?子どものころからそうして育ってきましたから、その価値観がしみついてしまっているのです。
岡本先生の言葉です。「私たちは自分の能力や地位、自分が所有する知識や名誉の一つ一つに依存して生きています。そこに自分の誇りがあり、自負があります。だからこそ私たちは、人生の最後に、その一つ一つを神さまにお返しして、ただ神にのみ依り頼む者として、神の御前に霊的に成熟するプロセスが備えられているのです。まさに「主は与え、主は奪う。主の御名はほめたたえられよ」です。」
高齢期とは、神の御前に霊的に成熟する期間の始まりなのです。
ではどのように成熟のプロセスを踏むのでしょうか。「成熟」という言葉の響きは麗しいですが、そのためには喪失経験を積み重ねるのです。最初に白髪を見つけたときのショックから始まり、老眼、シミ、シワ、もの忘れ。この間、教会の早天祈祷会で、デイリーブレッドというデボーションサイトを使っているのですが、それをいつものように朗読していたら、潮の満ち引きの「干潮」、「干潮」という言葉が出て来て、私、読めなかったのです。知っている漢字なんです。それなのに、その時は読み方が出てこなかったのです。そんなことは初めてだったので、本当にショックでした。そんなことは序の口で、これから年を重ねるごとに、できていたことができなくなる、そんな喪失を重ねてゆくのだと思います。それを受け入れる忍耐が必要とされるのです。
うちの教会の先輩方がよく言われます。年をとるのは容易ではない。昔、親に、あなたもこの年になってみればわかると言われていたけれど、本当にそうだった。なってみないとわからない痛み、辛さ、切なさ、だるさ、衰えがあります。
ヤコブ書1:4にこうあります。「あくまでも忍耐しなさい。そうすれば、完全で申し分なく、何ひとつ欠けたところのない人になります。」後半を新改訳では「何一つ欠けたところのない、成熟した、完全な者となります。」「成熟した」という訳になっています。やっぱり成熟には忍耐が必要なのです。この御言葉を共に聞いたときに、うちの88才の先輩がこうおっしゃいました。「年を取ったら忍耐してやらないと。忍耐してやり続けて、やっと今までのことができる。今までのペースになる」。高齢期は、神の御前に霊的に成熟する期間、それには忍耐が必要なのです。
それは大変なことです、しかしそれはイコール不幸なのでしょうか?私の恩師のひとりが静岡県で榛原教会を牧会しておられます。榛原教会は今年100周年を迎えました。その記念誌に先生がこんな風に書いておられます。
「そこでわたしたち榛原教会です。百年生きての榛原教会を人にたとえるなら、高齢となり、衰えたのです。それが今あるわたしたちの教会の現実です。でも神は、その有様でわたしたちの教会を養っておられる。
この世にあって、強さは憧れです。富むこと、豊かになることが喜ばれます。逆に弱くなること、貧しくなることは嫌がられます。実際、人は自らの衰えを痛感させられると、人生に望みを持てなくなってしまいます。
教会の思うところもこの世と同じなのでしょうか。教会が大きくなり、強くされ、その持ち物において豊かにされてゆく。それを喜び、感謝するのが当然とされています。でも、問題はその先にあります。その教会もやがて衰え、弱くなり、貸しくなってゆくときもある。そうなると、盛んだったころに溢れていた喜びは、感謝は、教会からなくなってしまうのでしょうか。そうだとすれば、教会も衰えを恐れねばなりません。貧しくなることを恐れねばなりません。榛原教会、勢いを回復できないうちは喜びなどないはずです。
でも、そうではありませんよね。教会はこの世の誰よりも弱く、誰よりも貧しくなられた十字架の主キリストによって救われた者の集いです。そして教会は、主から次の御言葉をいただいています。自身の弱さに悩むパウロを希望に溢れさせた言葉です。
「わたしの恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ。」』これが聖書の価値観です。
この朝は創世記12章、信仰の父、アブラハムの出発の記事をお読みいただきました。彼の出発は75才だったのです。この時代の75才と現代の75才は同じではないでしょう、ただ、10代20代の青年期ではない。30代40代、経験を積みさらに新しいことへ挑戦する働き盛りの年代でもない。50代60代、収穫の壮年期でもない。75才、やっぱり高齢者です。そのアブラハムに主が言われます。
ことの発端は、神なのです。神である主が、アブラムに言われた。このころの名前はまだアブラムでした。「あなたは生まれ故郷 父の家を離れてわたしが示す地に行きなさい」。主なる神が、アブラムを呼ばれた。召命です。この召命の特徴は「分離」。離れることにあります。「行きなさい」という言葉は強い言葉が使われています。
ヘブル語の語順どおり、直訳すると、「行きなさい・あなた自身に向かって・あなたの国から・あなたの故郷から・あなたの父の家から・私があなたに見せる地に向かって」。
「あなた自身に向かって出て行く」。不思議な表現です。神を信じる生涯は、新しい自分へと出発する生涯です。それにはあなたの国、故郷、父の家を出ていきなさいと主はいわれます。もちろんこれは、みんな仕事をやめ、家族を離れて出家しなさいといっているのではありません。古い価値観から出て行きなさい、ということです。聖書の価値観へと鞍替えすることです。これまでは生産性があるかないかで自分を、人を評価していた。この世がそうなのですから。でも聖書の価値観を私は選ぶ、と決めることです。
私たちは、教会は、キリストのしもべになろうとするならこの世の価値観からの分離を自覚的に意識しなくてはなりません「わたしの恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ。」』Ⅱコリント12:9 この価値観で、聖書の価値観で生きていくことを自覚的に選び取り続けます。
神に向かって開けている。それが霊性であり、霊性の深まりです。「しかし、主の方に向き直れば、覆いは取り去られます。…わたしたちは皆、顔の覆いを除かれて、鏡のように主の栄光を映し出しながら、栄光から栄光へと、主と同じ姿に造りかえられていきます。これは主の霊の働きによることです」。Ⅱコリ3:16-
聖霊がそれを成してくださるのです。それを求め続けます。これがきよめであり、聖化です。
最初にお話しした岡本先生、教会でこんなことがあったそうです。ある日の集会で、一人の教友が次のようなことを語られました。「自分は若いころに洗札を受けてから信仰一筋の生を歩んできた。教会に奉仕し、若い人たちを訓練し、いつも精いっぱい働いてきた。でも最近、毎日一つずつできないことが増えてきて、本当に情けなく思う。もう神さまのお役に立てないのかと思うと本当に悲しい」と。
私の教会でも時々そうおっしゃる方がおられます。青葉荘の皆さんはいかがでしょうか。
その呻きとも取れる問いに岡本先生はこう答えられた。いいえ、そうではない。あなたはこれまで自分が依り頼んできたものを、一つ一つ神さまにお返ししているのです。そして私たちは最後に、ただ神にのみ依り頼む者とされるのです。たとえ体が動かなくなる時が来ても、そこであなたが献げてくださる祈りが、この群れを支えるのですと。人生の霊的成熟期を迎えた人々の果たす、大切な役割とはこのことです。
この方は、私が申し上げたことを瞬時に理解してくださいました。「ああ、なるほど、本当にそうでした。よくわかりました」と言ってくださったのです。」
この方は、生産性で自分を評価することをやめる、そのことを選んだのです。どちらを選ぶか、それを決めるのはあなたです。決めたからといって、すぐにそうなれるわけではありません。成熟に至るには忍耐が必要です。毎週毎週、私たちはこの礼拝で、日々のデボーションで、我に返るのです。ちがうちがう、何ができるできないではない。私はイエスさまの血潮で買い取っていただいた、神の子とされたのだ。その神が「わたしの恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ。」とおっしゃる。
「行きなさい」と主はあなたに言われます。「行きなさい・あなた自身に向かって・あなたの国から・あなたの故郷から・あなたの父の家から・私があなたに見せる地に向かって」。
神を信じる生涯は、新しい自分へと出発する生涯です。新しい自分。「わたしたちは皆、顔の覆いを除かれて、鏡のように主の栄光を映し出しながら、栄光から栄光へと、主と同じ姿に造りかえられていきます。」この自分へと出発する。その姿を後に続く若い人たちは見ています。自分の10年先、20年先、50年先はこうなりたい、そう若い人たちが思えるように、その姿を見せてください。弱さの中でこそ発揮される強さを見せてください。また、若い方々は、そうして人は年を重ねてゆくことを自覚し、先輩方の手助けをしてください。そうして青葉荘教会は形成されるのです。