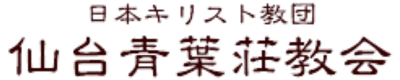フィリピの信徒への手紙3章4~14節
「なすべきことはただ一つ」
仙台宮城野教会牧師 齋藤朗子牧師
私は学校の体育の授業が大嫌いでした。走る、飛ぶ、泳ぐ、投げるといったことに点数が付けられ通信簿がつけられるのが嫌でした。ほかの人と順位や記録を競うことも嫌いでした。参加することに意義があると言うのなら、順位や記録などどうでもいいではないかと思っていました。運動会で、1等賞の商品をもらうことにも興味がありませんでした。ノートや鉛筆をもらって喜ぶクラスメイトを眺めて、「持っている人はさらに与えられて豊かになり、持っていない人は持っているものまで取り上げられる」というキリストの言葉はこういう世の中の現実を指すのだと、冷めた気持ちでいました。人には、得意、不得意がある。こんな当たり前のことが、当たり前のこととして受け入れられていない現実に、いつもいらだっていました。
なので、パウロが「神の賞」を得るために、目標を目指してひたすら「走る」ようにと言う言葉が、私は大嫌いでした。パウロは時々、信仰者の歩みを競争に例えますよね。「競技場で走る人たちは、皆走っても、賞を受けるのは一人だけです。あなたがたも賞を受けられるように走りなさい」(1コリ9:24)とか。この世の理、真理、自然界の秩序、そういう、人が生み出したり操作したりできないものを生み出し、扱い、保とうとする「神」と呼ばれる存在を信じて生きるということは、あくまで自分自身の成長や生き方の充実のためであって、誰かと優劣を競うものではない、それなのに、それを「競争」や「賞」と言う言葉で表現するパウロという男は、なんと高慢な人間だろう。そう思っていました。そして、パウロが書いたとされている書物を読むと、パウロは生粋のヘブライ人でイスラエル民族でベニヤミン族であるのが自慢で、えらい学者に師事して律法を学んだ厳格なファリサイ派だったこと、しかも、自分の敵を容赦なく攻撃するほど熱心な信仰者だったことを、恥ずかしげもなく自慢している。本当にパウロという人が私は嫌いでした。
今でも私は、どうしてパウロが「競争」「走る」「賞」という言葉を使って信仰の歩みを表現しようとしたのか、理解していません。相変わらず、こういう言葉を目にすると、嫌な気持ちになります。けれども、パウロがこういう言葉を使ってなにを言わんとしているのかは、クリスチャンとして暮らす年月を通して少しずつわかってきたような気がしますので、それをお話してみたいと思うのですが、パウロは決して、自分が生まれながらに持っているもの(生粋のヘブライ人、神に選ばれたイスラエル民族、小さいながらも『有名人』を幾人も排出したベニヤミン族)や、自分で努力して得たもの(律法の知識や熱心さ)を自慢したいのでもありません。そうではなくて、生まれや特権や能力といった「肉の頼み」(4節)、つまり人間的な要素が、神がくださる「賞」つまり人間の救いを決定するのではないということを、今日読んだ箇所で語っています。そしてパウロは今日の箇所を、神による救いは、生まれながらの血筋、国籍、特権と、努力で勝ち取った資格や能力の両方か、あるいは後者があってこそだと主張していた「らしい」人々に向かって書いたふしがあります。
神が与えてくださる救いは、「イエス・キリストを信じる」ことで与えられる。パウロは、ある日ある時キリストに「捕らえられ」て以来、そう信じるようになった人でした。「私には、律法による自分の義ではなく、キリストの真実による義、その真実に基づいて神から与えられる義があります」(9節)とある通りです。しかしこのことに疑義を呈する人々がいたようです。そしてこの人々は、キリストを信じる者は、ユダヤ律法もきちんと守らなければ救われない、といった趣旨の信仰を、教会の仲間たちに教えていたようです。これは想像ですが、「ユダヤ律法を守る派」のクリスチャンはたぶん、食事の前には必ず手を洗っただろうし、どんなに空腹でも道端の麦の穂を摘まなかっただろうし、安息日に家族が病気になっても医者を呼びにいかなかっただろうし、羊が穴に落ちても安息日が明けるまで助けるのを我慢しただろうし、同じクリスチャン以外とは親しく付き合わなかったかもしれませんし、誰かに振舞われても絶対に食べない物があったかもしれません。
いろいろ気を付けて、我慢をして、律法を守る努力を続けて、最終的に救われる「かもしれない」。これはまさに「賞」を目指して走る競争のような信仰のあり方です。目標に到達できない場合は「賞」つまり救いを得られない、苦しい信仰のレースです。意外と日本人にはこういう考えのほうが馴染みやすいかもしれませんが。しかし、パウロは、かつては自分もそういう競争を走っていたけれども、そして、そういう競争を走っていることを自慢にも思っていたけれども、そういう競争を走り続けることが自分のアイデンティティだと思っていたけれども、今はそんな風には思っていません。むしろ、そんな風に頑張って走っていたことも、また、自分が要するにアブラハムの子孫だということも、なにもかもが「救い」には無用どころか、かえって邪魔だ、持ってる方が損だとわかってしまった。かつて自慢に思っていたこと、誇りに思っていたことは全部「損失」(7節)だ、「屑」「塵あくた」(8節)だと。「塵あくた」という言葉は、原語では「汚物・糞尿」という意味です。そのくらい無価値だとパウロは考えました。
なぜパウロはこんなにもガラリと考えや価値観、信仰スタイルが変わったのでしょうか。それは、イエス・キリストと出会い、キリスト・イエスを信じて神に義とされるという「秘儀」(コロサイ1:26)を知らされ、「私の主」つまり、わたしという一人の人間が個人的に、親密に、イエス・キリストというお方を知るごとに、ますますイエス・キリストに身も心も捕らえられていく経験をするようになったから。パウロはそう語ります。
パウロは、まずキリストによって神と和解し、罪を赦されて救われました。律法をしっかり守ったその先のゴールが「救い」ではなくて、まず先に、ただ神の憐みゆえにキリストによって救われたのです。このこと自体が、ファリサイ派・パウロにとっては青天の霹靂、この上ないカルチャー・ショックでした。このショックが納得に代わり、しっかりと腑に落ちて喜びとなるまでには、ある程度の時間は必要だっただろうと思います。その間、今までの自分はなんだったんだ、いや、今まで自分が大事だと考えていたことはそんなに無価値なものなのかと、葛藤もしただろうと思いますが、聖霊がパウロに、イエスの生き方、言葉、行動、その死のわけにさえも強いあこがれを持つよう導いたのでしょう。パウロは「キリストとその復活の力を知り、その苦しみにあずかって、その死の姿にあやかりながら、何とかして死者の中からの復活に達したい」(10節)と願う人に変えられました。そして、「後ろのもの」すなわち過去、自分が持っていると信じて頼りにしていたものを忘れて、イエス・キリストのように生き、イエス・キリストのように死に、キリストの再臨のときには、キリストのように栄光の復活の体に変えられること。ひたすらにそれだけを求めて走り続けました。
パウロ自身が「私は、すでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけではない」と言うように、パウロはキリストに捕らえ、キリストの者とされて、あるいは、キリストをいただいて、完全な者、キリストのような者になった、とは決して言いません。ときどきパウロは「私を模範としなさい」的なことを言いますけれども(たとえば3:17など)、そういうとき、パウロは自分がキリストにでもなったつもりで言っているのではありません。ただ、自分を形作っていると思っているつまらない殻を捨てて、キリストのために、キリストのあり方に近づくことだけに全身全霊を注いでいく、この歩みを私と一緒に歩みましょう、と、パウロはフィリピの教会の人々を、そして私たちを誘っているのです。これこそが、なすべきただ一つのこと(13節)だと。
結論を先に言えば、キリスト者がなすべきただ一つのことは、キリストを模範として生きること(2章)だ、ということです。これ以上、つまり、自分がキリストになることを要求しているのではありません。そういうことは、イエスご自身も求めてはいません。同様に、あれこれと言い訳を言って、「キリストに倣って生きること」をしないことも誤りです。イエス・キリストの弟子は、イエス・キリストの弟子である以上、師であるイエス・キリストに倣うことが本分です。たとえ、キリストの生き方を完璧に自分の生き方にできなくても、それでも、弟子として、キリストの日の復活にあずかるその日まで、キリストの弟子であり続けること。師であるイエス様の言葉と業から、イエス様の御心、イエス様の価値観、イエス様の理念や信念、神への信頼のあり方を学び、それを自分の生き方に反映させるよう、神の助けを受けつつ歩む。このことを、パウロは言っており、パウロ自身がそのように生きている最中に、この手紙を書いたのでした。
キリストを模範とする私たちの歩みは、「理想か現実か」の二者択一であってはいけないと思います。自分自身の現実、現状というものを認めつつ、なおキリストという理想にあこがれ、神に赦されながら、キリストに近づこうとするのです。まれに「自分はクリスチャンをやめた」という人と出会いますが、日曜日の礼拝に行かないとか、献金や奉仕をしないとか、酒やたばこを飲むといったことが「クリスチャンをやめる」ということではなくて、イエス・キリストへのあこがれを失うこと、イエス・キリストという理想を捨てること、自分の内的な性質がキリストとまったく同じものに変えられてゆくことを望まないことが「クリスチャンをやめる」ということではないかと、私は思ったりします。
イエスを私の主、私の救い主と信じた方は、その信仰ゆえにすでに救われています。「キリストの真実による義、その真実に基づいて神から与えられる義があります。」(9節)かつて、キリスト者を迫害するほどに熱心なファリサイ派だったパウロは、自分に厳しく、他者にも厳しく、人を裁いて歩く過去と決別し、キリストの福音を延べ伝えるために愛と寛容に生きるようになりました。キリストゆえにすべてを失い、キリストを得たパウロの、キリストにある自由の行使や恐れのない愛の実践の日々は、パウロに苦しみや試練を与えると同時に、喜びをもたらしました。もしも信仰者の歩みを「競争」という言葉でたとえるなら、その内容は、ゴールまで走って救いという賞を貰うことを目指す競争ではなく、理想に近づくことをあきらめそうになる自分自身との闘いなのかもしれません。キリストという理想に向かって、キリストの霊に支えられ、キリストと共に歩み続けるならば、苦しみもまた喜びになる。パウロはそういう経験をし続け、それを手紙に書きました。フィリピの信徒への手紙が「喜びの手紙」と呼ばれるのはそのためです。
8月10日の午後に、カトリック本寺小路教会において、仙台キリスト教連合「平和を祈る合同祈祷集会」が行われました。エキュメニカルな祈祷会です。私は参加しませんでしたが、夫がその祈祷会で用いられた「典礼聖歌390番」の歌詞を教えてくれました。今日の聖書のことばにも合うと思うので、最後にご紹介します。
「キリストのように考え、キリストのように話し、キリストのように行い、キリストのように愛そう。もはやこの身に生きることなく、キリストと共に生きるために。キリストの死をその身に受け、新たないのちに召されたなら。」
これが、ただ一つの「なすべきこと」です。