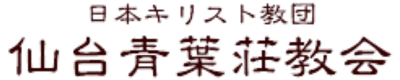テサロニケの信徒への手紙2章17節~20節
「再臨信仰を持とう」
牧師 野々川 康弘
今日の箇所の冒頭を見ますと、「兄弟たち、わたしたちは、あなたがたからしばらく引き離されていたので」そう記されています。これは一体どういう意味なのでしょうか。それを知るためには、第二次伝道旅行でパウロがテサロニケで伝道した時のこと、つまり、使徒言行録17章1節~9節のことを知る必要があります。
そこに記されているのは、マケドニア州の州都であるテサロニケに、ユダヤ人の会堂があったからこそ、テサロニケの地で伝道することにしたということです。
確かにパウロは、異邦人に福音を宣べ伝える使徒として、神に遣わされているという自覚を持っていました。でも、パウロの伝道のやり方は、いつもユダヤ人たちに福音を宣べ伝えるところから始めています。その理由は、主イエスがこの世に来られる前に、神の民の歴史を担ってきたのがユダヤ人たちだったからです。神の救いは、最初に彼らに現わされてきたからです。だからパウロは、テサロニケのユダヤ人の会堂で、三回の安息日にわたって伝道をしたのです。その結果、ユダヤ人の会堂で、沢山の人たちが主イエスの福音を信じる人たちが起こされました。特にユダヤ教に改宗したギリシャ人たち、町の有力者の婦人たちが、沢山救われました。でも、その一方で、ユダヤ人たちは、自分たちの会堂に出入りしていたギリシャ人たちや、町の有力者の婦人たちが、パウロの語る主イエスの福音を信じて、パウロに従うようになったのを妬んで、彼を迫害したのです。
その結果、ユダヤ人たちは、広場にたむろしていたならず者を、何人かを抱き込んで、暴動を起こして町を混乱させたのです。更には、主イエスの福音を信じたヤソンの家を襲って、パウロを民衆の前に引き出そうとして彼の家の中を捜したのです。それは、「ヤソンがパウロをかくまっている。」そういう訴えが彼らの耳に入ったからです。
そんな騒動が起こったからこそ、わずか3週間~1カ月足らずで、ヤソンに夜のうちに送り出されて、テサロニケを去って、次の町ベレヤへと、パウロは旅立たざるを得なくなったのです。
そういうこともあって、パウロはずっとテサロニケに出来たテサロニケ教会のことが気になっていたのです。生まれたばかりの教会の今後が、とても心配だったのです。
そんなパウロは、ベレヤに行った後、アテネの町で主イエスの福音を宣べ伝えていました。でもそこでテサロニケ教会のことが気になって、我慢の限界が来て、テモテをテサロニケに派遣したのです。そのことが記されているのが、テサロニケ信徒への手紙1の3章1節~5節です。
そんなパウロは、アテネの町で主イエスの福音を宣べ伝えた後、アテネの町からテサロニケ教会に派遣したテモテと合流して、コリントで主イエスの福音を宣べ伝えたのです。テモテと合流した時、パウロはコリントで、テモテからテサロニケの報告を聴いたのです。その時に、テサロニケ信徒への手紙1をパウロは書き記したのです。
パウロはもっとテサロニケで、主イエスの福音を宣べ伝えたかったのです。でも、それが許されず引き離されてしまいました。その悔しさが現れているのが、17節の「兄弟たち、わたしたちは、あなたがたからしばらく引き離されていたので」という言葉です。でも、パウロの悔しい気持ちがこもったこの言葉には、パウロのテサロニケ教会に対する熱い愛を垣間見ることが出来ます。その理由は、17節の「しばらく引き離されていた」という言葉は、「一時間の間、子供を失っていた」そう解釈出来る言葉が使われているからです。
つまり17節でパウロが言わんとしていることは、「テサロニケの人たち、わたしたちは、あなたがたからほんの束の間、僅か一時間ぐらい子供であるあなたがたを見失っていた。。。でもそれは、顔を見ることが出来ないという意味であって、心が束の間、僅か一時間ぐらい離れていたという意味ではない。そんなことを言っている内に、あなたがたの顔を切に見たいと望むようになりました。」そういうことです。
このことから分かるように、パウロはとてもテサロニケ教会の人たちを愛していました。
でも、テサロニケにもっと滞在したいと思いながらも、次の町ベレヤに行かざるを得なくなった時もそうですが、いつもサタンにテサロニケに行くことを妨げられたのです。
でも、どのようにサタンに妨げられたのかは、聖書からは具体的には分かりません。
でも、テモテからテサロニケ教会の報告を受けたパウロは、テサロニケ教会に対する心配が吹っ飛んで、喜びに満ちたのです。そのことを伺い知ることが出来るのが、19節~20節です。そこでパウロは、「わたしたちの主イエスが来られるとき、その御前でいったいあなたがた以外のだれが、わたしたちの希望、喜び、そして誇るべき冠でしょうか。実に、あなたがたこそ、わたしたちの誉れであり、喜びなのです。」そのようにテサロニケ教会のことを褒めています。
パウロがテサロニケ教会のことを、褒めるに至ったテモテの報告は、一体どういう内容だったのでしょうか。それが記されているのが、テサロニケ信徒への手紙1の3章6節です。そこを見ますとこう記されています。「テモテがそちらからわたしたちのもとに今帰って来て、あなたがたの信仰と愛について、うれしい知らせを伝えてくれました。また、あなたがたがいつも好意をもってわたしたちを覚えていてくれること、更に、わたしたちがあなたがたにぜひ会いたいと望んでいるように、あなたがたもわたしたちにしきりに会いたがっていることを知らせてくれました。」
このテモテの報告は、パウロをとても勇気づけました。その理由は、どんなに沢山の迫害に襲われていようとも、どんなにサタンに色々な妨害をされようとも、テサロニケ教会の信仰は成長していたからです。そのことを通してパウロが確信させられたことは、自分が福音の種さえ蒔けば、神がその種を、ちゃんと主イエスの再臨のその時まで、きっちり育て上げて下さるということです。
真に、コリント信徒への手紙Ⅰの3章6節~7節に記されている通りです。そこを見ますと、「わたしは植え、アポロは水を注いだ。しかし、成長させてくださったのは神です。ですから、大切なのは、植える者でも水を注ぐ者でもなく、成長させてくださる神です。」そう記されています。
パウロは、福音の種をテサロニケで蒔いて、まだ新芽しか出ていないような中で、迫害に遭って、次の町ベレヤへ、旅立たざるを得なかったのです。だから心配で心配で、ベレヤの後に行ったアテネの町で、福音の種を蒔いていた時、テモテをテサロニケに送ることにしたのです。それだけではありません。何度も何度もテサロニケに戻ろうともしたのです。でも、サタンにことごとく妨害されたのです。そんな中で、テサロニケ教会の人たちの信仰が成長している報告をテモテから受けたのです。パウロが、「わたしは植え、アポロは水を注いだ。しかし、成長させてくださったのは神です。ですから、大切なのは、植える者でも水を注ぐ者でもなく、成長させてくださる神です。」この言葉を、後に第三次伝道旅行の時に、エフェソから、コリント教会に書き送ることが出来たのは、テサロニケの教会成長のことが脳裏をよぎったからかもしれません。
福音を信じたばかりのテサロニケ教会が、いわば、赤ちゃんのようなテサロニケ教会が、色々な迫害を受けている中で、神の導きと守りによって、信仰が成長して、愛に満ちた教会に育っていっていたのです。
そのことが分かったパウロは、テサロニケ信徒への手紙1の3章7節で、「兄弟たち、わたしたちは、あらゆる困難と苦難に直面しながらも、あなたがたの信仰によって励まされました。」そうテサロニケ教会の人たちに言っています。
どんなに迫害に遭おうと、どんなにサタンの妨害があろうと、自分が福音の種さえ蒔くならば、神がその種を、主イエスの再臨のその時まで、きっちり育て上げて下さるという確信を得たパウロは、19節~20節でこのように言っています。「わたしたちの主イエスが来られるとき、その御前でいったいあなたがた以外のだれが、わたしたちの希望、喜び、そして誇るべき冠でしょうか。実に、あなたがたこそ、わたしたちの誉れであり、喜びなのです。」
この意味は、「私たちの主イエスが再臨された時、その御前で、聖霊の義の実を結んだあなた方以外の誰が、私たちの希望、喜び、勝利者の花冠になりえるでしょうか。実に、あなたがたこそ、主イエスが再臨された時の私たちの誉れであり、喜びなのです。」そういう意味です。
つまりパウロは、主イエスの再臨の時に、自分たちが神の栄光を受ける者に化ける栄化の姿をテサロニケ教会に見ていたのです。聖霊の義の実を結ばしめて、広い意味の救いを完成して、決して死ぬことがない新しい体を得て、神と、神を信じる人たちと、永遠に生きることが出来る栄化の姿。それをテサロニケ教会に見ていたのです。
そこで、私たちが問われることがあるのです。それは、私たちはテサロニケ教会の人たちのように、どんなに迫害が襲ってこようとも、どんなにサタンに妨害されようとも、聖霊の義の実を結ばしめていくことが出来るでしょうか。
確かに、聖霊の義の実を結ばしめていくことが出来るようになるのは、まずは、私たちが神を無視する罪の身代わりとなって、主イエスが十字架に架けられて殺されたことを信じることから始まります。
信仰義認を得て、神を無視する歩みから、神を神とする歩みに変わる関係の変化、リラティブチェンジが起こらなければ、神の言葉を聴いて、聖霊の力を借りて、義の実を結ばしめるという内実の変化、リアルチェンジは起きません。
でも、リラティブチェンジとリアルチェンジは連動しています。切り離すことは出来ないのです。
リラティブチェンジの恵みに与っている人は、リアルチェンジがあるし、リアルチェンジの恵みに与っている人は、リラティブチェンジがあるのです。それが、主イエスの広い意味の救いに与っている人。主イエスの再臨の時に栄化の恵みに与ることが出来る人です。
私たちは、狭い救いである信仰義認に与っている者として、こうあるべきという律法主義に陥ることなく、かといって、狭い救いである信仰義認に与っているから、何をしても大丈夫という静止主義に陥ることなく、主イエスの十字架・復活・昇天の救いの御業に与っている神の子として、一日一日、神の言葉をちゃんと聴いて、聖霊の義の実を結ばしめながら、主イエスの再臨のその時まで、皆さんと共に豊かに歩んでいければと心から願っています。
最後に一言お祈りさせて頂きます。