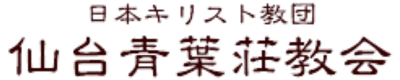ヨハネ黙示録1章7節
「教会が弾圧された意義」
牧師 野々川康弘
今日は、ホーリネスの弾圧記念礼拝です。
昭和17年6月26日。日本基督教団第六部の日本聖教会と、第九部のきよめ教会の牧師たち、つまり、ホーリネス教会の牧師たちが検挙されて教会は解散させられました。
実は、昭和17年6月26日に行われた検挙は一第一次検挙であって、第二次検挙もあったのです。第二次検挙は、昭和18年~19年まで国内外で行われました。第一次と第二次を合わせるなら、合計139名のホーリネス系の牧師が検挙されたのです。仙台青葉荘教会7代目の牧師、中島代作先生も、昭和17年6月26日の午前5時に特高警察に検挙されました。
当時、日本聖教会ときよめ教会を合わせて383人の牧師がいました。383名中139名が検挙されたということは、約35パーセントのホーリネス教会の牧師が検挙されたことになります。
検挙された139名の牧師の内、75名の牧師が起訴されて、最高4年の実刑を受けました。不起訴になった教師の中には、約一年間、留置所生活をすることになった方もおられました。更に言うと、7名の牧師が獄死しました。
当時、日本聖教会と、きよめ教会を合わせて、295の教会ありました。そのうち270もの教会が、国の命令で解散させられました。
悲しいことは、牧師が検挙された後、教会員が集まって、検挙された牧師の妻に、自主的に解散することを申し出た教会もありました。
私たちが属しているホーリネスの群れは、第九部のきよめ教会に属していました。当時、きよめ教会の財産処理を担当していた牧師の報告によりますと、教会の財産を売却して、弁護士費用や牧師家庭の必要のために、財産を売却したお金を用いたと言っています。
当時のホーリネス教会の牧師たちも、また牧師の家庭や信徒さんたちも、とても大変だったと思います。
今日は、ホーリネス教会に対する、政府の弾圧の原因は一体何だったのか。また、弾圧にあったホーリネス教会は、どういう信仰を持っていたのか。そのことを皆さんと共に学びたいと思います。
弾圧は、理由なしに起きるわけではありません。必ず、それなりの理由があるのです。
その理由を知るためには、まず最初に、政府が教会を弾圧しなければならないと思った時の、日本の社会情勢がどういうものだったのかを知る必要があります。
日本は、昭和3年頃までは、大正デモクラシーの時代でした。その時は、言論の自由が認められていて、何でも自由に話すことが許されていました。その当時は、宣教の自由もありました。でも昭和4年に、世界金融大恐慌が起こりました。そのことによって、日本経済が破綻していったのです。昭和5年には、失業者が250万人を超えて、「大学は出たけれど」という言葉が当時の流行語になったと言われています。その時に、第一次産業が中心である農村、漁村は、大きな打撃を受けました。まともに食べることが出来ない児童があふれて、子供たちの生活は荒廃したのです。農村、漁村では、娘を売り出す悲しい事件も頻繁に起こりました。そういったこともあって、政府の対応が不十分であるとして、当時の首相であった浜口雄幸(はまぐちおさち)が、東京駅で狙撃されました。彼は一命を取り留めましたが、このことを期に退陣しました。そんな時代だったからこそ、社会主義運動や共産主義運動が台頭してきました。そして、そういう運動に、日本全土が飲み込まれていきました。
そんな中、昭和5年、犬養毅(いぬかいつよし)が首相になって、犬養内閣の方策によって、景気の回復が徐々に見え始めていました。しかし、軍事予算の削減、軍事力に対する非難によって、当時、社会不安を感じていた若い海軍将校たちの政治不安が強化されて、若い海軍の将校に、犬養毅(いぬかいつよし)は射殺されました。
そんな中、日本では、軍国主義が台頭してきました。
実は、治安維持法は大正15年に出来たものです。治安維持法は、共産主義の拡大を脅威とみて、皇室や私有財産を否定する運動を取り締まることを目的として制定されました。だからこそ、昭和3年3月15日に、共産党の活動をしていた多くの人たちが政府の弾圧を受けたのです。
でも、軍国主義が盛んになっていく中で、昭和10年に、宗教に対してまで、治安維持法が適用されるようになりました。宗教に対しても、天皇・皇族・神宮に対して、尊敬の念を持っておらず無礼であるという理由や、宗教を、国を変革するために利用しているという理由で、治安維持法が適用されるようになって、宗教家が政府の弾圧を受けるようになりました。
そんな社会情勢の中、日本基督教団の中では、日本精神とキリスト教の調整が色々な形で行われるようになっていったのです。九州バンドの1人である海老名弾正は、「新日本精神について」という講演の中で、「日本の多神教も改革していけば、キリスト教と神道を『同一の宗教』に行きつかせることは可能である」そう言っています。
彼は、自分の言ったことを、彼が属していた組合教会で実行に移しました。当時、組合教会では、三位一体を神道に当てはめて、日本の神話と主イエスの誕生や復活の類似点を探して、両者を強引に同一視しようとしたのです。でも、そういう動きは、組合教会に限ったことではありません。当時の他の日本基督教団の教会や、日本基督教団のメソジスト教会の中にも、そういう動きが起こりました。ある牧師は、「天皇の臣民(しんみん)であることは日本人の大公約数だ。われわれは日本人である。クリスチャンであるけれども日本人である」そう語っていたそうです。
当時、国家権力の圧力によって、キリスト教がそのようにされたというよりも、政府を恐れて、自発的にそういう主張に傾いていったと言われています。当時の日本のキリスト者の多くは、天皇制とキリスト教の同一性を求めたのです。
実は日本基督教団は、昭和15年に、治安維持法に基づいた宗教団体法によって設立されたのです。日本基督教団が設立された時、教団規則として、主イエスが神であると口では言いつつも「天皇中心の国策に私たちは協力していく」そう記したのです。教会の中で疑問を持った方が大勢いたはずですが、その思想が受け入れられて、そういう規則に沿って、日本基督教団は歩み出すことになったのです。当時、日本基督教団の講演会で、衆議院議員であった松山常次郎が、「私たちは宗教を信じる場合、全て皇室中心、皇祖崇拝思想を中心として出発しなければならないのであります。」そう語った記録が残っています。つまり、日本基督教団は、天皇中心の思想を持たなければならなかったのです。
実は、天皇を中心とした政治の復興を目指していた大本教が拡大していたことを憂いていた日本政府は、昭和2年に、「文部大臣は、宗教団体の秩序を維持するために、必要な処分をすることができる」そういう文言が11条に入った宗教法案(後の宗教団体法)を打ち出していました。この11条の趣旨は、宗教そのものを、政府が監督して取り締まることが出来るというものでした。この宗教法案を、中田重治は、国が思想統一をし始めたとして大きな危機感を持ったのです。そのため、教会がどういう行動を起こすべきかを祈りつつ考えて、反対運動を起こしたのです。彼は、普段はあまり交わりのない色々な教会と連携して、「我々キリスト信徒は、信教の自由の束縛、あるいはこれに類する案の提出に反対する。」そういう決議をして、法案を国会へ提出することを反対する運動をしたのです。しかし、その運動も虚しく、昭和14年に、政府に教会の監督権が与えられる宗教法案が成立したのです。そして、その翌年に、その宗教法案が公布されました。それが宗教団体法です。この法律は、宗教団体が成立する時、教団のトップに誰かが就任する時、個教会が成立する時に、国家の許可が必要であるという法律です。また、この法律は、教会の行事の制限や、教会の行事を禁止する権利が政府にあるという法律なのです。
そういう宗教団体法にのっとって、設立に至った日本基督教団の在り方に、ホーリネス教会は苦しみました。でも、宗教団体法に沿わなければ、宗教活動は国に認められなかったのです。
ちなみに、宗教団体法の下で教会と認められるためには、教会数50以上、信徒数5000人以上という規定がありました。これよりも小さい宗教団体は、日本政府は、宗教活動を認めなかったのです。教会数50、信徒数5000人とは、かなり無茶苦茶な数字です。だからやむをえず、いろいろな教派が集まって、日本基督教団が昭和15年に結成されるに至ったのです。
国の圧力によって、設立に至った日本基督教団を、悪の力によって無理やり一つにされたと捉えた教団や教会は、戦後、日本基督教団を抜けていきました。しかし、国の圧力によって設立に至ったとしても、たとえ悪の力がそこに働いた結果だったとしても、「神の御手の内で起こったことである。そこに神の摂理がある。」そう捉えた教団や教会は、戦後、日本基督教団に残り続けたのです。
ホーリネス教会の中でも、ホーリネスの群れは教団に残り続けました。それはともかく、ホーリネス教会は、国家に認められて宗教活動を行うために、つまり、宗教団体法をクリアーするために、個教会としてではなくて、ホーリネスの群れとして(当時、ホーリネスの群れは監督制の教会だったからです。)、日本基督教団に加入することになって、第9部として活動することになったのです。
でも、先程申し上げました通り、宗教団体法にのっとって、運営されていた日本基督教団の在り方に、ホーリネス教会は大変苦しんだのです。
ホーリネス教会は、神社参拝を拒否していました。あるホーリネス教会の役員の息子は、神社参拝を拒否したという理由で、学校の退学を求められたといいます。また、「特高資料」によると、ある牧師夫人は、神社参拝しないために顔が変形するほど、なぐられたといいます。でも、その牧師夫人は、そういうことがあっても、尚も、神社参拝を拒否し続けたということが記されているのです。
また、最初の方で申し上げました通り、ホーリネス教会の7名の牧師が獄中死しています。獄中死には、暴力が関係していると言われています。
そういう厳しい時代でしたので、多くの教会は、国の方針に抵抗することなく、そのまま受け入れていました。教会は、教会組織を守るために、国の方針に反しない範囲で信仰を守るという判断に立っていたのです。多くの教会が、信仰を守るために、何をしなければならないのかということを考えるよりも、国の方針にあらがうことなく、日本の精神と一つになることを求めていったのです。
そのため、「えっ!この教会が?」、「えっ!この牧師が?」、と思うような人たちが、「愛する友のために死ぬというのは、喜んで戦争で死ぬことであり、戦争に行かなければならない」そういう説教をしたり、それに対してアーメンと言っていたりしたのです。当時の多くのキリスト教会は、国教会のように、政府に完全に従っていた状態だったのです。
そういう時代にあって、ホーリネス教会は異質な存在でした。ホーリネス教会は、戦争は賛成していたものの、四重の福音に堅く立って再臨信仰を貫いていました。
中田重治は、黙示録1章7節の言葉、つまり「見よ、その方が雲に乗って来られる。すべての人の目が彼を仰ぎ見る、ことに、彼を突き刺した者どもは。地上の諸民族は皆、彼のために嘆き悲しむ。然り。アーメン。」という言葉。これを信じるが故に、主イエスの再臨があることを信じていたのです。
黙示録1章7節が言っていることは、「見よ、主イエスが再臨される。キリスト者も、キリスト者でない者も、そんな彼を仰ぎ見る。でも、彼を殺した人、彼の救いを拒絶した人たちは、彼が再臨したことを嘆き悲しむ。これは本当のことです。」そういうことです。
中田重治は、本当の王なる主イエスが再臨して、王なる主イエスと、王なる主イエスの救いを信じている者たちと、ずっと一緒に歩めるようになることを、心から待ち望んでいたのです。
これは、東京聖書学校で聞いたことですが、山岡先生の若き日に、皆で学校の屋根に上り、主にロープをくくりつけて、天から引っ張るような動作をしながら、「主よ、来たりませ!」そう叫んでいたというのです。馬鹿ばかしい話と言えばそれまでです。でも、この馬鹿ばかしい話に、純粋なホーリネス信仰の継承を見ることが出来ると私は思っています。
この馬鹿ばかしい話は、人間の理屈を越えている神が、ちゃんと働いて下さっていることを信じて、頭・心・行動で、再臨を待望していた何よりの証拠です。
当時、日本基督教団では、新神学、つまり19世紀に出て来た近代ドイツ神学が盛んな時でした。ですから、主イエスの復活や再臨を信じていない教会があったのです。
そんな中で、中田重治は、社会がどのように変化していった時に、主イエスの再臨が起こるのか。そのことを熱心に研究していたのです。彼は再臨を待ち望む意味で、社会の変化にとても興味を持っていたのです。
彼は社会運動自体に、興味を持っていたわけではありません。あくまで、再臨の時に備えるために、社会の変化にとても興味を持っていたのです。
そんな彼が絶えず考えていたのは、主が再び来られるその時まで、日本人キリスト者の使命として、一体何をしていくべきなのかということでした。
そんな彼は、昭和7年11月に淀橋教会で、「聖書より見たる日本」という聖書解釈の連続講演を行っています。その講演の内容から分かるのは、日本が破竹の勢いで、西へ西へと進んでいっている中で、彼は黙示録の東から翼を呼ぶという御言葉を思い起こしながら、日本が軍事力をもって、必ずエルサレムが回復する力を与えると考えていたということです。その証拠に、講演の中で、「中国に進駐して行くと日本軍隊はそのままエルサレムまで行く」そう語っています。また、「きよめの友」という本を見ますと、「反戦主義を私はとらない。なぜならば神は戦争を通してその業を進めている。その証拠として日本が中国を占拠している。それが必ずエルサレムまで行く。そして、イスラエルの建国を助ける」そう彼は書いています。
彼がそういう思想を持つに至ったのは、「主が私たち一人一人に使命を与えているように、国や全ての民族に、使命を与えておられる。」そう考えていたからです。そして彼は、「日本の使命は、イスラエルの建国を助けること。」そう結論付けています。
彼は、「黙示録7章の、5人の天使は各民族を表わしていて、東の天使は日本民族のことである。」そのように「きよめの友」に書いています。つまり彼は、「偽キリストが現われて、世界を乱そうとする時、イスラエルを助けるために戦っていくのが日本である。」そう考えていたのです。
でも、彼のその解釈は間違っています。でも、間違っている彼の解釈を通して、私が言いたいことが一つあるのです。
それは、当時のホーリネス教会は、天皇を神とするのには、猛烈に反対していました。しかし、政府が大切にしていた戦争への協力や、天皇中心として生きるという考え方に対しては、反対してはいなかったのです。その証拠に、「きよめの友」という本の中で、彼は「天皇中心の社会が聖書的である」そう書き記しています。また、「日本のために祈ること、天皇のために祈ることはホーリネスきよめ教会にとって大事なことだ。」そう書き記しているのです。
だから、当時のホーリネス教会は、弾圧が起こって牧師が逮捕された時に、教会の人たちも、牧師たちも、牧師の家族の人たちも、とても驚いたのです。
確かに、天皇の神格化には激しく反対していました。でも、当時のホーリネス教会は、戦争の協力、天皇中心として生きるという考え方に対しては、全く反対していなかったのです。それなのに何故、弾圧を受けたのでしょうか。
それを知るために、ホーリネス教会の信仰を確認したいと思います。ホーリネス教会の信仰は、新生、聖化、神癒、再臨を信じる信仰です。特に再臨は、前千年王国説を信じる信仰です。前千年王国説とは、主イエスが再臨した後、千年王国とよばれる王国がこの世に誕生する。そう信じる信仰です。
実は、千年王国と呼ばれる王国がこの世に誕生するという信仰が、弾圧を受ける原因になったのです。千年王国のことを、日本政府は革命運動の一つであるとして、危険な思想と見做して弾圧したのです。日本政府は、ホーリネス教会は、神社参拝を拒否しただけではなくて、天皇の権威をも否定して、ユダヤ人中心の国家の建設を援助するために伝道をしている。そう解釈したと言われています。つまり、共産主義運動の人たちが、共産主義社会を目指したのと同じであると判断されて、弾圧をされたということです。
何故そう言えるのでしょうか。それは、弾圧のために拘置所で召された仙台青葉荘教会3代目の牧師、菅野鋭(すげのとし)先生の尋問調書や、起訴状の中にそういった内容が記されているからです。菅野鋭(すげのとし)先生は、尋問される中で、「千年王国は、社会制度の変革であり、天皇政治から神政治に変わることである。」そう言っています。そして、「信仰を持つ以上、神がなされる政治が一日も早く布かれることを切望しているものでございます。」そう言っていたことが尋問調書に記されているのです。
特高資料には、「多くの教会は、ホーリネス教会の牧師たちに対して、知識のない者、誤って聖書を解釈する者、政治と宗教を混同していると言って批判している」そう記されています。
何故、日本基督教団の多くの牧師から、そういった批判が日本政府に寄せられていたのでしょうか。それは、近代ドイツ神学の問題が絡んでいます。リベラル派の中には、主イエスの復活も再臨も無いとしている教会が在るのです。それに対してホーリネス教会は、主イエスの復活も再臨も信じているのです。
でも、ホーリネス教会の先輩牧師たちは、教団内や政府から、弾圧を受けたことを誇りに思っていると誰もが言っています。何故でしょうか。それは、迫害を受けたことで、復活信仰、再臨信仰の証が立ったと思っていたからです。
私たちも、ホーリネスの伝統を持つ教会に召されている者として、ホ―リネス教会の先達たちが大切にしてきた復活信仰、再臨信仰を、いついかなる時も、皆さんと共に、貫いていくことが出来ればと思っています。
最後に一言お祈りさせて頂きます。