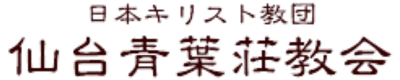申命記8章2節~10節
「悔い改めるとは」
牧師 野々川康弘
今回の箇所は、出エジプトした後のイスラエルの民に、神が荒れ野の40年という試練と教訓を与えた理由は、親が子を慈しむように慈しむためだったこと。神を信頼する人は、生涯、神によって全て必要なものが備えられて、生活が守られて、神を賛美するようになること。そういったことが記されています。
今日は主に3つのことを覚えたいと思います。
1つ目は3節後半の、「人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった。」という言葉から、「主の口から出るすべての言葉によって生きる」という言葉。それを心に刻みたいと思います。
2節の御言葉を原文で見ますと、「思い起こせ」という言葉から始まっています。一体何を思い起こせと言っているのでしょうか。
それは、主が導かれた40年の荒れ野の旅のことです。40年間、荒れ野の旅を強いられた理由は、イスラエルの民が罪を犯したためです。
では、イスラエルの民が犯した罪とは一体何だったのでしょうか。それは、民数記14章34節に記されていることです。そこを見ますと、「 あの土地を偵察した四十日という日数に応じて、一日を一年とする四十年間、お前たちの罪を負わねばならない。お前たちは、わたしに抵抗するとどうなるかを知るであろう。」そう記されています。
これはイスラエルの民が、神の命令通り、カナンの地に偵察に行った際に、その土地に、強そうな民がいることを知って恐れて、泣き言や不平を言い続けて、カナンの地を与えるといった神の言葉を信じなかったが故に、荒れ野の生活が40年に引き伸ばされることになった神の審判です。この審判を神が下した理由は、神を信頼しない彼らが、神がお与えになった言葉を心から守り続けたいと願うかどうか。そのことを、神が長くイスラエルの民と関わる中で見極めるためだったのです。だから神は、40年の荒れ野の生活を、彼らにさせることを決定したのです。
神はその荒れ野の生活を、3節前半が言っている通り、「苦しめ、飢えさせ」たのです。その理由は、今までのイスラエルの先祖たちも、荒れ野時代のイスラエルの民自身も、かつて味わったことのない「マナ」という食べ物を食べさせるためだったのです。
「マナ」のことは、出エジプト16章に出てきます。「マナ」とは、荒れ野の旅の中で食べ物が何もない時に、神がイスラエルの民に養って下さった時の食べ物のことです。
神が40年という長い荒れ野の生活を彼らにさせた理由は、人間の努力で何も得ることの出来ない荒れ野という過酷な場所で、神の恩寵によって与えられる食べ物でのみで生かされるという実感を、彼らが日々の生活の中で味わうことが出来るようになるためだったのです。それこそが3節の、「人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった。」という意味です。
イスラエルの民が、40年間、荒れ野で生活をしていた時、そこには全く何も無かったのです。食べ物も、飲む水も、衣類もなかったのです。普通に考えれば、体の健康なんか到底守られるわけがありません。しかし、そんな悪条件の中で、彼らは全てを神に与えられて、守られたのです。そのことこそ4節に記されている、「この四十年の間、あなたのまとう着物は古びず、足がはれることもなかった。」という意味です。
このように神が荒れ野の旅を40年間導いたことを、2節の冒頭で、「思い起こしなさい」そういっているのです。信仰とは、過去に神に与えられた恵みを数えることから始まるのです。でも残念なことに、イスラエルの民は、40年間の神の導きを思い起こしなさい。「人は主の口から出るすべての言葉によって生きる。」そう忠告されていたにも関わらず、その後のイスラエルの民の歩みは、神への背信→神の審判→民の悔い改め→救済が繰り返されるのです。その結果、アッシリア捕囚、バビロン捕囚を経験することになるのです。
神を侮ってはいけません。神は罪をお赦しになっても、罪の刈り取りは必ずさせる御方です。そのことは、聖書を読んでいけば分かります。
それはそうと、イスラエルの民は、アッシリア捕囚、バビロン捕囚を経験してもまだこと足りず、主イエスを十字架に架けて殺すことにまで至るのです。そこに人の愚かさや、罪深さを見ることが出来ます。
でも、そのような人間のどうしようもなさにピリオドを打つために、救いの完成として、神が受肉し、主イエスとして現れて、十字架・復活・昇天の救いの御業をなして下さったのです。
つまり神は、人間に対して、自分の力で潔くなることを求めてなんかいないのです。そんなことよりも、人間の力では決して潔くなれないことを認めて、神が救いを完成して下さったという神の恩寵を知って、それを信じて、神を頼って生きること。つまり御言葉に頼って生きること。そのことを、神は人間に対して望んでおられるのです。
2つ目は5節の、「あなたは、人が自分の子を訓練するように、あなたの神、主があなたを訓練されることを心に留めなさい」という言葉から、「人が自分の子を訓練するように、あなたの神、主があなたを訓練されることを心に留めなさい」という言葉を、心に刻みたいと思います。
神の恩寵を知って、それを信じて、神を頼って生きるようになることが大切だとしても、それをすること自体がとても難しいのです。その理由は、私たちが罪人だからです。私たちは自己中心で、神を無視して歩んでいる罪人であるが故に、神の御言葉を蔑ろにして日々歩んでいるのです。そんな私たちであるが故に、神が私たちに願われている道から大きく外れていくのです。
それは、イスラエルの民の歴史がそれを証明しています。だからこそ5節は、「人が、自分の子を訓練するように、あなたの神、主があなたを訓練されることを心に留めなさい。」そう言っているのです。
荒れ野の生活の最中、イスラエルの民は神のテストに失敗して、神に背いてしまうことが多々ありました。そして、その失敗の刈り取りを神はイスラエルの民にさせたのです。
その失敗の刈り取りの一つが、イスラエルの民の荒れ野の生活が40日から40年になったことです。
神は、罪の刈り取りの40年という長い時間使って彼らを切り捨てず、彼らを再訓練したのです。その時、彼らが学び得たものは神の戒めを守ること。神の道を歩むこと。神を畏れることだったのです。でも残念なことにイスラエルの民は、イスラエルの歴史を見れば分かる通り、神の再訓練を受けた時に学び得たものを、その後の歩みに生かし続けることが出来なかったのです。その結果、アッシリア捕囚、バビロン捕囚の苦難を受けることになったのです。これこそが、罪人である人間の姿なのです。
荒れ野の試練を本当の意味でクリアー出来た人は、主イエスだけなのです。マタイ4章1節~12節と、ルカ4章1節~11節に記されている誘惑の出来事、つまり、試練、荒れ野、飢え、40日の試みというテーマは、出エジプトからカナンの地に向けての荒れ野の旅と全く同じテーマなのです。主イエスは、40日の試みをクリアーしたのです。でも、イスラエルの民は40日の試みに失敗して、40年という長い月日の試みが追加されてしまったのです。このことから言えることは、罪人である人間は、神を信じて歩んだとしても、失敗をいつもしてしまうということです。
しかし、その失敗を用いて、神との関係がより深まっていくようになるために、イスラエルの民を長い時間をかけて、神が再訓練したように、私たちキリスト者を鍛え上げる御方なのです。
私たちキリスト者が何度失敗したとしても、最終的には人間の親が、子供の失敗を叱って再教育をして、最後に親としての尻拭いをするように、神も御自分の子供となったキリスト者のめんどうを見て下さるのです。途中で放棄することなく、最後まで責任をもってめんどうを見て下さるのです。
言葉は若干、不適切かもしれませんが、親としての尻拭いの表れこそ、十字架・復活・昇天の主イエスの救いの御業といっても過言ではないのです。
神の訓練は、広く大きな視野で見るならば、つまり、木ではなく森で見るならば、親として、尻拭いをしてくれることまで視野にいれた、とても思いやりに富んでいるものなのです。
でも私たちは、神の訓練を、狭く小さな視野でついつい見てしまうのです。木を見て森を見ないのです。
私たちが、今、目の前にある訓練の苦しさのみに囚われないように気を付けることは、とても大切なことです。
ハンス・セリエという心理学者はこのように言っています。「ストレスは人生のスパイスである。」人生に張りがなさすぎて弛みっぱなしであれば、人は本来の持ち味を発揮して生きられません。神は皆さんの持ち味を存分に発揮出来るようになるために、自分の子である私たちを、時に厳しい訓練を施すのです。
そんな愛に富んでいる神であるからこそ、6節は、「あなたの神、主の戒めを守り、主の道を歩み、彼を畏れなさい。」そのようにイスラエルの民を諭しているのです。
主の訓練は、神の民というアイデンティティーを確立するためのものです。だから6節は、そんな慈愛に富んだ神を神として畏れ敬って、神の指示に従って、主がよしとされる生き方をすることの勧めがなされているのです。
最後に7節~10節の、「あなたの神、主はあなたを良い土地に導き入れようとしておられる。それは、平野にも山にも川が流れ、泉が湧き、地下水が溢れる土地、小麦、大麦、ぶどう、いちじく、ざくろが実る土地、オリーブの木と蜜のある土地である。不自由なくパンを食べることができ、何一つ欠けることのない土地であり、石は鉄を含み、山からは銅が採れる土地である。あなたは食べて満足し、良い土地を与えてくださったことを思って、あなたの神、主をたたえなさい。」という言葉から、「あなたを良い土地に導き入れようとしておられる」ということを心に刻みたいと思います。
6節の「主の戒めを守り、主の道を歩み、彼を畏れなさい。」という神の勧めに応えていくとすれば、どんな祝福が約束されているのでしょうか。そのことが記されているのが7節~10節です。7節~10節を見ますと、「土地」という言葉が7回も出てきています。これは完全数です。つまり、完全に祝福されることが約束されているのです。そして、よく見るならば、7節と10節に「良い土地」という言葉が出てきていて、その間に、5つの良い土地が記されているのです。5つの良い土地とは、1.水が豊かな土地、2.農作物が豊かに実る土地、3.果実が豊かな土地、4.食物に困らない土地、5.鉄と銅が豊かな土地です。つまり、神の主権を認めて、神を信頼して歩む人の実生活は、未来永劫、素晴らしく祝福されることが約束されているのです。
ということは、日々、主の戒めを守り、主の道を歩み、神を畏れて歩むならば、霊的なことだけではなくて、この地上の実生活も含めて、素晴らしい祝福に与ることが出来るようになることが約束されているのです。
神は私たちを、霊的なことだけではなくて、実生活をも、祝福したいと願われている御方なのです。
結論を言えば、神は私たちの今の実生活も、死んだ後も、素晴らしい祝福を与えたいと願っておられるが故に、神の御言葉に生きることが出来るように、私たちを日々訓練されるのです。逆に言うと、神の御言葉に生きない自己中心な自分勝手な生き方は、今の実生活も、死んだ後も、神の素晴らしい祝福を失うことになるのです
でも、いつも神に背を向ける罪深い私たちは、神の御言葉によって生きることを愛するのではなくて、神の御言葉によって生きない自由奔放な生き方を愛するのです。そんな生き方を自由であると思い込んでいるのです。本当の自由は、ルールーがあってこその自由なのです。ルールがない自由は、自分の首を絞める結果に至る自由なのです。そんな自由は、不自由なのです。
不自由を愛する私たちは、本当の自由を私たちに与える御言葉というルールに従って歩めないのです。
主イエスは、そんな私たちの罪の代価を支払うために、十字架にお架かりになられて死なれたのです。
キリスト教会がいう罪の悔い改めとは、神を無視するあまり、神の御言葉を蔑ろにして歩む生き方を辞めることです。つまり、神と向き合って生きるようになって、神との関り故に、神の言葉をちゃんと心に蓄えて生きるようになることが、罪を悔いあらためるという意味なのです。それが、180度方向転換するということなのです。
そういう180度の方向転換が起こってこそ、今も死後も、充実した命が得られるようになるのです。
そのことを心に刻み込んで、いつも罪の悔い改めを大切にして、今週一週間、皆さんと共に歩んでいければと心から願っています。
最後に一言お祈りさせて頂きます。