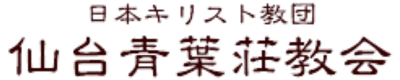使徒言行録8章26節-40節
「神を知る=礼拝する」
牧師 野々川康弘
今日の箇所は、フィリポの伝道のことが書き記されています。彼はエルサレム教会で食事の世話をするために、ステファノと共に選ばれた7人の内の1人です。
でも、ステファノの殉教を機に散らされて、サマリアの町で伝道をしていたのです。そんな彼は、26節に記されている通り、「エルサレムからガザへと南に下っていく、寂しい道を行け。」そのように天使に語りかけられたのです。だから彼は、そこに向かっていったのです。そうしたら、一人のエチオピア人の宦官に出会ったのです。
そのエチオピア人の宦官のことは、27節で紹介されています。そこを見ますと「エチオピアの女王カンダケの高官で、女王の全財産を管理していたエチオピア人の宦官」そう記されています。
宦官とは、女王や、王の周囲の女性たちに仕えるために、去勢された男性のことです。宦官は、男性機能を失うことと引き換えに、王の周囲の女性たちに仕える高い地位や、名誉を得ていたのです。そんな彼は、エルサレムで礼拝して、帰る途中、イザヤ書を朗読していたのです。その証拠が27節~28節です。そこを見ますとこう記されています。「エルサレムに礼拝に来て、帰る途中であった。彼は、馬車に乗って預言者イザヤの書を朗読していた。」
エチオピアからエルサレムに向かう旅は、当時、とても大変な旅だったのです。行って帰るのに、何カ月もかかったと言われています。それでも彼は、「エルサレム神殿に行きたい、主なる神を礼拝したい。」そう思ったのです。
彼の国には国の宗教があったのです。それでも彼は、「エルサレムに行って、ユダヤ人たちの信じている神を礼拝したい。」そう思ったのです。そこまで強い思いを持って、エルサレム神殿に行って礼拝をしたのです。でも彼は異邦人です。異邦人がエルサレム神殿で礼拝をしようと思ったとしても、そこには厳しい隔ての壁があったのです。
彼は異邦人であるが故に、エルサレム神殿の「異邦人の庭」までしか入れなかったのです。異邦人は、その庭までしか入ることは許されなかったのです。その庭からもう一つ中に入ると、ユダヤ人女性が、入ることが許されていた「婦人の庭」がありました。さらにその奥には、ユダヤ人の男性だけが、入ることが許されていた聖所があったのです。
異邦人でしかなかったエチオピアの宦官は、神殿の中心から、かなり離れた場所からしか、礼拝できなかったのです。
でも彼は、腹を立てなかったのです。当然のこととして受け止めていたのです。主なる神の民であるユダヤ人と、そうでない人たちとの間に区別があるのは、「当然なこと」と思っていたのです。そんな彼は、神の民のみが、与えられるものがあるのは、「当然なこと」と思っていたのです。
以前にも申し上げました通り、ユダヤ人は、血のつながった民族的集団ではないのです。割礼さえ受けていれば、血のつながりがあっても、なくても、ユダヤ人になることができるのです。ユダヤ人は、血が繋がっているということではなくて、割礼という神の民の印がある、信仰共同体です。割礼を受けて、神の民に加わっている人と、そうでない人と、区別が設けられているのは、当然のことです。
そんなことよりも、エチオピア人の宦官が問題にしていたのは、「ユダヤ教に改宗したい。主なる神の民に加えられたい。」そう思っても、それが叶えられないということです。
その理由は、彼が宦官だったからです。申命記23章2節を見ますと、こう記されています。「睾丸のつぶれた者、陰茎を切断されている者は主の会衆に加わることはできない。」
宦官は、去勢された男性であるが故に、割礼を受けて、神の民であるユダヤ人になることが出来なかったのです。
そこに、彼の深い悲しみがあったのです。そういう深い悲しみがあったにも関わらず、彼はエルサレムを離れるとき、大金を使って、イザヤ書を買ったのです。
この当時、聖書の中にある書簡の一つ一つが、大きな巻物になっていたのです。その巻物は、よほどのお金持ちでなければ、買うことが出来なかったのです。でも、エチオピア人の宦官は、大金を使って、イザヤ書を買ったのです。そして、馬車に揺られながら、故郷に帰る途中に、それを読んでいたのです。
そのことから彼は、宦官としての、隔ての壁があるにも関わらず、主なる神を真剣に求めていたことが分かるのです。
私たちはどうでしょうか。私たちは、隔ての壁があると、すぐに挫けてしまうのではないでしょうか。私たちは、隔ての壁があったとしても、宦官のように、真剣に神を知ることを求めているでしょうか。
それはそうと、何故エチオピア人の宦官は、イザヤ書を買って、読んでいたのでしょうか。それはおそらくイザヤ書56章3節-8節と、関係しています。
そこにはこう記されています。「主のもとに集って来た異邦人は言うな。主は御自分の民とわたしを区別される、と。宦官も、言うな。見よ、わたしは枯れ木にすぎない、と。なぜなら、主はこう言われる。宦官が、わたしの安息日を常に守り、わたしの望むことを選び、わたしの契約を固く守るならわたしは彼らのために、とこしえの名を与え、息子、娘を持つにまさる記念の名を、わたしの家、わたしの城壁に刻む。その名は決して消し去られることがない。また、主のもとに集って来た異邦人が、主に仕え、主の名を愛し、その僕となり、安息日を守り、それを汚すことなく、わたしの契約を固く守るならわたしは彼らを聖なるわたしの山に導き、わたしの祈りの家の喜びの祝いに連なることを許す。彼らが焼き尽くす献げ物といけにえをささげるなら、わたしの祭壇で、わたしはそれを受け入れる。わたしの家は、すべての民の祈りの家と呼ばれる。追い散らされたイスラエルを集める方、主なる神は言われる。既に集められた者に、更に加えて集めよう、と。」
此処には、異邦人も、宦官も、神の民になることを許される恵みが記されています。律法的には、神の民から排除されている異邦人や宦官が、神の大いなる恵みによって救いにあずかることが記されているのです。
この箇所こそ、エチオピア人の宦官が、イスラエルの民の神を、求め続けることができる希望だったのです。
彼は、この箇所に記されている救いは、一体何によって実現するのか。そのことを知りたかったからこそ、イザヤ書の巻物を読んでいたのです。
フィリポが天使の導きにより、エチオピア人の宦官が乗っていた馬車の傍らに立った時、エチオピア人の宦官が朗読していたのは、イザヤ書53章7節-8節でした。此処には、屠殺場に引かれていって、苦しめられて、正当な裁きが行われず、殺されていく人のことが記されています。
エチオピア人の宦官が読んでいたのは、「苦難の僕」そう言われているところです。注目すべきことは、今日の33節に「子孫」という言葉があることです。
苦難の僕主イエスは、命を断たれることが定められていたが故に、自分の子孫を持つことが出来ませんでした。それは、エチオピア人の宦官の姿でもあります。去勢されていた彼は、子孫を得る望みが断たれていました。そんな宦官に対して、イザヤは、イザヤ書56章3節を通して、「わたしは枯れ木にすぎない」と言うな。そう言っていたのです。宦官には、その言葉がとても響いたことでしょう。
彼は、自分のことを、自分は新しい芽を出すことができない枯れ木のような者。そう思って、苦しんでいたのです。でも、イザヤ書53章の「苦難の僕」の10節には、こう記されています。「病に苦しむこの人を打ち砕こうと主は望まれ、彼は自らを償いの献げ物とした。彼は、子孫が末永く続くのを見る。主の望まれることは彼の手によって成し遂げられる。」
「病に苦しむ」という言葉は、「痛む」そう訳すことが出来る言葉です。口語訳聖書では、イザヤ書53章10節を、こう訳しています。「しかも彼を砕くことは主のみ旨であり、主は彼を悩まされた。彼が自分を、とがの供え物となすとき、その子孫を見ることができ、その命を長くすることができる。かつ主のみ旨が彼の手によって栄える。」
つまり、イザヤ書53章10節は、「子孫を残すこともできずに殺されたはずの主イエスが、子孫が末永く続くのを見る」そう約束しているのです。それと似たことが、イザヤ書56章5節にも記されています。そこを見ますと、「むすこにも娘にもまさる記念のしるしと名を与え、絶えることのない、とこしえの名を与える。」そうイザヤは言っています。
エチオピア人の宦官は、「自分にとっての大きな希望がそこにあるのではないか。」そういう思いで53章を朗読して、一生懸命理解しようとしていたのです。そんな彼に、フィリポはこう語りかけたのです。「読んでいることがお分かりになりますか。」
宦官は「手引きしてくれる人がなければ、どうして分かりましょう」そう言って、フィリポを馬車に乗せて、自分の傍らに座らせたのです。そこから、フィリポの聖書の説き明かしが始まったのです。
つまり、フィリポがした伝道は、聖書のみ言葉の説き明かしです。宦官は「苦難の僕」について、フィリポに、「どうぞ教えてください。預言者は、だれについてこう言っているのでしょうか。自分についてですか。だれかほかの人についてですか」そう質問したのです。
簡単に言えば、彼の質問は、「いわれのない苦しみを受けて殺されて、子孫が末永く続くのを見る約束をされた人は誰なのか?」そういう質問だったのです。その質問に対してフィリポは、35節に記されている通り、「聖書のこの個所から説きおこして、イエスについて福音を告げ知らせた」のです。
つまりフィリポは、「苦難の僕と呼ばれている人は、主イエスのことである。」そのように明確に、宦官に答えたのです。
フィリポは、「何の罪もないのに、えられて、裁きを受けて死んだ苦難の僕とは、神の独り子主イエスのことである。主イエスは、私たちが神を無視する罪の身代わりとして懲らしめを受けて、打ち砕かれて、殺された。だから、私たちが神を無視する罪が赦されて、神の民として迎え入れられる道が出来た。主イエスが、「子孫が末永く続くのを見る」そのように父なる神に言われた理由は、主イエスの罪の身代わりである十字架を信じて、神の子となった神の民が誕生するからである。そこには、異邦人や宦官を排除するような隔ての壁は、もはや何もない。イザヤ書56章で、約束されている異邦人や宦官の救いは、主イエスの十字架、復活、昇天の御業によって実現した。今や宦官であるあなたも、主イエスの救いの御業故に、神の民になるように招かれている。主イエスの救いの御業を信じて、信仰告白をして、洗礼を受けるなら、神の民となることが出来る。」そう宦官に、イザヤ書を解き明かしたのです。
フィリポの聖書の説き明かしを聴いた宦官は、「神の民になりたい!」そう思いながらも、自分では、どうしても乗り越えることが出来なかった隔ての壁を、主イエスの救いの御業が破壊して下さって、自分を神の民に加えて下さろうとしていることを知ったのです。
そのことを宦官が知るや否や、フィリポに対して、「ここに水があります。洗礼を受けるのに、何か妨げがあるでしょうか。」そう言ったのです。それが記されているのが36節です。それに続く37節は、今日の箇所に記されていません。実は37節は、272ページに記されています。そこを見ますと、「フィリポが、『真心から信じておられるなら、差し支えありません』と言うと、宦官は、『イエス・キリストは神の子であると信じます。』と答えた。」そう記されています。
37節のことを経て、エチオピアの宦官は洗礼を受けて、新しい神の民の1人として、教会に加えられたのです。
彼が洗礼を受けると、「主の霊がフィリポを連れ去った。宦官はもはやフィリポの姿を見なかったが、喜びにあふれて旅を続けた。」そう39節に記されています。宦官に聖書を説き明かして、彼に洗礼を授けたとたんに、フィリポは彼の前からいなくなりました。でも宦官は、「喜びにあふれて旅を続けた」のです。
洗礼を受けて、神の民とされた人は、喜びにあふれて、この世の旅路を歩んでいくようになるのです。
宦官は、「自分は宦官であるが故に、割礼を受けることが出来ないから、神の民にはなれない。遠くからしか礼拝することが出来ない。自分がどんなにあこがれても、神の民の中に、入ることが出来ない人として、一生を過ごすしかない。」そう思っていたのです。
そう思っていた彼が、神の民とされたのです。神の民として、神を礼拝する教会の一人とされたのです。
また宦官は、自分は宦官だから、「子供を持つことができない。子孫を見ることができない。財産を築いてもそれを遺してあげる人はいない。自分は枯れ木なのだ。」そう思っていたのです。
そんな中、主イエスの救いの御業に与ったことで、息子や娘を持つ以上のもの、つまり、決して消し去られることのない自分の名が、聖書の中に刻み込まれて、主イエスに連なっている兄弟姉妹という家族を与えられたのです。その喜びは、宦官にとっては、何物にも替え難い喜びであり、何物によっても奪い去られることのない喜びだったのです。
その喜びは、その喜びを告げしらせてくれたフィリポがいなくなっても、決して失われることのない喜びだったのです。
御言葉を説き明かす伝道者の姿は消え去って良いのです。
宦官は、聖書を熱心に読んでいたのです。でも、自分ではそれを理解することが出来なかったのです。福音を正しく聞き取ることが出来なかったのです。だから、手引きしてくれる人が必要だったのです。そこに、聖書を説き明かす教職者の存在意義があるのです。でも教職者は、その役目が終れば消え去っていくのです。大事なのは教職者ではなくて、主イエスの福音と、聖書を熱心に読んでいる人、神学をしている人が、結びついていくことなのです。
自分を救って下さった神を、礼拝するために教会に来ている人たちが、主イエスの十字架・復活・昇天の救いの御業に喜びにあふれて、神と永遠に旅を続けていくようにサポートすることが、教職者の働きの目的なのです。
宦官が故郷に向かう旅、これから先、彼がこの世で歩んで行く旅は、主イエスの救いを信じて、洗礼を受けたことで、全く新しい、喜びにあふれるものとなったのです。私たちの人生の旅も、主イエスの救いを信じて、洗礼を受けることで、新しくなります。
私たちが神の民の一人となる時、つまり、私たちのために肉を裂かれて、血を流して下さった主イエスの体と血とを覚えて、主イエスとの交わりに生きる人となった時、神を毎週礼拝することを、喜びとする自分の人生の旅を、この世で送っていく人になるのです。
カルバンは、「本当の神を知るということは、神を礼拝する者となることである。」そう言っています。その通りだと思います。主イエスの救いを知った人は、毎週の礼拝を喜ぶ人となるのです。
そのことを、今日、私たちの胸に刻み込んで、今週一週間、皆さんと共に歩んでいければと心から願っています。
最後に一言、お祈りさせて頂きます。