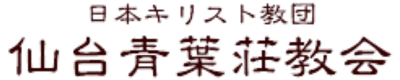「固定概念からの解放」
マルコ12章41節~44節
牧師 野々川 康弘
聖書の言葉は、神の言葉です。神の言葉であるからこそ、聖書は、私たちの理解を超えている言葉です。私たちの理解を超えている神の言葉に耳を傾けて聴いていくならば、私たちの常識は打ち砕かれて、私たちの小ささを知るようになるのです。
私の友人は、ある時、私にこういったことを言っていました。「神学の学びは、海岸で、砂のお城を造るようなものだ。砂の城を造った瞬間に、海の波で削られる。だから砂の城を修復する。でもまたそれも、海の波で削られる。そういう繰り返しをしていくこと。それが神学をするということなのだ。」
本当にその通りだと思います。神を知るために学んで、「神を知った」そう思った瞬間に、その知ったはずの神像は削りとられて、また学んで、また神を知ったはずの神像が削り取られていくのです。そういう繰り返しの中で、神を人間の力で知ることが出来たなら、それはもはや神ではないことを教えられるのです。神学は、神がミステリーとしていることと、神が開示していることを、ちゃんと区分け出来るようになることなのです。でもそれが難しいのです。その理由は、人間は罪人だからです。人間は、神の手放す権威を蔑ろにして、掴み取ることが出来る権威を欲するのです。そんな人間は、自分が分かること、自分の手でしっかり握りしめることが出来ることを好むのです。でも、それが、神の言葉である聖書を遠ざけるのです。
私たちは、聖書を知ることが大切なのではありません。そうではなくて、私たちは聖書を知ることが出来ないからこそ、聖書を神に知らされることがとても大切なのです。
今日は皆さんと、マルコによる福音書12章41節~44節を、神学したいと思います。
今日の41節-42節を見ますと、「イエスは、賽銭箱の向かいに座って、群衆がそれに金を投げ入れる様子を見ておられた。大勢の金持ちがたくさん入れていた。ところが、一人の貧しいやもめが来て、レプトン銅貨二枚、すなわち一クァドランスを入れた。」そう記されています。此処には、多くの金持ちと、一人の貧しいやもめと、群衆と、主イエスが登場しています。
今日の話は、エルサレム神殿で起こった事です。エルサレム神殿は、民族、性別、人の立場で、入ることが出来る場所が決まっています。女性は、婦人の庭の先にある、男子の庭や、男子の庭の先にある、祭司の庭に、入ることは禁じられていました。ということは、今日の貧しいやもめの献金の話は、エルサレム神殿の、婦人の庭が舞台になっているということになります。実は、婦人の庭に、ラッパの形をした13の献金箱が当時ありました。その献金箱が置いてあるところに、大勢の金持ちがやって来て、たくさんの献金を投げ入れていたのです。献金箱はラッパの形をしていました。それ故に、お金を投げ入れると、音がよく響いたのです。その響きは、投げ入れる硬貨の種類や数によって、音が変わりました。例えば、日本の500円玉を投げ入れたなら、500円玉は、大きくて重いので、音が大きく響くのです。でも1円玉は、小さくて軽いので、音は殆ど響きません。大勢の金持ちは、大きくて重い硬貨を、沢山投げ入れていたが故に、大きい音が鳴り響いていたのです。そんな中、ひとりのやもめがやって来て、レプトン銅化2枚を投げ入れたのです。レプトン銅貨は、今でいえば、1枚50円程度の硬貨です。
当時、レプトン銅貨より、小さいお金は無かったのです。そこから容易に想像出来ることがあります。それは、レプトン銅貨は軽くて、大きな音が鳴り響かなかったのではないかということです。主イエスは、音が鳴り響かないレプトン銅貨2枚を、投げ入れたやもめに対して、43節~44節に記されている通り、「はっきり言っておく。この貧しいやもめは、賽銭箱に投げ入れている人たちの中で、だれよりもたくさん入れた。皆は有りあまる中から入れたが、この人は、貧しい中から自分の持っている物をすべて、生活費を全部入れたからである。」そう言ったのです。
実は、今いった43節~44節の主イエスの言葉は、二つの解釈が存在しています。一つは、やもめの信仰に対する、主イエスの賞賛の言葉として解釈するもの。もう一つは、やもめの置かれた状況に対する、嘆きの言葉として解釈するものです。やもめの信仰に対する、主イエスの賞賛の言葉として解釈する方は、すでに何回も聴いたことがあると思います。
今日の箇所を、やもめの信仰に対する賞賛の言葉として解釈するならば、やもめの神への応答姿勢を、主イエスが賞賛したことになります。そして、その解釈は、積極的に神へ応答していくこと、自分の精一杯を神に捧げていくこと、そういったことが、中心的テーマとなります。
その解釈は、とても大切な解釈です。ホーリネス教会である私たちの教会は、その解釈に立っています。でも、その解釈に立ちつつも、違う解釈があることを、知る必要があると思います。では、違う解釈とは、一体どういう解釈なのでしょうか。それは、43節~44節の主イエスの言葉は、やもめの置かれた状況に対しての、嘆きの言葉であるという解釈です。この解釈は、43節~44節の「はっきり言っておく。この貧しいやもめは、賽銭箱に投げ入れている人たちの中で、だれよりもたくさん入れた。皆は有りあまる中から入れたが、この人は、貧しい中から自分の持っている物をすべて、生活費を全部入れたからである。」その主イエスの言葉を、38節~40節の言葉と結び付けて、考えるところから来ています。特に40節の冒頭を見ますと、主イエスは律法学者たちに、「やもめの家を食いものにしている」そう言っています。そして、やもめの家を食い物にしている実態が、41節~42節です。そこを見ますと、「この貧しいやもめは、賽銭箱に入れている人の中で、だれよりもたくさん入れた。 皆は有り余る中から入れたが、この人は、乏しい中から自分の持っている物をすべて、生活費を全部入れたからである。」そう記されています。その実態を、律法学者たちが、彼らのみせかけの献金で引き起こしたことを、主イエスが嘆いた。そう解釈することが出来るのです。もしその解釈でいくならば、今日の箇所は、やもめを食いつぶして、やもめを虐げたことに対する、主イエスの嘆きということになります。
私たちの教会が立っている解釈と、今ご紹介した解釈は、根本的に考え方は違っています。でも、どちらにも共通していることがあります。それは、やもめの献金額そのものを、主イエスは見ておられないということです。主イエスは、献金するやもめの心を見ておられるのです。
やもめの話に戻りますけども、金持ちから見たら、レプトン銅貨2枚は、投げ入れても大して音が鳴らない、わずかなものです。でも、やもめにとっては全財産です。レプトン銅貨2枚が、全財産だからこそ、それを全て捧げることは、容易ではありません。でも、やもめはその全てを捧げたのです。私たちの解釈からすれば、「やもめは、心から神を信頼して、喜んで捧げた。やもめの信仰は、素晴らしい信仰である。」そう思うのです。そんな私たちは、43節の「はっきり言っておく。この貧しいやもめは、賽銭箱に入れている人の中で、だれよりもたくさん入れた。皆は有り余る中から入れたが、この人は、乏しい中から自分の持っている物をすべて、生活費を全部入れたからである。」この主イエスの言葉は、やもめの信仰に対する賞賛の言葉である。そう受け止めています。
でも、この言葉を、やもめの置かれた状況に対しての、主イエスの嘆きの言葉である。そう解釈したら、少し違って来ます。
41節を見ますと、「大勢の金持ちがたくさん入れていた。」そう、記されています。「入れていた」という言葉は、原文を見ますと未完了形になっています。未完了形ということは、継続している状態にあるということです。つまり、金持ちだった律法学者たちが、「次々と、たくさん投げ入れ続けていた」状態にあったのです。そんな中で、とてもレプトン銅貨2枚の内、1枚だけを投げ入れる雰囲気ではなかったのです。やもめは、ひょっとしたら2枚のうち、1枚だけは残しておきたかったのかもしれません。でも、金持であった律法学者たちが、見栄をはって、次々と大金を投げ入れて、大きな音を響かせている中で、たとえ音が大して鳴らなかったとしても、レプトン銅貨2枚全てを、捧げなければならい気持ちに、追い込まれていたのかもしれないのです。金持ちだった律法学者たちの行動が、意識的ではなかったにしても、やもめに、持っている全財産を、献げなければならないように追い込んでいた可能性があるのです。
そういった理解に基づいて、「はっきり言っておく。この貧しいやもめは、賽銭箱に投げ入れている人たちの中で、だれよりもたくさん入れた。皆は有りあまる中から入れたが、この人は、貧しい中から自分の持っている物をすべて、生活費を全部入れたからである。」そういう43節~44節の主イエスの言葉を考えるならば、この主イエスの言葉は、やもめが、金持ちだった律法学者たちの献金によって、圧迫を受けていたことに対しての嘆きの言葉として語られた。そう解釈することになるのです。そして、そう解釈するなら、主イエスは律法学者たちが、やもめの心を、知らず知らずのうちに死に追いやっていることを、嘆いた言葉なのだ。そう解釈できるのです。そう解釈すれば、神や隣人との関係の死に、追いやっていく人の罪を、主イエスが嘆かれたということになります。
律法学者たちの、自己承認欲求からくる見栄が、沢山お金を入れることに繋がり、やもめを、神や、神の民との関係を遠ざけるように、別の言葉で言えば、神や、神の民との関係の死に、導いていたのです。そんな中で、主イエスは、「はっきり言っておく。この貧しいやもめは、賽銭箱に入れている人の中で、だれよりもたくさん入れた。皆は有り余る中から入れたが、この人は、乏しい中から自分の持っている物をすべて、生活費を全部入れたからである。」そう言って、律法学者たちの罪を断罪するのと同時に、孤独になっていたやもめを、独りぼっちに感じていたやもめを慰めて、神や神の民との関係に、引き戻したのです。
真に、マタイ16章25節に、「神の国は、自分の命を得ようとする者はそれを失い、わたしのために、自分の命を失う者は、それを見出すのです。」そう記されている通りです。
そこで、私たちが問われることがあります。それは、「自分は神の民ではないかも知れない。」そういう自己不安から脱却するために、周りから神の民として接してもらうための、見せかけの信仰になってはいないかということです。そして、見せかけの信仰生活を、日々送っているうちに、知らず知らずのうちに、人を、神や隣人との関係の死に、追い込んでしまっているなんてことはないでしょうか。
ある神学者は、こういったことを言っていました。「キリスト者とは、いつでもキリストの香りを持ち運んで、キリストを証するためにキリスト者とされている。キリスト者は、地の塩である。地の塩とは、この世で神の手放す権威が、キリスト者の歩みを通して見えることである。でもキリスト者は、神の手放す権威を、この世で十分に発揮して生きていない。発揮して生きていないどころか、この世の掴み取る権威を発揮して生きている。キリスト者がそうなってしまう理由は、聖書の法則と、この世の法則を分けて生きた方が、自分が楽だからである。」
本当にその通りだと思います。
人間は、いつも何かを得ようとして、この世を歩んでいます。この世では、沢山(たくさん)のものを得ている人が、人から尊ばれます。でも、神の世界では、失うことが尊ばれます。神のために、人のために、自分を失うことが尊ばれるのです。罪深い私たちは、自分を分け与える十字架の軛を負って、神と共に生きていくこと以上に、自分が楽になる自由を得るためや、自分の自己実現のために、神や人との関りを断っていくことを選ぶのです。
それが、神に背を向けて生きる罪です。そんな私たちの罪を赦し、私たちが自分を分け与える十字架の軛を負って、神と共に歩んでいくことが出来るようになるために、主イエスは十字架・復活・昇天の御業を成し遂げて下さったのです。
もし、その神の救いが、私たちの府に落ちているならば、神や隣人との関りを断ってでも、自分が楽になろうとしたり、自分の自己実現をしようとしたりすることを放棄するようになるのです。それだけではありません。神の救いが、腑に落ちている人は、自分が十字架に架かってでも、神や隣人を生かすように生きることを選ぶのです。関係を切ることなく、神や隣人と、共に生きていくことを選ぶのです。
かつてウエスレーは、私たちは罪人だから仕方がない。そういって罪の中に留まってしまっている人たちに対して、聖書の言葉を通して、徹底的に戦ったのです。
ウエスレーは、主イエスの十字架・復活・昇天の救いの御業は、人を変える力があることを知っていたのです。神の救いの御業は、神を見上げて歩む人たちを、神の子らしく整えていく力があるのです。
でも、そうはいっても、人間は所詮罪人なのです。いつも自分が楽になることばかり考えるのです。そんな罪深い私たちであることを、主イエスは知っておられたからこそ、十字架・復活・昇天の御業を成し遂げて下さったのです。そして、その救いをいつも見上げて、生きていくことが出来るように、毎週日曜日、仙台青葉荘教会の礼拝に、私たちを招いて下さっているのです。
毎週日曜日に、主イエスの救いの御業を見上げて、神に背を向ける罪が赦されていることを再確認して、神との関係に立ち返って、神との関係に生きている者として、神が私たちに願っている十字架を負っていく歩み。それをまた、月曜日から土曜日までしていくのです。
自分が楽になることばかりを考えるような罪深い私たちが、いつも十字架を負って、神との関係、隣人との関係に生きて行く自由を得られるようになるために、神は私たちを、毎週日曜日に、教会の礼拝に招いて下さっているのです。
罪人である私たちが思う自由は、自分が楽になっていくことです。でも、神が私たちに与えようとする自由、聖書が私たちに与えようとする自由は、私たちが十字架を負って、神と隣人との関係に生きて行くことです。確かにそれは、人間の固定概念を超えています。でも、人間の固定概念を超えたところにこそ、神の国を見る祝福が、与えられるようになるのです。
そのことを心に刻み込んで、今週一週間、皆さんと共に豊かに歩んでいければと、心から願っています。 最後に一言お祈りさせて頂きます