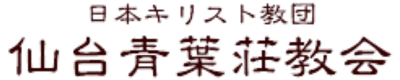マルコによる福音書16章1節‐8節
「復活の主と会える場所」
マルコによる福音書16章1節‐8節
「復活の主と会える場所」
牧師 野々川 康弘
安息日が終わって、日曜日の朝、三人の女性の弟子たちは墓に行きました。そうしたところ、墓の入り口を覆っていた大きな石がすでにわきに転がしてあったのです。だから彼女たちは、その墓の中に入ったのです。そうしましたら、白い長い衣を着た若者の天使が、右手の方に座っていたのです。彼女たちはそれを見て、「ひどく驚いた」のです。これはただ単に「びっくりした」ということではありません。5節の「ひどく驚いた」という言葉。これを原文で見ますと、「ひどく恐れた」そう訳すことが出来る言葉です。
ということは、女性の弟子たちは、若者の天使が右手の方に座っているのを見て、深い恐れを抱いたということになります。深い恐れを抱いた彼女たちに、天使は、「恐れることはない」そう語りかけたのです。これは、全然不思議なことではありません。たいていの人は、神の偉大な御業を見た時に恐れおののくのです。クリスマスの夜もそうでした。野宿していた羊飼いたちに天使が現れて、主の栄光が彼らを照らした時、彼らは「非常に恐れた」のです。その時も天使は、「恐れるな」そう羊飼いたちに語りかけて、神の救いの到来を、つまりは、救い主の誕生を、告げ知らせたのです。その時と同じように、主イエスが復活した日の朝に、女性の弟子たちに恐れが生じたのです。
その時に、恐れることはないと言った天使は、「あなたがたは十字架につけられたナザレのイエスを捜しているが、あの方は復活なさって、ここにはおられない。御覧なさい。お納めした場所である」そういった6節の言葉を、彼女たちに告げたのです。この言葉は、主イエスの復活が何であるかということを指し示しています。
墓は、人の遺体を納める場所です。この地上で、色々な業績を積み上げていた人が亡くなって、全てのことが過ぎ去って過去の人になる。それが墓です。
死んだ人は、生きている人に対して口出しすることは出来ないのです。それは、過去の人になっているからです。
なので、女性の弟子たちからすれば、主イエスは過ぎ去った人だったのです。過去の人になっていたのです。確かに、主イエスが遺体となった後も、彼女たちは主イエスを慕っていました。
でも、彼女たちは、「主イエスが、過去の人になったことを、受け入れなければならない。」そう思っていたのです。だから彼女たちは、主イエスに対する最後の奉仕として高い香料を買って、夜明けと共に墓に出かけたのです。墓にさえ行けば、主イエスと確実に出会うことが出来る。心おきなく涙を流しながら、主イエスに最後の奉仕を捧げることが出来る。そう思ったからです。そうすることで、悲しみにくれる自分たちへの慰めを求めていたのです。でも、墓の中にいたのは、主イエスではなかったのです。若者の天使だったのです。その天使が、「主イエスはここにはおられない」そう彼女たちに告げたのです。それが復活の出来事です。
主イエスが墓にいないということは、彼女たちの思い出の中だけに、生き続けるような過去の人になったのではないということです。主イエスは、生きて活動しておられるということです。もはや語ることの出来ない、過去の人になんかなっていないということです。ということは、主イエスは今、生きて働いていて、語りかけてくださるということです。
じゃあ、そんな主イエスと一体どこで出会うことが出来るのでしょうか。
実は、天使がそのことを7節で教えています。そこを見ますと、「さあ、行って、弟子たちとペトロに告げなさい。『あの方は、あなたがたより先にガリラヤへ行かれる。かねて言われたとおり、そこでお目にかかれる』」。そう記されています。
つまり、ガリラヤに行けば、復活した主イエスと出会えるということです。ペトロをはじめとする全ての弟子は、ガリラヤに行けば、主イエスと出会えるのです。
でも、何故、ガリラヤに行けば、主イエスと出会うことが出来るのでしょうか。それは、主イエスが先にそこへ行っておられるからです。主イエスが、ガリラヤにおられるからです。だから、そこにさえ行けば、主イエスと出会えるのです。
でも私たちは、そういった道理を、しばしば、わきまえないことがあります。私たちは、主イエスがおられる場所を求めて行くのではなくて、主イエスがおられる場所は此処である。そのように、自分で勝手に決めてしまっていることがあるのです。
自分が思い描いている場所。自分にとって都合の良い場所。そういった場所で、主イエスと出会おうとするのです。
例えば、主イエスは、神が定めた日曜礼拝に来ることを待っておられるにも関わらず、自分の都合が悪いから日曜礼拝には行けない。自分の都合の良い日に、自分の都合が良い時間に、インターネット礼拝に出席する。なんてことがあります。
もっというと、私たちは一生懸命、教会の礼拝に集い、聖書を読み、祈り、教会の色々な奉仕を担うならば、主イエスと出会える。主イエスがおられることを、豊かに感じることが出来る。そう思っているかもしれません。
確かに、礼拝に集い、聖書を読み、祈り、教会の奉仕を担うのは、キリスト者の生活において大切です。でも、主イエスとの出会いは、私たちが、これだけ頑張れば、出会うことが出来るという類のものでは無いのです。主イエスが、「来なさい」そのように言われる所に、私たちが行ってこそ、主イエスとお会いすることが出来るのです。
更に言うと、主イエスが待っている場所に行くことは、聖書が教えている言葉。そこに行くことでもあるのです。一字一句の聖書の言葉は勿論のこと、聖書の文脈や、書簡と書簡の繋がりを通して、御言葉が指し示しているところにこそ、主イエスが待っておられるのです。もし私たちが、自分勝手に聖書を解釈していくならば、私たちがいくら頑張っても、主イエスが待っておられるところに、行きつくことは出来ません。
私たちが、主イエスは、「ここにおられるはず。」そのように勝手に思い込むのは、もう動くことも、語りかけることも出来ない、墓に入れられている主イエスであると、見做している証拠なのです。
主イエスの復活の出来事は、「ここにおられるはず。」そう勝手に思い込んでしまう私たちに、「主イエスは、あなたが思っているそこにはおられない。」そう告げられる出来事なのです。
復活して生きておられる主イエスとの出会いは、私たちが、自分が思い描いている場所なんかではなくて、主イエスが決めておられる場所でこそ、出会うことが出来るのです。
自分が主イエスと、出会えたと感じる自分の感覚だけに頼るような信仰は、ある面で危険なのです。キリスト者である私たちは、「聖霊の導きを、今感じた。」そういう言葉をしばしば使っています。でも、自分の感覚ではなくて、聖書の文脈が示していること、書簡と書簡の繋がりあること。そういったことが無ければ、本当の主イエスの導きとはいえないのです。私の言葉で言うと、右脳的信仰(感覚的信仰)と、左脳的信仰(論理的信仰)がマッチしていなければ、そこに主イエスはおられません。
私たちは、女性の弟子たちが、「主イエスは、死んだのだからお墓におられるはずだ。」そう決めつけていたら、天使が、「あなたがたは十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさって、ここにはおられない。御覧なさい。お納めした場所である。さあ、行って、弟子たちとペトロに告げなさい。『あの方は、あなたがたより先にガリラヤへ行かれる。かねて言われていたとおり、そこでお目にかかれる。』そう告げた、6節~7節の言葉を忘れてはなりません。
彼女たちが天使に告げられたのは、主イエスとお会い出来る場所は、墓ではなくてガリラヤだったのです。
でも何故、主イエスは出会う場所を、ガリラヤに定めたのでしょうか。そのことを皆さんと共に考えてみたいと思います。
ガリラヤは、多くの弟子たちの故郷です。更には、若者の天使が、「ナザレのイエス」そう主イエスのことを呼んでいるように、ガリラヤは、主イエスの出身地でもあるのです。主イエスはそこで育って、そこから福音を、宣べ伝え始めたのです。そんな主イエスは、ガリラヤで12弟子を選びました。
12弟子と、ここに出て来るマグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメたちを中心とする女性の弟子たちは、ガリラヤから、主イエスにつき従って、遠いユダヤのエルサレムまで、一緒に旅をしてきていたのです。
でも、主イエスが捕えられて、十字架につけられた時、12弟子は皆、逃げ去ったのです。彼らは信仰が挫折して、途方に暮れていたのです。そんな彼らは、もはやエルサレムに留まっていることは出来なかったのです。挫折して、行き詰まった彼らは、どうすることも出来ず、敗北感を感じながら、故郷であるガリラヤに、戦に負けた兵士みたいに、帰るしかなかったのです。そんな12弟子の姿は、まるで、放蕩息子がぼろぼろの乞食のような姿になって、父の家に帰ったようなものです。
天使はそんなガリラヤに、復活した主イエスが先に行って、そこで彼らに会おうとしていることを告げたのです。
つまり、主イエスは御自分を見捨てて、逃げていった12弟子が、ぼろぼろになって流れ着いたガリラヤで、出迎えたのです。
ということは、復活した主イエスは、神に背を向ける罪を赦し、復活の命を12弟子たちに与えるために、ガリラヤで会うことを決めていたということになります。
実はそれこそが、若者の天使が、「あの方は、あなたがたより先にガリラヤへ行かれる、かねて言われたとおり、そこでお目にかかれる。」そう7節で言った本当の意味です。
そんな7節をよく見るならば、「弟子たちとペトロに告げなさい。」そう言った上で、「あの方は、あなたがたより先にガリラヤへ行かれる、かねて言われたとおり、そこでお目にかかれる」そう言っていることに気付かされます。
此処で疑問になるのは、ペトロも12弟子の一人なのに、何故、彼の名だけが、わざわざ挙げられているのかということです。
その理由は、主イエスが捕らえられた時、ペトロが、鶏が鳴くまでに、主イエスのことを三度「知らない」と言ったからです。3という数字は完全数です。ということは、ペトロは、主イエスと自分の関係を、完全に否定したということになります。つまり、主イエスの弟子であることを完全に放棄したのです。彼はそんな自分に失望して、ガリラヤに帰って、漁師の仕事に復帰しようとしていたのです。主イエスは、そんなペトロの心を知っておられたのです。だから、復活した主イエスは、ガリラヤに先回りして、彼の罪を赦し、復活の命を与えるために、待っていることを、
若者の天使に告げさせたのです。
此処に、主イエスのとっても深い愛が示されています。主イエスが、ペトロの一番弱いところまで降ってきて、神に背を向ける罪を赦し、復活の命を与えるためには、ガリラヤでなければならなかったのです。復活した主イエスは、罪に打ちひしがれて、方向転換しそうになったペトロを懸命に追いかけて、救ったのです。そんな主イエスの愛の眼差しは、今日、此処に集っている全ての人たちにも向けられています。
何故、そう言いきることが出来るのでしょうか。それは、若者の天使が、7節後半で、「かねて言われたとおり」そう言っているからです。「かねて言われていたとおり」とは、マルコによる福音書14章28節のことです。そこで主イエスは、弟子たちに対して、「わたしは復活した後、あなたがたより先にガリラヤへ行く。」そう言っていたのです。何故そういっていたのでしょうか。そのことを紐解く鍵は、マルコによる福音書14章27節です。そこを見ますと、主イエスは弟子たちに、「あなたがたは皆わたしにつまずく」そう言っていたことが記されています。
つまり、12弟子全ての信仰が挫折することを、すでに予告していたのです。でも彼らは、その当時、それがどんな意味なのかさっぱり分からなかったのです。それにも拘わらずペトロは、「たとえ、みんながつまずいても、わたしはつまずきません」そう言いきったのです。それを受けて主イエスは、「ペトロが今夜、鶏が二度鳴く前に、三度わたしのことを知らないと言うだろう。」そう言われたのです。
主イエスは、ペトロがこれから陥る信仰の挫折を見つめていたが故に、復活した後、あなたがたより先にガリラヤへ行く。そう既に予告していたのです。7節の「かねて言われたとおり」とは、「その時のことを思い出しなさい」そういう意味です。
最後になりますが、天使が告げた、「そこでお目にかかれる」という7節の言葉。その言葉に注目したいと思います。これは原文を見ますと、「あなたがたはそこで彼を見るであろう」そう訳すことが出来ます。この意味は、主イエスに背をむけて、ガリラヤに帰った弟子たちが、復活の主イエスと出会って、その罪が赦されて、復活の命を得る姿を「見る」ことになる。そう天使に告げられていたということです。
勿論これまでも、彼らは主イエスのことを見ていたのです。でも、肝心なことは、何一つ見えていなかったのです。
ペトロは以前、マルコによる福音書14章31節で、「たとえ、御一緒に死なねばならなくなっても、あなたのことを知らないなどとは決して申しません。」そう言っていました。その時、彼は、主イエスが見えていたつもりだったのです。でも実際に、彼が見ていたのは、自分の熱心と、決意によって、従っていくことが出来る主イエスだったのです。自分の力で、関係を保っていくことができる主イエスだったのです。彼はその数時間後、自分も捕えられてしまう恐怖から、主イエスを見失いました。自分の熱心や決意によって、築こうとしていた主イエスとの関係は、脆くも崩れ去ったのです。
信仰の挫折から、もはや自分から、主イエスとの関係を築くことが出来なくなっていた中で、「主イエスは、あなたがたより先に、ガリラヤへ行かれる。そこでお目にかかれる。」そう天使が告げてきた言葉。それが、ペトロに響いたのです。この御言葉に導かれて、ペトロを始めとする弟子たちは、本当の主イエスの姿を見るに至ったのです。
ペトロは、「自分の熱心と決意が、主イエスと自分との関係を支えていると思っていたけれども、そうではなかった。主イエスの愛によって、自分が支えられ、守られ、導かれていた。」そう気づかされたのです。
その結果、ようやく本当の意味で、主イエスを見ることが出来たのです。
私たちも、今日、登場した、女性の弟子たちや、12弟子のように、無意識のうちに、主イエスを墓の中に閉じ込めてしまっているということはないでしょうか。私たちが、全くそんなつもりは無かったとしても、罪人であるが故に、自分の考えや思いに合った、自分にとって都合の良い主エスを、見てはいないでしょうか。でもそれは、主イエスを墓に閉じ込めていることと同じです。墓に入っている主イエスと見做して、主イエスはもう何も語らない。そう思っていることと、同じなのです。
今日、神は、主イエスをつい墓に閉じ込めてしまう私たちに、「あの方は復活なさって、ここにはおられない」そう言われています。
この御言葉によって、私たちは、主イエスを見失うのです。これまで私たちが分かっていると思っていた主イエスが、一瞬、分からなくなるのです。でも、そうなることこが正しいのです。
私たちがそうなってこそ、今日の御言葉は、私たちにもう一つのことも告げて来るようになるのです。それは、主イエスが私たちより先に、ガリラヤに行っておられて、そこで私たちと出会って下さるということです。
ガリラヤは、自分の力や努力によって、立派な信仰者として歩んでいこうとすることが打ち砕かれる場所です。自分が打ち砕かれて敗北した結果、行きつく場所です。でも、復活した主イエスは、私たちが敗北することを分っているからこそ、既にガリラヤにいて、私たちに罪の赦しと、復活の命をそこで与えて下さるのです。
そんなガリラヤは、今日、私たちが集っている日曜礼拝です。日曜礼拝で与えられる神の御言葉の解き明かしを通して、つまり、聴くことの出来る聖餐である説教を通して、いつも主イエスを見失う、私たちの頑なな罪を指し示されると同時に、その罪の赦しが与えられて、復活して、永遠に続く神との関係、神を信じる人たちとの関係に生きる永遠の命に、生かされていくようになるのです。
そのことを覚えて、今週一週間、皆さんと共に歩んでいけたらと思います。
最後に一言お祈りさせて頂きます。