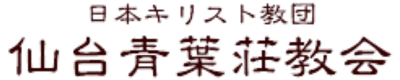ヨハネによる福音書9章1節~12節
「シロアムの池の癒し」
仙台松陵教会牧師 藤野美樹
仙台松陵教会の牧師の藤野美樹と申します。今日は、青葉荘教会の皆様をともに礼拝を守ることができ、嬉しく思っております。
私たちはいま、受難節の時を過ごしております。
受難節のとき、今一度、主イエスの十字架と復活の出来事が、この、わたしのために起きた出来事であることを知るときである、と思います。
神であるイエス・キリストは、十字架の上で死なれ、私たちの罪を赦してくださいました。主が、十字架の上で命を捨てて、罪を赦してくださったことが、どれほど大きな神の愛を示すものなのか。神様の憐みがいかにおおきなものか、私自身、理解しきれていないように思います。だからこそ、この受難節の時、もう一度深く、考え、御言葉から知らされたいと思います。
私たちは主の十字架の赦しなしには、生きてゆけないものです。神によりすがることによってのみ、生きることができる。神様の、その計り知れない大きな憐み、愛に触れたとき、私たちは本当に自分自身の罪を見つめ、悔い改めへと導かれるのではないでしょうか。
そして、主イエスの赦しの恵みのうちに、一人でも多くの人々が救われるよう、私たちが信仰と愛をもって、隣人の罪のために、執り成しの祈りを捧げる時でもあります。
そのために、わたしたちは、ともに御言葉に聞きたいと思うのです。
本日は、ヨハネによる福音書の御言葉を共に聞きました。
ヨハネによる福音書を読んでいますと、キリストは、私にとってどのような方であるか、ということを繰り返し、問いかけられているように思います。キリストとは、いったい、どのような方か、という問いは重要な問いであると思います。
今日はご一緒に、「シロアムの池の奇跡」の御言葉を聞きました。
この物語は、ある生まれつき目の見えない人が、イエス・キリストによって目が開かれ、キリストを信じるようになったという、奇跡の物語です。
主イエスは、ユダヤ教の「仮庵祭」という祭りの終わりに、神殿で、ユダヤ人たちと激しい論争をしました。その論争の争点は、「イエス・キリストとは一体誰であるのか」ということ。ユダヤ人たちは、主イエスが、神をご自分の父と呼び、御自分を神と等しい者であると公言されると、激しく怒りました。
主イエスは、たびたび、「安息日」に病人を癒すという奇跡の御業を行われました。安息日に奇跡の御業をなさったということは、主イエスご自身は神であり、「安息日の主」であることを示されるためでした。けれど、キリストが神の御業をなさればなさるほど、ユダヤ人たちはキリストを拒絶しました。イエス・キリストと言う人は、安息日の律法を破り、自分たちが大切にしてきたことをなし崩しにする。恐るべき存在でしかありませんでした。自分たちのアイデンティティーを崩す存在。
憎しみを募らせたユダヤ人たちは、主イエスを憎み、殺意を抱き、石を投げつけようとしました。けれど、この時はまだ、主イエスが十字架に付けられる時ではなかったため、主イエスは身を隠して神殿の境内から出て行かれたのです。主が神殿から去ろうとされたとき、起きた出来事が、本日の「シロアムの池の奇跡」の出来事です。
主イエスは、神殿の入り口に、一人の、生まれつき目が見えない男が座っているのを見つけられました。そして、彼に声をかけられました。その男は、大勢の人々が行き交うその場所に、毎日座って物乞いをしていました。彼は、長年、苦しみ続けていました。彼の病を治すことができる人は、これまで誰もいませんでした。彼がそこに座って物乞いをしている姿は、日常の光景であったと思います。彼に目を留め、立ち止まり、病を心配してくれる人など、いなかったと思います。彼自身もまた、大きく日常が変えられるような出来事など、期待もしていなかったのではないでしょうか。それは、闇のなかで、「深い淵の底」にいるような状態であったと思います。
けれど、ある日、彼にとって、思いもよらないような出来事が起きたのです。
イエス・キリストというお方が、目の前に現れたのです。神であり、言葉であるキリストが、彼に声をかけられたのです。キリストは、地面に唾をして、唾で土をこねて彼の目に塗られました。そして、「シロアムという遣わされた者という意味のある池に行って、目を洗いなさい」とひとことおっしゃった。彼は、主の言葉通りにしました。すると、彼の目は、見えるようになったのです。
彼は、イエス・キリストを知らなかったし、一度も、その目でキリストを見ていないのです、けれど、彼はただ、キリストの言葉に従いました。すると、キリストの言葉の通りになったのです。
この不思議な出来事に、いったいどんな意味が含まれているでしょうか。この出来事には様々な解釈があります。
たとえば、4-5世紀に生きたアウグスティヌスは、こう解釈しています。土と、キリストの唾でつくられた泥は、キリストの言葉そのものなのだと言っています。
また、16世紀に生きた、フランスの宗教改革者、カルバンは、このように解釈しています。
「人間は、はじめ、泥で創られたので、それと同じようにして目を創り直すために、わたしたちの主イエスは、泥を用いて、父なる神が人間の全身を創る時に示したのと同じ力を、肉体の一部において、示したのだ。」と言っています。
つまり、天地創造の時、神が土の塵から人間をお創りになられたのと、同じ神の御業を、神であるキリストは体の一部分において示されたのだ、ということです。
どちらの解釈に従っても、この奇跡に示されていることというのは、キリストが、御自分が神であることをはっきりと示された、と言うことであるということではないでしょうか。
ヨハネによる福音書1章1節には「初めに言があった。言は神と共にあった。言は神であった。この言は、初めに神と共にあった、万物は言によって成った。」とあります。言であり、神であるキリストが、目の見えなかった彼の目を見えるようにしたということは、ただ単に、肉体的に目が開かれた、というだけではなくて、神が、御自身の存在を、彼にはっきりと示されて、彼は神であり言であるキリストをはっきりと、見ることができたということなのではないでしょうか。
実際に、彼がキリストをその目で見るのは、35節以下のところです。それまでは、彼は一度も、キリストを見たことがありませんでした。けれど、彼は、キリストの言葉に触れ、その言葉に従うことによって、その言葉通りになるという経験をしました。見えなかった彼の目は、キリストの言葉によって、新しくつくりかえられるという経験をしたのです。彼は、苦難の中で、はっきりと、神の御業を見たのです。彼が、生まれて初めて、神が創造されたこの世界を目にしたとき、それはどんなに感動的であったでしょうか。彼は、キリストと出会い、光を見て、歩み出すことになるのです。彼にとって、キリストとは、闇から救いだしてくれた、光であり、真の救い主なのです。
9章を読んでみると、一つの奇跡の物語よりも後の部分のほうが、長く記されていることわかります。今日はお読みしませんでしたが、そこには、目が見えるようにされた彼とは、対照的な人々のことが記されています。キリストと出会い、目が開かれた彼とは対照的に、キリストを目の前に見ていても、キリストが誰であるかわからない人たちの姿です。彼らは、目の見えなかった人の目が開かれたとき、彼の喜びを共有することができませんでした。彼の両親でさえ、キリストが誰であるのか、わからなかったのです。彼らは、目の見えなかった彼に、尋問するようにしてこう尋ねます。
10節「お前の目はどのようにして開いたのか。」
すると彼は、こう答えました。
11節「イエスという方が、土をこねて私の目に塗り、『シロアムに行って洗い流しなさい』と言われました。そこで、言って洗ったら、見えるようになったのです。」
彼は、自分が経験した出来事をそのまま語りました。イエスという方が、自分の目を見えるようにしてくれた、と。けれど、人々は、それを信じようとしませんでした。そして、人々は、目の見えるようになった彼を、ファリサイ派の人々のところへ連れて行き、ファリサイ派の人々に判断を委ねるのです。
すると、今度は、ファリサイ派によって、まるで目の見えなかった彼が被告人であるかのような尋問が始まります。ファリサイ派の人々は尋ねます。「なぜ目が見えるようになったのか」。ファリサイ派の人々の中でも、「イエス・キリストとは誰であるのか」という問いを前に、意見が分かれ、分裂が生じたということが、9章の終わりにかけて、長い部分で語られています。
いくら、律法の専門家で、人々の間で権威を持っていたとしても、彼らには、主イエスがだれであるか、ということを見出すことができなかったということです。けれど、おもしろいことに、ファリサイ派の人々にもわからなかった、主イエスが誰であるか、という疑問を前に、目の見えなかった彼は、はっきりと答えるのです。
17節「あの方は預言者です。」。
彼は、キリストについて、大胆に、確信をもって、「キリストは預言者である」と、答えました。「主イエスは預言者である」という彼の理解は、不十分であったと思います。彼は、主イエスを「神の子です」とも言っていないし、メシアです、とも言っていないからです。けれど、彼は、主イエスが自分の目を癒してくださったことを感謝し、与えられた信仰に確信をもっているのです。38節で、彼は、「主よ、信じます」と告白しています。ファリサイ派の学者たちを前にして、何の学もなく、身分の低い者であったにも関わらず、大胆にキリストについての考えを、確信をもって述べたのです。
先ほどもご紹介した、宗教改革者のカルバンは、この出来事を、「もうひとつの奇跡」である、と述べています。目の見えなかった彼は、まだ、キリストが誰であるのか、「神の子」であることを、十分に理解していないであろうにも関わらず、「かくも率直に、大胆に、キリストは預言者である、と述べていることは、目が見えなかったのに、見えるようになったのと同じように、「奇跡」である」とカルバンは言っています。
このカルバンの言葉を受けて、自分が信仰告白を受け、信仰者となったときの記憶が甦りました。私は、両親が牧師のため、クリスチャンホームで育ちました。中学3年生のときに、教会学校の先生から、礼拝後に、母と買い物をしている最中、一通のメールを受け取りました。「そろそろ、信仰告白してみない?」というシンプルなメッセージ。でも、その言葉がとてもうれしく、信仰告白をしたいとすぐに思いました。それからしばらくして、母にそのことを相談しているなかで、信仰も持つということは、「イエス・キリストの十字架と復活を信じること」だというようなことを言われて、ショックを覚えました。なぜなら、その時、自分が本当にイエス・キリストというお方を思っているかどうか、突き付けられたからです。神様は信じているつもりでいたけれど、果たして、イエス・キリストという方を信じているかどうか。その時、私はキリストについて最低限のことしかわかっていなかったと思います。今でも、そうです。神について、キリストについて、まったく不十分な理解しか持っていなかったし、今もキリストについて十分に知ることはできていないけれど、でも、神様は、わたしに、信仰を与えてくださったのです。信仰を与えてくださったことは、カルバンが言うように、奇跡と言えるのだと思います。
教会に集う方々、みな、その奇跡に与っているのです。そして、毎週の礼拝で、ともに、主イエスの御言葉にアーメンと言えるということ、それ自体が奇跡と言えるのではないでしょうか。
目の見えなった彼が目を癒されたとき、キリストが誰であるのかわかりませんでした。彼は11節で、主イエスについて、このように言っていました。
11節「イエスという方が、土をこねてわたしの目に塗り、『シロアムに行って洗いなさい』と言われました。」
人々は、「その人はどこにいるか」と尋ねると、彼は、
12節「知りません。」と答えました。
この時彼はまだ、はっきりと、主イエスが誰であるか、わかっていなかったかもしれません。けれども、彼にはその時、キリストの言の通りにしよう、という信仰が与えられていたと思います。彼は、その与えられた信仰によって、わずかな光かもしれなかったけれど、その光を消すことなく、光輝かせようと、キリストの言の通りにしたのではないでしょうか。一方で語られている、奇跡の御業を信じることができなかった人々は、そのわずかな光をも、消さずに灯しておくことができませんでした。自らすすんで、その輝きを暗くしようとし、闇を招いてしまったのです。それは、肉体的な目は見えていても、「信仰の目」が閉じている状態と言えます。
主イエスを見ているのに、その本当の姿を見ることを拒み、灯を決してしまうということは、私たちにも起こり得ることです。
自分の立場、考え、経験などが、キリストをまっすぐに見ることを邪魔する時あります。また、時に苦難を襲ってきたとき、苦難の中から、神に向かって叫び、祈ることは、何と難しいことでしょうか。かといって、順風満帆に行っているときには、自信が自分の大半を占めて、神により頼むことができなくってしまうことがあります。自分自身、本当に罪深い者であると思います。本当に簡単なことに、心揺らぎ、神様をまっすぐに見られなくなり、光よりも闇を好む自分の罪。それは、「深い淵の底」にいるような状態だと思います。
けれど、そのような時、詩編130編の御言葉は、私たちを励ましてくれます。詩編の作者は、どのような時にも、神に叫びの声を上げることをすすめています。
詩編130編で、詩人はこのように歌います。
「深い淵の底から、主よ、あなたを呼びます。主よ、この声を聞き取ってください。嘆き祈るわたしの声に、耳を傾けてください。」
詩人は何度も、「深い淵の底」から、神に叫び、求めます。私の声を聞き取ってください、耳を傾けてください。けれど、詩人は、絶望の淵に立っていながらも、そこは、闇で支配されているのではなく、光で満たされているのです。詩人が見ているのは、光です。5節を読むとそのことは、はっきりとわかります。詩人は、こう歌います。
5節「わたしは主に望みをおき、わたしの魂は望みをおき、御言葉を待ち望みます。」
詩人は、「魂」から望みを待ち望んでいるのです。心の奥深いところで、神に望
みをおく者は、神の御前から離れ去ることなく、平安と忍耐の内に自身の実を守る
ことができる。
詩人に忍耐を与え、詩人を堅固に支えたのは、「御言葉」への信頼です。御言葉
を心に留め、その救いの約束を確信するとき、私たちがたとえ深い淵の底にいたとしても、希望が与えられ、忍耐が与えられるのです。
生まれつき目が見えなかった男の存在は、それまで、「深い淵の底の」闇の中にあったと言えます。苦難の原因は、彼自身や、彼の両親に負わされてきました。彼は闇の中で、何に助けを求めたらよいかすらもわからなかったのではないかと思います。
けれど、ある日、主イエスという方が、きてくださいました。主イエスが目の前に現れ、「シロアムの池に行って目を洗いなさい」と一言言われた、そのときから、彼が一人で負ってきた苦難の人生は、彼自身のものではなく、神のものとなったのです。ずっと苦しんできた病は、神の業が現わされるためにある、とはじめて、積極的な意味を与えられたのです
目の見えない病の中で、闇しか見えなかった彼は、目の前に「真の光」を見ました。そして、その光は、輝き始めて、周りを照らし始めるのです。
ヨハネによる福音書1章4節と5節には、このような言葉がありました。
「言の内に命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は、光を理解しなかった。」
まさに、この御言葉が、目の見えない彼の上に、実現したのです。彼は、言葉そのものであるイエス・キリストと出会いました。神であるキリストに出会いました。そして、目の前のキリストの中に、光をはっきりと見ました。彼がみたその光は、生まれてから一度も見たことがない、明るい、かけがえのない、光でした。
この奇跡の物語が伝えてくれること、それは、目の見えなかった彼の目が、肉体的に本当に見えるようになった、ということにとどまらず、その奇跡を通して、彼に主が関わってくださったことを通して、彼は、「本当の救い」、「本当の光」が見えるようになったということだと思います。目の前にいらっしゃるイエス・キリストと言う方が、誰であるのか、ということを知ったということ。それこそが、奇跡の出来事であると言えます
彼が背負っている苦難は、彼自身のものではなく、神のものとしてそこにあるということです。
この癒しの物語を通して、私たちは自分自身のことを考えます。じつは私たちもこの男と同じ存在ではないか。私たちは皆本当に癒されることを必要としているものです。人生を生きる中で、病、家族の事、災難、試練など、何度も苦難を経験します。そして最後に待っているのは、死ということです。そのような時、目の前が真っ暗になります。廻りが見えなくなり、この世界で自分だけ、暗い闇の中に放り込まれてしまったように思います。不安と思い煩い、孤独が取り囲みます。それは恐ろしい闇のるつぼのようです。もう死への道しか見えなくなってしまう時があります。神も主イエスも見えなくなってしまいます。自分だけ、なぜこのような目に遭うのか、自分だけがなぜこんなに苦しい思いをしているのか・・・。こんなことに遭うのは、自分に何か悪いことがあるのではないか・・。訳を知りたいともがきます。でも答えは与えられないのです。
更に、クリスチャンであるならば、こんな重荷を感じるでしょう。こんなに不安に陥り、思い煩いで心をいっぱいにして、絶望しているのは、神にゆだねることができないのは、わたしに信仰がないからではないか。それは、ちょうど、主イエスが目の見えない男の目に泥を塗って、ますます目が見えなくなったと感じるようなことです。しかし、主イエスは、この男にシロアムの池に行って泥を洗い流しなさいと言われたのです。主イエスの言葉どおりにシロアムに行って洗い流したのです。すると、目が見えるようになりました。
この奇跡は、私たちにも行われているのではないでしょうか。
それはちょうど、礼拝に行って御言葉を聞きなさいという主イエスの言葉のように聞こえます。苦しい只中で、こんな時に礼拝になどいけないと思っても、礼拝に行って、罪の赦し御言葉を聞き、聖餐に与りなさいということです。その通りにすると、見えるようになるのです。神の前に生かされている自分、主イエスに罪を赦され、守り導かれている自分が見えるようになります。自分の絶望ばかり見ていた目が、キリストの十字架の救いを見ようと目を上げるようになるのです。この苦しみの中に、十字架の主がいてくださる。神が共にいてくださる。このことを乗り越えるように支えてくださっている。そして、そのことによって、神の御業がわたしの経験の中に現れるということが、分かるようになるのです。そこにいてくださる十字架と復活の主、この世界の全ての命の創造者と出会うことができるようにしてくださるのです。すべてはそこからまたはじまります。
そして、救いを与えられたものは、さらに、ある役割をも与えられているのです。それは4節の言葉です。
「わたしたちは、わたしをお遣わしになった方の業を、まだ日のあるうちに行わねばならない。だれも働くことのできない夜が来る。わたしは世にいる間、世の光である」。
「まだ日のあるうちに」とはどういうことでしょうか。それは、イエス・キリストがいらっしゃる時をさしていると思います。私たちは、「キリストがいらっしゃる時に」、「わたしのお遣わしになった方の業を」行わねばならないのです。それは、キリストと結ばれた者にとっての、大きな役割です。主は、マタイによる福音書の最後に、「見よ、わたしは世の終わりまで、いつもあなたがたと共にいる」と言われました。キリストは、世の終わりまで、いつも、私たちとともにいてくださいます。キリストは目には見えなくても、今、ここに共にいてくださっているのです。その大きな愛によって、私たちに「信仰」を与えてくださって、神は私たちに生きてくださっています。だからこそ、私たちは、主の御言葉を常に礼拝で聞き、信仰によって、この社会で主のために働かねばならないのです。私たちが信仰によって働くとき、そこには必ず、主イエスがともにいてくださいます。そして、神の御業が行われます。けれど、私たちが、罪の内に、思い煩い、信仰の光を決してしまうことによって、闇の夜が来てしまう。その夜に捉えられたなら、そこから働きだすものは何もなくなってしまうのです。
キリストが、私たちに神の御業に参与するための役割を与えてくださっているとは、なんと幸いなことでしょうか。なんと、私たちの人生は、意味のある、喜びのあるものとされているのでしょうか。
私たちは、キリストがおられる、という信仰の光を大切にして、信仰者として、歩み出したい。そして、神の御業のために働きたいと思います。