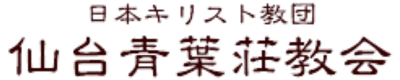使徒言行録7章44節-8章1節
「本当の保証とは」
牧師 野々川康弘
もし皆さんが、「神は何処にいるのか。」そう聴かれたとしたら、皆さんは、どのように答えるでしょうか。ある人は、「神は天にいる。」そう答えるかもしれません。確かにそれは正しい答えです。実際、聖書にはそう書いてあります。「じゃあ、神は天にいるとして、その神の国は、一体、何処にあるのでしょうか。」
今の時代、私たちは、神の国が空の上に無いことを知っています。
実は、神の国は、この世の何処かにあるわけではありません。聖書が言っている神の国は、人間の力で、決して到達することが出来ない、別次元の所にあるのです。
じゃあ、この世で生きている私たちは、そこにいる神と、何処で会うことが出来るのでしょうか。
ある方は、「それは私たちの心の内で出会うことが出来る。神は、私たち一人一人の内に居る。」そのように言うかもしれません。その通りです。でもそれも、微妙なところがあります。その理由は、その答えには、とても主観的な要素が含まれているからです。もし神と出会う事が、主観的なものであるなら、神と出会うことは、私たちのコンディション次第になります。もしそうであれば、神と出会うことが、とても不安定で、こころもとないものになります。
確かに、私たちの気持ちが高まっている時に、「神は自分の内にいる。」そう感じます。でも、私たちの気持ちは持続しないのです。ちょっと調子が悪くなれば、「神は自分の内にいる。」そういう思いが、直ぐに消えるのです。その結果、「神は自分の内にいる。」そういう思いが消えてしまう恐怖から、無意識の内に「神は私たちの内にいる。」そう自分に言い聞かせるようになるのです。何故、そのように自分に言い聞かせるのでしょうか。それは、「本当は、神は自分の内にいないのかもしれない。」そういった不安を、打ち消したいからです。
更に言うと、ちょっと自分にとって嫌なことが起こった時に、「神なんて知るか。自分は自分が思ったことを言う。」そう思うのではないでしょうか。それが意味しているのは、「神なんて自分の内にはいない」そうしてしまっているということです。
それが、私たち罪人の姿です。もし、そういうことが無い人がいるのであれば、それはとても幸いなことです。でも実際は、そういう人は、まずいないと思います。
罪深い私たちは、「神がいる」という事実に、目を向けないのです。自分が何となく神を感じられるか、感じられないか。そこに生きてしまう。
それが意味しているのは、人間は、どこまでも自分を人生の主人公として、いつも生きているということです。
でもキリスト者は、神を、自分の人生の主人公としているのです。
ということは、「自分の心の中に神がいる」という答えは、私たちの感情次第で、変化してしまう答だからこそ、「神は何処にいるのか。」という問いの答としては、不正解とまでは言わなくとも、ちょっとずれた答だと言わざるを得ないのです。
そうであれば、「神は本当に何処にいるのでしょうか。」
最初の方でも申し上げました。神はこの世とは、別次元に居ます。でもその神と、何処で出会うことが出来るのでしょうか。実はこれはとても大きな問題です。
模範的な回答として、よく言われるのは、「神に会うことが出来る場所は、教会の礼拝である。」そういう答えです。確かにそうです。教会の礼拝で、神に会うことが出来ます。それがキリスト者の、信仰です。じゃあ私たちは、どうしたら、教会の礼拝の場に居る神と、出会うことが出来るのでしょうか。
実は、そのことが良く分かるのが、今日の箇所です。
今私たちは、ステファノが裁判で語ったことを学んでいます。彼は、モーセの律法と、神殿を汚したことを疑われて、裁判にかけられて、裁かれているのです。
その裁判で、ステファノが、エルサレム神殿について語ったのが、今日の箇所です。
彼の神殿に関する主張の中心は7章48節です。そこには、「いと高き方は人の手で造ったようなものにはお住みになりません。」そう記されています。
つまりステファノは、神は神殿に住んでいない。そう言ったのです。彼が力を込めて、そう言ったのは、ユダヤ人たちや、ユダヤ教の指導者たちが、「エルサレム神殿は、神が住んでいる場所だ。そこに行けば神に会える。」そう考えていたからです。でも、それだけではありません。彼らは、神が住んでいると思っている神殿を、所有していることを誇り、神が住んでいると思っている神殿に定期的にかよっている自分の行為に、安心感を得ていたのです。
これは他人ごとではありません。私たちも、神が教会に居る。そこに行けば神と会える。そういうところから、自分の安心感を見出している可能性があるのです。つまり、会堂という目に見える建物を持っていて、会堂に通うという自分の行為に、自分の安心感や、自分の支えを求めているなんてことがあるのです。
実際にイスラエルの民は、目に見えるエルサレム神殿を、自分たちが神に選ばれた、神の民である印として、「そこにお参りにさえいけば、神の守りと祝福を得ることができる。」そう思って、エルサレム神殿があることに安心感を抱いていたのです。
でも、それに対してステファノは、「神は人間が手で造った神殿などには住まない。」そう反論したのです。
ステファノが、人々から憎まれて、キリスト教会最初の殉教者となったのは、そのことを主張したからです。
じゃあステファノは、神が何処にいると考えていたのでしょうか。またどういうふうに、神と会うことが出来ると、信じていたのでしょうか。
実は、その答えを言うために、ステファノは、神殿が建てられる以前の、イスラエルの民の歴史を語ったのです。
イスラエルの民は、モーセの導きで、エジプトを脱出した後、40年もの間、荒れ野で放浪をしました。その時代、イスラエルの民は、44節に記されている「証の幕屋」で、神と会っていたのです。
「証の幕屋」とは、「臨在の幕屋」のことです。そこが、神が、イスラエルの民と出会う場所であり、イスラエルの民が、神の民として、神を礼拝する場所だったのです。
「証の幕屋」の造り方は、出エジプト記26章-29章にかけて、詳しく記されています。そこには、いろいろな細かい寸法まで記されています。
「証の幕屋」で最も大事なことは、テントのように分解して、持ち運ぶことが出来ることだったのです。
イスラエルの民は、荒れ野の放浪生活の中で、神から、「出発しなさい。」そういう命令を受けると、幕屋を即座に分解して、それを担いで出発したのです。つまり、「証の幕屋」は、特定の場所ではなくて、旅路の途中で、神と会い、神を礼拝するために、持ち運んでいたものなのです。
でもそれは、人間の都合に合わせて、神殿を簡略化していたからではありません。そのことは、44節後半をみれば分かります。そこにはこう記されています。「見たままの形に造るようにとモーセに言われた方のお命じになったとおりのものでした。」
つまり「証の幕屋」は、荒れ野を旅するイスラエルの民のために、簡略化されたものではなかったのです。そうではなくて、神が、イスラエルの民に求めた礼拝の場が、「証の幕屋」だったのです。
神は、特定の場所や建物ではなくて、イスラエルの民が、荒れ野を歩む旅路の途上に留まった所で、その都度、礼拝を受けて、イスラエルの民と出会っていたのです。それが神の御意志だったのです。
じゃあ、その「証しの幕屋」の中には、一体何があったのでしょうか。それは「契約の箱」です。
「契約の箱」が、神からイスラエルの民に与えられたのは、主なる神が、イスラエルの民の神となり、イスラエルの民が、神の民となるというシナイ契約を、神とイスラエルの民が結んだからです。
因みにシナイ契約に至ったのは、かつてのアブラハム契約があったからです。アブラハム契約は、創世記12章1節~3節に記されています。そこを見ますとこう記されています。「あなたは生まれ故郷/父の家を離れて/わたしが示す地に行きなさい。わたしはあなたを大いなる国民にし/あなたを祝福し、あなたの名を高める/祝福の源となるように。あなたを祝福する人をわたしは祝福し/あなたを呪う者をわたしは呪う。地上の氏族はすべて/あなたによって祝福に入る。」
この契約があったからこそ、神がモーセを用いたのです。イスラエルの民を、エジプトの奴隷状態から救い出して、解放する救いを、齎したのです。そしてシナイ山でモーセに、主なる神が、イスラエルの民の神となり、イスラエルの民が、神の民となるという、そういうシナイ契約を与えた時に、モーセの十戒が入った「契約の箱」を、イスラエルの民に与えたのです。
ということは、イスラエルの民が、荒れ野の旅で、持ち運んでいたのは、シナイ契約だったということになります。
余談ではありますが、ヘブル語で契約を結ぶことを、契約を切ると言います。契約を切るということで、思い出されるのは、創世記15章17節です。そこを見ますと、「日が沈み、暗闇に覆われたころ、突然、煙を吐く炉と燃える松明が二つに裂かれた動物の間を通り過ぎた。」そう記されています。これは、アブラハム契約の締結の言葉です。17節が意味しているのは、神がアブラハム契約を破ったなら、命ある動物が、二つに割かれて死んでいるように、神は、御自身が二つに割かれて死ぬということです。
煙を吐く炉と燃える松明とは、神のことです。二つに割かれた動物の間を通り過ぎたとは、神が契約を破ったなら、御自分が二つに割かれて死ぬという神の宣言です。
イスラエルの先祖アブラハムは、その神の契約が与えられて、神と共に旅立ち、旅の途上で礼拝し、礼拝したその場で、神と会い、交わっていたのです。
話を今日の箇所に戻します。シナイ契約が、イスラエルの民に与えられた時に、契約の箱が与えられました。その契約の箱を納めた幕屋が、「証の幕屋」と呼ばれた理由は、礼拝の度に、アブラハム契約に基づいて、神がシナイ契約を与えて下さったことが、証される幕屋だったからです。つまり「証し」とは、神の言葉が与えられたことを、証しすることなのです。
「証の幕屋」の礼拝は、神の契約、つまり、神の言葉が与えられたこと。そのことを証する礼拝だったのです。
つまり、ステファノが、今日の箇所を通して言っているのは、「もともとイスラエルの民は、神を神殿に縛りつけて、そこで神と出会って、神の祝福を得ようとする礼拝ではなかった。」そういうことなのです。
ステファノが今日の箇所を通して言っているのは、「アブラハム契約に基づいて、主なる神が、イスラエルの民の神となり、イスラエルの民が、神の民となるというシナイ契約が与えられたこと。そのことが証される場所が、つまりは、神の言葉が、与えられたことが、証される場所が、神がいる場所であり、神と交われる場所なのだ。」そういうことです。
ユダヤ人たちや、ユダヤ教の指導者たちが大切にしていた神殿は、ダビデとソロモンの時代に、エルサレムに建ちました。そのこともステファノは、46節~47節で言っています。
もともと神殿は、神が住んでいる場所ではなくて、荒れ野の幕屋の精神を、受け継いだものなのです。
神殿を神に献げた時、ソロモンは、神に祈りを捧げています。その時の祈りが、列王記上8章22以下に記されています。その祈りの中で、ソロモンが、こう祈っているところがあります。「神は果たして地上にお住まいになるでしょうか。天も、天の天もあなたをお納めすることができません。わたしが建てたこの神殿など、なおふさわしくありません」
実は48節の、「けれども、いと高き方は人の手で造ったようなものにはお住みになりません」という言葉は、そのソロモンの祈りの言葉を踏まえて、ステファノが言っていることです。
また、49節以下が、引用しているのは、イザヤ書66章1節~2節の言葉です。そこを見ますと、「主はこう言われる。天はわたしの王座、地はわが足台。あなたたちはどこに/わたしのために神殿を建てうるか。何がわたしの安息の場となりうるか。これらはすべて、わたしの手が造り/これらはすべて、それゆえに存在すると/主は言われる。わたしが顧みるのは/苦しむ人、霊の砕かれた人/わたしの言葉におののく人。」
つまりステファノは、「ソロモンも、イザヤも、「神殿に神がおられるのではない!」そう言っていた。」そう言っているのです。
つまりステファノは、ソロモンや、イザヤと同じことを言っただけなのです。そうであるにも関わらず、神の住まいである神殿を、冒涜したという罪で、裁かれたのです。
ステファノがそんな目にあったこと自体、イスラエルの民が、荒れ野で、証の幕屋礼拝をしていた精神を、失っていた証拠なのです。ステファノは、証の幕屋礼拝の精神を、失っていることを、厳しく批判したのです。
でも何故ステファノは、ユダヤ教の指導者たちが、間違った礼拝をしていることを、鋭く指摘出来たのでしょうか。
それはステファノ自身が、本当の神と出会って、交わっていたからです。生き生きとした、神の言葉がちゃんと、明かされる礼拝を、体験していたからです。
神の言葉が、ちゃんと明かされる礼拝とは、「『主なる神が、イスラエルの民の神となり、イスラエルの民が、神の民となる』そういうシナイ契約を、いつも破ってしまう愚かな私たちは、本来、死んで滅びないといけない命でしかない。でも神は、アブラハム契約を、ちゃんと覚えていて下さり、私たちを大いなる国民にするために、別の言葉で言うと、私たちを大いに祝福するために、御自分の、とても大切な独り子主イエスを、私たちがシナイ契約を破る、罪の身代わりとして、十字架に架けて、私たちがいつも、シナイ契約に生き続けることが出来るようにして下さった。また主イエスは、死から復活して、昇天する御業を通して、聖霊を、私たちの内に内住させ、シナイ契約を、いつも守っていけるようにして下さった。」ということなのです。そのことを解き明かされる礼拝を、彼は体験していたのです。
そしてそれが、今の私たちの礼拝です。もっと厳密に言うと、今の私たちの教会の礼拝は、シナイ契約を、いつも覚えることをしていた「証の幕屋」礼拝が、成就したことを感謝する礼拝をしているのです。
シナイ契約の成就を、心から感謝していたステファノは、本当に生きて、働いておられる神を知っていたのです。だから彼は、心から、主イエスの救いを、感謝する礼拝が出来ていたのです。
そんな彼だったからこそ、神殿で、礼拝する自分の行為を通して、自分の中に神がいることを、必死に自分で言い聞かせて、それによって安心感を得ようとする愚かさを知っていたのです。
私たちもステファノと同じように、自分の内に、神がいることを、必死に自分に言い聞かせて、安心感を得ようとする愚かさを、知らなければならないと思います。
そうでなければ、「神はどこにいるのか。あなたは神と、何処で会うのか」そういう質問を受けた時、目に見えて分かるもの。自分に安心感を齎すマニュアル。それを人々に指し示すことになります。でもそこに神は居ません。
私たちにとって、とても大切なことは、主イエスの救いの御業を通して、主なる神が、私の神となり、私が、神の民となることを、成就して下さった主イエスを、心から喜ぶ礼拝体験をすることです。
つまり、主イエスが、ちゃんと自分の信仰を握って下さっているということに、感謝する礼拝を体験することなのです。そして、「その礼拝体験を出来る所が、神がいるところであり、神と出会えるところである。」そのようにちゃんと、言えることなのです。
じゃあ、神を心から喜ぶ礼拝体験、神が自分の信仰を握ってくれているという確信が与えられる礼拝体験は、どうしたら与えられるのでしょうか。そのヒントが、51節です。そこでステファノは、「かたくなで、心と耳に割礼を受けていない人たち、あなたがたは、いつも聖霊に逆らっています。」そう言っています。
頑ななユダヤ人たちや、ユダヤ教の指導者たちは、聖霊に逆らっていました。聖霊に逆らう人たちは、自分の神理解が正しい。そう思っていたり、自分が癒される神像ばかりを、追い求めたりしているのです。そういう人たちは、聖霊が指し示す、本当の、主イエスの救いを受け入れることが出来ないのです。その結果、主イエスの救いの御業を、感謝する本当の礼拝を、体験することが出来なくなるのです。
真に、ユダヤ人たちや、ユダヤ教の指導者たちがそうだったのです。その一方で、ステファノは、聖霊の働きを求めて、祈る人でした。その証拠が6章5節です。そこを見ますと、彼のことを、「信仰と聖霊に満ちている人ステファノ」そう紹介しています。
彼は、自分に内住している、聖霊の働きを信じ、いつも聖霊の働きを、祈り求める信仰深い人だったのです。
ステファノは、聖霊の働きを信じて祈り、命の言葉である、神の言葉をちゃんと待ち望んで、心を開いて聴く礼拝をしていた人だったのです。だからこそ彼は、生きてこの世で働いている神と、豊かな交わりが与えられていたのです。
今日の私たちの礼拝は、ステファノが守っていた礼拝と、全く同じ礼拝です。
私たちは今日、聖書朗読と、聖書の説き明かしを通して、主イエスの救いが、証されている御言葉を聴いています。
主イエスは、この礼拝で、聴くことの出来る聖餐である御言葉の解き明かしを通して、私たちの真ん中にいて下さり、豊かな交わりを、私たちと持って下さっているのです。
そのことを、実現させてくれているのが、聖霊です。
私たちは、その聖霊の働きを信じ、聖霊の働きを祈り求めつつ、御言葉の解き明かしに与ることが大切なのです。そこにこそ、生ける真の神との交わりが、生まれるのです。
ステファノの、神の救いを証する、純粋な説教を聴いて、それに反発した人たちは、怒り狂って、彼を都の外に引きずり出して、石を投げつけて殺したのです。
神の救いを証する、純粋な説教をする人は、自分の手で、自分自身の確かさを、保して生きようとしている人たちの、憎しみや、殺意を、引き起してしまうのです。
ステファノは、自分の手で、自分自身の確かさを、確保して生きようとしていた人たちの手によって、キリスト教会最初の殉教者となったのです。
でも、死んでいく苦しみの中で、彼は55節~56節に記されている通り、神の栄光と、神の右に立っている主イエスを見たのです。
ステファノが、礼拝で交わっていた主イエスが、自分の手で、自分自身の確かさを確保して、生きようとしている人たちの憎しみにより、今正に殺されようとしていたその時に、ステファノに、御自分の存在を、はっきり示されたのです。
ステファノが見た主イエスは、神の右に立っていたのです。つまり、天の王座に立っている主イエスが、ステファノをそこへ迎えるべく、立っていたのです。それをステファノは、はっきり見たのです。
石を投げつけられて、殺されるその苦しみの中で、ステファノは、その主イエスに向かって、「主イエスよ、わたしの霊をお受けください」そう言ったのです。
そして、主イエスに、自分の命を委ねたのです。そこには、大勢の人たちのリンチ殺人という場面に、そぐわない不思議な平安があります。
ステファノの中にあった不思議な平安が、彼に言わしめた言葉が、「主よ、この罪を彼らに負わせないでください」という祈りだったのです。その祈りをもって、彼は死んだのです。
「主イエスよ、わたしの霊をお受けください」、「主よ、この罪を彼らに負わせないでください」、これら二つの言葉は、主イエスご自身の、十字架の上での最後の言葉と重なります。
ステファノは、主イエスと同じ死を遂げたのです。
それはステファノが、自分を殺す人をも、赦すことが出来る、立派な人だったということではないのです。そうではなくて、彼の中に住んでいる聖霊が、礼拝で、彼を主イエスと出会わせて、主イエスとの交わりを、持たせたからこそ、主イエスを追体験する人になったのです。
最初の殉教者ステファノは、私たちに与えられている礼拝と、同じ礼拝の恵みの中で生きた人だったからこそ、苦しい中にあっても、死を目前にしても、神の救いの恵みに満たされて、死ぬことが出来たのです。
私たちも、神の救いの恵みに満たされて、ステファノのように、主イエスを追体験して、この世で生きていくことが出来たらと思います。
でもそれは、自分の力で、到底出来ることではありません。
それが出来るようになるのは、自分が欲っする目に見える保証を捨てて、つまりは、自己承認欲求を捨てて、聖霊に自分の身を委ねて、聖霊と共に生きる歩みをしていってこそ、主イエスを追体験することが、可能となるのです。
私たちが、主イエスを追体験していくこと。それが本当の意味で、保証された私たちの人生になるのです。
そのことを覚えて、今週も皆さんと共に、豊かに歩んでいけたらと、心から願っています。
最後に一言お祈りさせて頂きます。